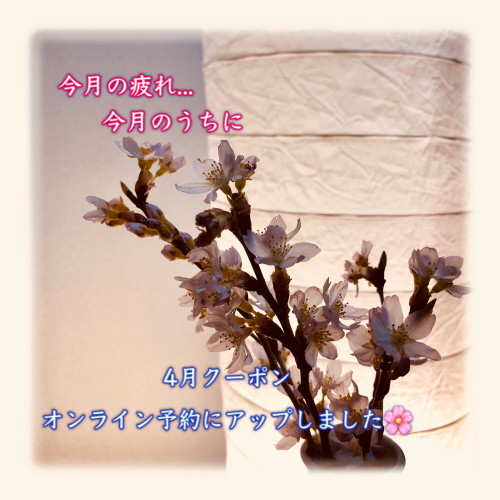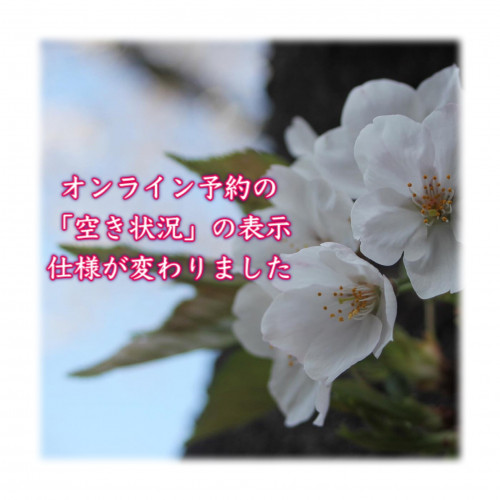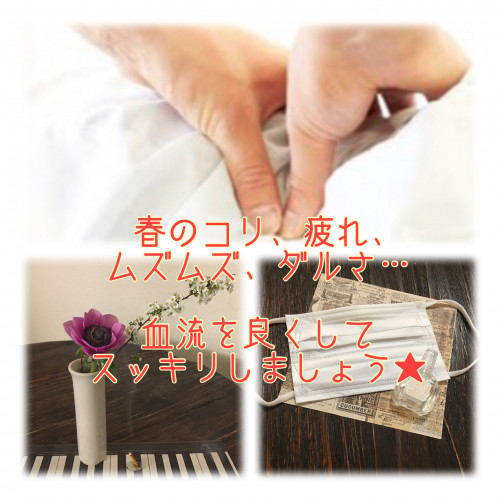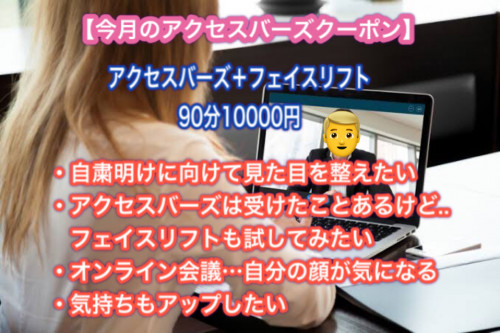♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ
「推し」が心の免疫に
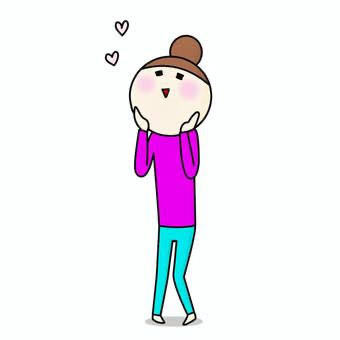
最近、「推し活」というのが流行っているそうです。
もともとはアイドルや好きなアーティストを
応援すること、いわば「追っかけ」から来ていますが
今や、対象は人だけでなく、アニメのキャラクターやモノにまで。
それは
単純に「好き」という気持ちだけでなく
誰かを応援し、その人の幸せを願うこと…
誰もが心理的に
「慈しむ対象」
を持つことで、心のバランスを保っていて、
応援しながら自分も精神的に支えられているため、これが多くの人の「心の免疫」になっているんだとか。
何かにときめいたり、夢中になっている時は
ドーパミンが出るそうです。
ドーパミンは、やる気を巡らせて前向きな好循環を生むガソリンなので
・幸せな気持ちになり意欲に繋がる
・集中力がアップ
・ポジティブになれる
といったことが脳内で起こります。
そんな私も人に推されて?某アニメにどハマりしたわけですが笑
その話で誰かと盛り上がったり、熱く語ったりする時間て、とても楽しいものです。
最近、それぞれのお客様と
色んなジャンルのマニアックな話で盛り上がり、ドーパミン効果頂いてます♡
(調子に乗るとマシンガントークになります、すみません)
そしてお客様のペットの話やハマっているものの話をしている時って本当に楽しそうで、
その話を聞くのがとても好きです。
何かにハマること
夢中になること
誰かを応援すること…
それは心と体の健康や魅力にも繋がるかもしれません。
これがあるから、頑張れる
そんな「推し」ありますか?
ご予約はこちらから💁♀️🔽
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
※予約システムの「空き状況の表示」が変わりました。詳しくは🔽🔽
背中の痛み、息苦しさの原因は?【アンケートより】

今日もアンケートからのリクエスト記事
「最近、背中が痛くて息苦しい感じがします。対処法はありますか?」
背中の痛み、息苦しさを感じる方、増えています。
背中に痛みの原因は様々ですが
ざっくり言うと
・筋肉の疲れ
・内臓の疲れ
・神経疾患
・ストレス
が考えられます。
🔹筋肉の疲れ
多くは長時間のデスクワークにより座りっぱなしや猫背になることで、背中そのものの筋肉が原因というよりも
お尻が圧迫されたり、脇の下、腕、首
などから来ることが多いです。
🔹内臓の疲れ
食生活などで胃腸や肝臓、腎臓などの疲れが
背中の痛みを誘発する場合もあります。
🔹神経疾患
背中の骨がずれたり縮んだりすることで背骨の間を通っている神経を圧迫して痛みが生じるというものです。(何らかの理由によって肋間神経が圧迫・刺激されることで胸や背中に鋭い痛みが走る「肋間神経痛」など)
🔹ストレスで背中が痛い理由
息苦しさが伴う場合は
疲労、極度の緊張等で自律神経のバランスが崩れることで生じると考えられています。
自律神経のバランスが崩れると、胃酸が必要以上に分泌されて、胸の辺りが異物感を感じたりします。
自律神経の働きが十分に行われなくると、血流が悪化して筋肉が凝ってしまい、筋肉のコリがリンパの流れを滞らせることにもつながります。
筋肉のコリやリンパの流れの悪さは互いに悪循環を促し、背中の筋肉に痛みを感じさせてしまいます。
またストレスなどで眠りが浅くなると
疲れが充分にとれすま、疲労はどんどん蓄積されていきます。
少しずつ蓄積された疲労が内臓に負担をかけ、その結果として筋肉の状態をアンバランスにさせるといわれています。
筋肉がアンバランスになってしまうと背骨を歪め、痛みを発することも神経疾患の原因に…
また脳の機能とも関係があり
強いストレスによって脳の機能に不具合が生じると「身体化」という、もともと身体的には健康であるのに、脳が身体機能に制御をかけることによってさまざまな症状が現れます。背中の痛みもその一種と考えられます。
筋肉の疲れやストレスから来る場合は
血行やリンパの流れが悪くなっていることで筋肉が凝り固まってしまうのが原因なので
マッサージやストレッチで血流を促し、筋肉の動きをスムーズにしてあげるのが効果的です。
背中は全身の中央に位置し、他の部位とも繋がっているため、部分的ではなく全身のマッサージで全身の血流をよくすることで、背中にもしっかり血液がいきわたり、冷えやむくみの解消にもつながります。
冷え自体も体をこわばらせ、背中痛の原因にもなるので、血行を促すことはとても大切なのです。
それでも良くならない場合は
肝臓や胃腸、腎臓などが疲れているサインかもしれません。
極度に心配する必要はないと思いますが
油ものや甘いものなど控えるなど胃腸に負担がかからない食事をオススメします。
🍀背中を伸ばすセルフケア
①まずはバスタオルを巻きます。
②床①を置きその上に膝をたてて仰向けになり、寝転ぶだけ。
肩甲骨の下あたりにバスタオルが来るようにしましょう(タオルは背骨に対して縦ではなく横に置きます)
万 肩甲骨の少し下のタオルをあてることで、自然と胸椎が伸ばされ、ストレッチになります。手を上げて万歳すると、より胸椎が伸ばされます。
呼吸が浅いと感じている方にもオススメです。
奏では背中の痛み、息苦しさには
肩甲骨周りだけでなく、鎖骨や腕、脇の周りの施術でしっかり緩めていきます。
アロマトリートメントはリラックス効果もあり
ストレスからの背中の痛みにはオススメです◡̈
アンケートでリクエスト頂きましたお客様、ありがとうございました♡
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
※予約システムの「空き状況の表示」が変わりました。詳しくは🔽
頭のおしゃべりを止める

眠りが浅いというご相談が増えていますが
原因のひとつとして
「頭のおしゃべりが止まらない」ことがあるかもしれません。
ピンとくる方…
考えたくないのに、ついつい考えてしまうことってありますよね。
仕事のこと
人間関係のこと
未来や過去のこと
「○○だったらどうしよう?!」
「あれは○○だったかな・・・」
「あの人○○って言ってたなー」
考え出すと止まらない、
グルグル考えすぎてしまう
残念ながらシロクマ効果と言って
考えないようにしようと思えば思うほど
止まらなくなります。
(※シロクマのことを考えないでください!と言われるとシロクマのことばかり考えてしまうという研究による実験結果)
頭の中のおしゃべりを止めるには
目の前のことに集中することです。
ゆっくりと景色を眺めたり
好きな音楽を聴いたり
お風呂に入ってリラックスしたり
散歩もオススメです。
でも
布団の中だから…!
って話になります。
そこで
「ゴムバンド法」という方法があります。
米国の心理学者?の研究では
良くないイメージが頭に浮かぶたびにゴムバンド法を試したところ
1週間ほどでよくない嗜好が浮かばなくなり、9か月後の再検査でもゼロのままで、しかもゴムバンドを外しても元に戻らなかった、という報告を行っています。
手首にゴムを巻いておいて、頭のおしゃべりが始まったら、そこでパチンとゴムをはじく。その刺激を合図に「あ、そうそう。ネガティブな思考は止めよう」という意識する。
これを何度か繰り返すうちに、ネガティブな思考癖が消えていくんだとか…
これはタバコや食欲など
どうしても治したい癖や習慣があるときも
この作業を繰り返すうちにタバコと痛みの感覚が結びつき、やがて自然とタバコを遠ざけるようになっていくそうです。
このとき、痛みが強ければ強いほど効果がアップするといいます。
四六時中思考していると、脳の仕組みでそれを呼び寄せようとするので、ますますそのような現実が現れるようになります。
例えば、何かを批判をすれば、ますます批判したくなるような人や情報ばかりに脳が興味を持たせ呼び寄せるからです。
だからこそ、逆に
頭のおしゃべりが始まったら
恵まれていることや感謝できることを
頭の中でリストアップすることで
脳は意識した事をどんどん拡大して行く働きがあるので、潜在意識は今度はますます感謝できることや、嬉しいことや楽しい事を呼び寄せようと働くのです。
これを習慣にすると、人生を作っている脳の記憶領域の中に入っているデータが、プラスのデータが多くなって
いわゆる「運が良い」ということにつながるそうです。
体や心が疲れていると
脳に「疲れたなぁ」という言葉ばかりになるので
疲れたらこの都度リセットすることも大切です。
頭のおしゃべりにはアクセスバーズも◉
ご予約はこちらから💁♀️🔽
3月クーポン★心と体をリセットしましょう!

三寒四温と言われる今の時期
冬のように寒かったり
春めいて暖かったり
気圧の変動や
環境の変化など
体がついて行かず
体調を崩しやすい時期でもあります。
でも春はデトックスに最適。
冬に溜め込んだ老廃物をこの時期に
しっかり出すことが
春に元気にパワフルに動くカギになります。
老廃物が体に溜まったままだと
花粉症や不定愁訴など、いわゆる
"春の不調"が出やすくなってしまいます。
そして
年始から人と会うことやお出かけなどが
制限され
気持ちのリフレッシュができず
思っている以上に心もストレスと
戦ってきたかもしれません。
3月、
心身ともに要らないものをデトックスして
心地良く春を過ごす準備をしましょう。
クーポンはお客様ひとりひとりの状態に合わせて
指圧、オイルフット、ドライヘッドスパ、
お顔、ハンドマッサージ、ストレッチ…
組み合わせ自由です。
(※アクセスバーズ、全身アロマは組み合わせ不可)
ここをたくさん圧してほしい!
何が原因だかわからないけど痛い(辛い)
呼吸が浅い、
眠りが浅い、
体がだるい、やる気が出ない、
目が疲れている、
気持ちをリセットしたい…
ご相談ください。
いつもありがとうございます。
ご予約はオンライン予約をご利用頂けると助かります
睡眠力アップ!深く眠るためのストレッチ【アンケートより】

本日はアンケートからのリクエスト記事
「寝つきが良くなる・深く眠れるストレッチを教えて欲しい」
疲れているのに眠りが浅い、寝ても疲れが取れていない
するとどんどん疲れが蓄積することに…
疲れをとるための睡眠を深くするための
ポイントは
股関節
です。
長時間のデスクワークや同じ姿勢を続けると
体の関節の血管とリンパ管が圧迫され、血液やリンパ液の循環が滞ります。
特に股関節は一番面積が大きいので、
座りっぱなしなどで多くの血管やリンパ管が折れ曲がります。実際、4時間座っている姿勢を続けると、血流量が10%も低下することがわかっています。
大きな関節を緩めると身体の緊張がほぐれ、巡りが良くなります。
血流がスムーズになって体温が上がると、副交感神経が刺激されてリラックスできるのです。
同時に深い呼吸がしやすくなり、疲れがとれやすい状態に身体を導きます。
そして
血流が良くなることで自律神経も整うため、質のいい睡眠に繋がります。
そのためには股関節の“開放”
一番簡単な方法は
仰向け合せきのポーズ
・仰向けになり、両膝を立て、外側に開きます。
・左右の足裏を合わせ、かかとをお尻の近くに引き寄せます(膝は浮いてもOK)
・両手をバンザイし、肘が床につくところまで開いて深呼吸しながらリラックスし30秒キープします。
そして
私が色々と試した結果、眠くなるのは
温冷交代浴。
温冷交代浴は、もともとヨーロッパで温泉療法の一つとして行われてきたもので
睡眠効果や疲労回復や筋肉痛の緩和にも◉
温冷交代浴で起きる体の変化
まず温かいお湯に浸かると、温熱効果で血管が拡張します。次に冷たい水が体に触れると、筋肉と血管が収縮します。
このように血管が拡大と収縮を繰り返すことによって、血管のポンプ作用がアップします。そして全身への血流がよくなり、滞りがちな末梢の血行も改善することになります。
また、冷やした後により深いリラクゼーション効果が生まれるといわれています。
簡単にいうとお湯と水風呂を繰り返すので
銭湯などがベストですが
シャワーと浴槽を上手に活用すれば、ご自宅でも冷温交代浴は簡単にできます。
(1)軽く「かけ湯」をして、体をお湯に慣らす(2)40℃のお湯に3分間、肩まで全身浴で浸(3)手や足に先に水のシャワーをかける
(4) 首元に1分間水をかけます。
以上を3回繰り返します。
ポイントは水で終わること。
冷たすぎる場合は水温を上げてもok
こんな方は要注意。
高血圧の方、心臓や肝臓など内臓に持病のある方、発熱のある方、体調の悪い方は、避けましょう。
眠りの質を高めることは一番の疲労回復になりますが、
この時期は自律神経が乱れやすいので
眠りが浅くなりがちに…
奏では肩甲骨はがしだけでなく
股関節のストレッチも行っています★
寝る前の3分のひと手間の積み重ねが
体や心の元気に大きく影響するかもしれません。
リクエスト頂いたお客様ありがとうございました♡
ご予約はこちらから💁♀️🔽
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku