♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ
意外と知らない【血液の働き】とは
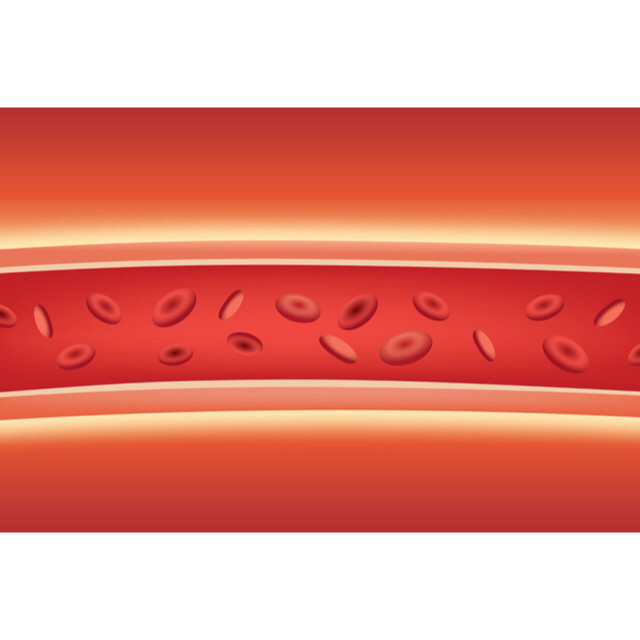
血流が悪ければ病気になりやすいとか
「血流」が大切だということは何となくわかっていますが
血液は「酸素と栄養を運ぶ」以外にも
とても大切な役割をしています。
・老廃物の回収
・免疫細胞を運ぶ
・体温調節
そして実は
情報伝達
という役割もしています。
体内での情報伝達は大きく分けて2つの方法があります。一つが神経、そして、もう一つが血液です。
特に脳がちゃんと機能するには、
安定した血流が欠かせないことと
現代の生活習慣が脳の血流に大きな影響を与えています。
人の脳は、重さは体重の2%しかないのに
体内の血液の15~20%を必要とします。
そして脳は筋肉の3倍、酸素を使うといいます。
血液は、その酸素をニューロンに送り届けて、ニューロンが効率よく働き、信号を送れるようにしているため
血流が十分でないと、ニューロンは死に始めるのだとか。
そして
血流は、脳にグルコース(ブドウ糖)も運んでいて
グルコースはニューロンのエネルギー源になります。
そして脳内の血流には、もう一つ重要な役割があり
それは
脳内に蓄積する老廃物を洗い流すこと
つまり
血流が悪くなると脳への栄養と酸素の供給が減り、
脳内に老廃物が溜まり
集中力、記憶力、創造力、判断力、認知機能と気分を司る脳領域がうまく働かなくなります。
でも…
以前は、大人になると新たなニューロンは生まれないと考えられていましたが
研究で、何歳になっても新しいニューロンを生み出すことができることがわかったそうです。
新しいニューロンを発生させるプロセスは
脳の海馬という部位で起き、脳の奥深くにあるタツノオトシゴのような形をした海馬は、記憶と学習に大きな役割を果たしています。
この海馬を活性化させる方法は…
軽い運動です。
やっぱり…
運動が良いのはわかっている!
耳タコ
だと思う方も多いかもしれません。
海馬は
βエンドルフィンという脳内物質のの分泌によって海馬の長期記憶が増強するそうなのですが
運動以外でβエンドルフィンを
分泌するにはアロマがオススメです。
好きな香りを嗅ぐとリラックス、鎮静作用のあるβエンドルフィンを分泌させます。
話は長くなりましたが
血液は流れてこそ、その働きを発揮させることができるのです。
血流促進には筋肉をほぐしたり緩めることも大切です。
なるべく良い血流を維持したいものですね◟̆◞̆
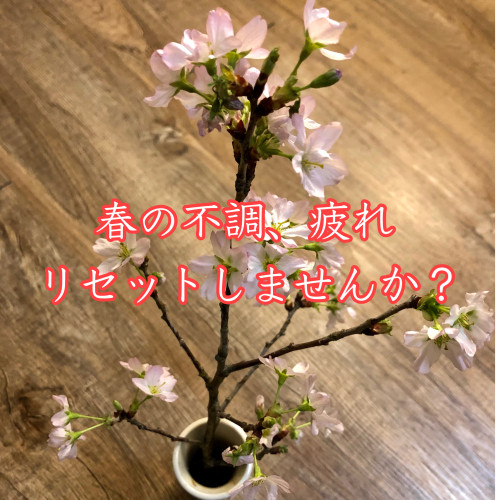
ご予約はこちらから💁♀️🔽
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
春は【目】が疲れやすい…?

この時期の目のトラブル
目の奥が痛む、目がチカチカする、
そして花粉が相まっての目のしょぼしょぼ…
実は春は花粉とは関係なく「目」トラブルが出やすい季節です。
なぜかというと
目の症状は、「肝」からきているとされ
肝は、「血」を貯蔵する働きをしているので
その血が不足すると目に栄養が届かなくなり、疲れ目や充血、視力低下が起こります。
肝はまた、涙の分泌をする自律神経のバランスをとる働きをしているため、肝の涙がうまく分泌されずドライアイをくことも…
そして
目は、周囲の情報をキャッチし、生きてゆくための重要な感覚器で
脳の情報の80%以上が視覚を通して集められているともいわれ、「脳の出張所」とも呼ばれます。
脳が疲れてくると、多すぎる情報をキャッチしないように無意識に視野を狭めるそうです。
眼精疲労は目自体に疲労が起きるわけではなく、自律神経の疲弊により引き起こされることがわかっています。
目の疲れは、首や肩のこり、頭痛、
また、集中力が落ちたり、注意力が散漫になったりすることも少なくありません。
目の疲れや痛み、充血といった症状は、心身が疲れていることを知らせるサイン。
まず、パソコンのモニターやスマホを見ていて疲れたなと感じたら、目を少し休めてください。
遠くを見たり、目の周りをマッサージしたり温めたりすると効果があります。
お茶に
「目薬の木」というものがあります。
江戸時代以前から眼病の特効薬としてよく知られており、目のかすみが解消されて、千里の先までよく見えるようになる、ということから「千里眼の木」ともいわれ
フェール配糖体のエピ・ロードデンドリンという成分が、目の疲れ、二日酔い、肝機能の向上、動脈硬化予防等に効果があるとされています。
整体では目は後頭部の筋肉とつながっているため
その周辺の筋肉を緩めること
またヘッドマッサージも目の疲れ解消になります。
目はとても、とても大切です。
目を駆使しすぎている現代社会…
特に春は目も労わりましょう。
春のダルさ、むくみの改善には…

春に起こるダルさやむくみ…
これは体の中の「水」が関係しています。
東洋医学的には
体内を流れる水分を津液(しんえき)と言い
血以外のすべての体液、
具体的には汗、涙、尿、よだれ、粘液などが挙げられます。
津液のはたらきは、全身を潤すことで
皮膚や毛髪、胃や腸などを潤すとともに、関節の働きを円滑にする管理などをしています。
そして身体の余分な熱やほてりを静めたり、汗や尿となり余分な老廃物を排出します。
血とは切っても切れない関係にあるため
血が不足すると津液が不足し、津液が不足すれば血も不足します。
水が不足したり、停滞すると…
流れている川の水はキレイですが
流れず停滞して濁ってしまうのと同じように
手足のむくみ、顔のむくみが出たり
お腹に余分な水がたまっていると、
食後に眠くなる、下痢などの症状が現れます。
体内の水(津液も)は
余っても不足してもダメで
適度な量でしっかり流れていることが大切です。
🔹津液を巡らせるには?
酸甘化陰(さんかんかいん)といって酸味と甘味を取ることで陰液(からだの体液)を作り出すと言われています。
甘味は砂糖ではなく、蜂蜜など自然な甘さのものをいいます。
蜂蜜が咳や風邪によいのは喉を潤す作用があるからです。
そして
いらない水分は尿か汗で出すこと
むくんでいるから水分は控えるという方もいますが、たまっている水は循環させたほうが良いです。
また鼻炎や指先のむくみなどは尿で出すより、汗で発散したほうが良いとされます。
春は激しい運動より、軽く汗ばむ程度の運動が
オススメです。
春のだるさ、むくみには理由があります。
そしてやはり血流も大切です!!
体、巡らせましょう★
【晴れの日の頭痛】と【雨の日の頭痛】

暦の七十二候では3/26あたりから
「桜始開(さくらはじめてひらく)」といい
読んで字のごとく、桜の花が咲くころ…
私も開花宣言の日に、桜を見に行きました。
気持ち良く晴れる日は気持ち良い春ですが
普段健康な人も、体調不良や特に「頭痛」のお悩みが増えてきます。
雨の日は頭が痛いのはよく聞きますが
実は晴れの日に頭痛が出るという体質もあります。
雨の日の頭痛は
水の巡りが悪い「痰湿(たんしつ)体質」の方がなりやすいとされます。
胃腸が弱ったり、水分や冷たい物の食べ過ぎなどで、からだに余分な水分(痰湿)が生じている状態で
痰はネバネバした性質、湿は重くじっとりした性質なので、それが体の中にもある状態と考えると
頭痛が起きるのも何となくわかります。
逆に
晴れの日の頭痛は
熱がこもったり、上昇しやすい人、
一概には言えないですが「肝」が弱っている人が出やすいとされます。
イライラしたり、カッカしたり、テンションが上がりすぎると体内の陽の気が上昇しますが
晴れていて外の陽気も上昇すると、つられて上昇しすぎて頭痛が出たりします。
特にストレスで噛み締め癖があると、晴れの日に頭痛を誘発しやすくなります。
同時に目の充血や、便秘、体の火照り感なども起きる場合も…
天気の影響で頭痛が出るときは
耳を軽く引っ張ったりクルクル回すことで
内耳のリンパの流れが良くなり痛みが緩和する場合があります。
ちなみに私は
雨の日の翌日に一気に晴れた時に体が重だるくなりますが
同じような方がいらっしゃるかもしれません。
また春は、それに相まって
寒暖差、環境の変化が大きく自律神経が大きく乱れます。
どちらにせよ頭痛が出やすい時は
疲れが溜まっている
血流や水の流れが滞っている
睡眠がたりない
胃腸が疲れている
そんなサインでもあります。
急激な寒暖差と
落ち着かない世の中の動きも相まって、心身ともに疲れがちですが
桜が美しい春を心地良く過ごすために
天気とも上手に付き合っていきたいですね。

ご予約はこちらから💁♀️🔽
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
【ホメオスタスシス】のはなし

桜が開花したと思ったら、雪が降ったり、また暖かくなったり…
気温の変化に対応するのに大変💦
このように寒暖差も激しい春は、体や心に想像以上に多大なストレスが加わり、さまざまな不調につながります。
そんなとかこそ知っておきたいのが
「ホメオスタシス」です。
ホメオスタシス(homeostasis)とは、簡単にいうと
生体が変化を拒み、一定の状態を維持しようとする働きのことで「恒常性」とも呼ばれます。
変化を拒むので、一見、邪魔な存在な気がしますが健康的に生きていく上でとても重要な働きをしています。
気温や気圧など、場所・時間によってさまざまに変化する体外環境は私たちの体の細胞レベルにまで及びます。
でも、体には、体外環境が変化しても体内の環境を一定に保とうとするしくみがあります。
それが「ホメオスタシス」で
例えば、
暑い時は、体温を下げるために汗をかきます。
寒い時は、体温を上げるために体を震えさせます。
他にも
・身体のなかに細菌などの異物がない状態を保つ
・軽いけがや風邪も時間が経てば健康な状態に戻る
・塩分濃度や血糖値など、体液の組成を一定に保つ
・体内の水分量を一定に保つ
・ダイエットしても体重は一気には減らない
つまり気象の変化や周りの環境に自分の体を適応させ、安定した状態を保つため、体には生まれ持った防御機能が備わっています。
ホメオスタシスは「自律神経」「内分泌」「免疫」3つの機能のバランスによって成り立っています。
しかし、ストレスにさらされ続けると、ホメオスタシスには過度な負荷がかかります。
すると、3つの相互作用が崩れてバランスを失い、さまざまな病気や体の変調を生んでしまいます。
そして、ホメオスタスシスは体だけでなく
心(心理的)にも働きます。
「今のライフスタイルや環境をなるべく維持しよう」という心理です。
頭では変わりたい、考え方を変えたい、性格を変えようなんて思っていても
無意識の部分では変わらないように拒みます。
脳は、自分の生命維持をはかるために、「今のままの状態を維持すること」を最優先にするからです。
人には「コンフォートゾーン」というのがあり
直訳すると「快適な領域」です。
ここにいれば安心だと思える場所、つまり“慣れた環境”なので
自分のコンフォートゾーンである“慣れた環境”を出ようとすると、ホメオスタシスが「本当にここから出て良いの?」と止めに入ってくるという仕組みになっています。
人は基本的に「変わりたくない」と思う生き物て
どんな人にも、このホメオスタシスは働いています。
体のホメオスタスシスは
自然の流れに沿って働いているので、あまり逆らず
疲れているなら休む、眠いなら寝る、
食べたいなら食べる
など正直になった方がよいです。
心理的なものに関しては
まず、「本当に変わりたい、変えたいのかどうか」
本当に変わりたいのであれば
よく「環境や付き合う人を変えよ」と言われます。
あくまで私の考え方ですが
周りの環境や人(の性格など)は自分の意思では
変えられないので
嫌なら自分が変わるか、環境を離れるか、
人から離れるしかありません。
環境や周りの人は関係なく
自分自身を変えたいときは
言葉を変えること
かなと思います。
「変わりたいのに変われない」
「体が心についていかない」
「頑張りたいのにやる気がでない」
そう思った時、それは怠けているからでも
才能がないからでもなく、
ホメオスタシスが現状維持しようと頑張っているせいなのです。
そして、気温差が激しいときは
まずは「体を整える」ことも大切なことです。
ご予約はこちらから💁♀️🔽
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
