♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ
呼吸は吸うより、吐くこと【ため息】の効果

お盆休みの方も多いかと思いますが、休みになった途端にドッと疲れが出てくるなんてこともあるかもしれません。
心が張り詰めていると自律神経が戦闘モードに入り、交感神経が優位なままになってしまいます。
リラックスするためには、副交感神経を優位にしてバランスをとることが大切です。
自律神経は特に呼吸と深くかかわっていて、心身が嫌な感じになると、人は呼吸が浅くなり、時には無意識に息を止めてしまっています。
そこで「苦しいな」と思うと、「息を吸わなきゃ!」と“吸う”ことばかりしがちです。
でも、心身を緩めるには、息を吸うより”吐く”ことが重要で
息を吐くときに副交感神経が優位になり、筋肉も弛緩してリラックスモードに変わります。
イラついたり心がギクシャクしているときはため息をついてみてください。
そもそもため息というものは、心身の緊張や疲れを取るために体に備わった知恵だと言います。
一般的にネガティブなイメージがあるため息ですが、呼吸を整えることで、無意識に心を落ち着かせようとする防衛反応であり、決して精神や身体に悪いものではありません。
乱れている呼吸を整えるだけでなく、気持ちをリセットする効果があります。難しい勉強や作業をしたり、緊張状態が続いているときに、途中で意識的にため息をつくことで区切りがつき、その後のモチベーションを維持しやすくなります。何らかのストレスを感じているときに、あえてため息をつくとストレス発散につながります。
また、ため息が多いときは「身体が休みたいんだな」と考えて、ゆっくり息を吸って長く吐き出す深呼吸のようなため息を心がけてみましょう。
呼吸が浅いと感じる方も、まずは体を緩めることをオススメします。
ご相談ください◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️⬇️
台風と体調

ちょうどお盆期間ですが台風が発生していますね。
最近、体調が悪い、鼻づまりや鼻水、頭痛やむくみ…
酷くなっている方が多いようです。
台風が近づくときは、特に気圧の変動が激しく、普段の生活では不調を感じない人でも
台風の時には特に大きく体調の異変を感じやすくなる可能性があります。
人の体は”体外の圧力”を常に受けながら生活しています。
低気圧により外の気圧が低くなると、体にかかる圧力が少なくなり、体のあらゆる部分がむくんでしまうのです。
むくみは、足や顔以外にも、血管や粘膜など体の機能をつかさどる部分にも影響を与えます。
本来は、耳の鼓膜の内側にある”内耳(ないじ)”で
気圧の変化に対して体の組織を調整するしくみがあるのですが、内耳が敏感な人は気圧のちょっとした変化でも、うまく調整しきれなくなり体調に変化を及ぼします。
また、気圧が低くなり、鼻などの粘膜が腫れると鼻がつまり、血管から水分が外へ出やすくなることで鼻水が出たり
血管が膨張することで、頭痛もおこりやすくなります。
これらの症状は漢方医学では、水滞あるいは水毒と呼び、体の中の水分バランスの乱れから起きると考えます。
身体の中で、水の偏りが生じていたり、本来不要の水(すいと )が存在したりしているため
治療法としては、余分な水分を排泄する方法が良いとされます。
●湯船での入浴
●適度なストレッチ
●水分補給
●食事はバランスよく
●自分に合った睡眠時間
マッサージなどは体の疲れを解消するだけではなく、
自立神経も同時にゆっくり整えて心身共にリラックスさせてくれます。
ダルいな…という気持ちをちょっとだけ奮起して
スッキリしませんか◟̆◞̆
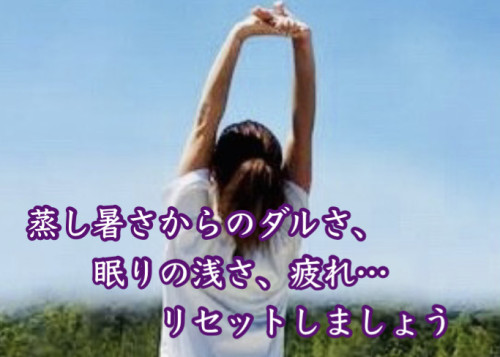
ご予約はこちらから💁♀️⬇️
楽しむ努力

毎日の繰り返しの同じルーティーンの中で
「楽しみ」はありますか?
旅行とか大きなことをしなくても
小さな楽しみを見つけることはとても大切だなって思います。
何かを楽しむためには“好奇心”や心の元気さも大事ですし、色々試して、その経験の中から知識や情報を得て、自分なりに楽しむ工夫をしていくことも重要なのかもしれません。
楽しむ努力
は何かを本当に楽しめるようになるためには、その事をよく知り、研究したり、上達する、時間や手間をかけることです。
うまくできるようになればなるほど、面白くなるということもあります。
私自身もセラピスト1.2年目よりも今の方が断然、
体の仕組みやコリを知れば知るほど、
施術が面白いと感じます。
もちろん、努力をしなくても楽しめることも
たくさんあります。
何かしんどいことがあったり、心が疲れることが
あっても、自分なりの「楽しみ」があるだけで
何とかやりきれるということもあったりします。
でも努力=苦労ではなく
どう楽しむかを考える努力は必要なことなのかもしれません。
そして、楽しむためには
体調と気持ち整えて、笑える準備をすることも
大切です◟̆◞̆
〇〇を緩めると自律神経も整う

この暑さもあって、「眠りが浅い」というお悩みが
増えています。
施術していて
眠りが浅い方に共通して硬い部位は
鎖骨
です。
実は鎖骨と自律神経には不思議な繋がりがあります。
鎖骨付近には星状神経節(交感神経が密集して形成されたもの)というものがあり
星状神経節は鎖骨が圧迫されることで神経が緊張して自律神経が乱れやすくなるのです。
鎖骨には5つの筋肉
①胸鎖乳突筋
②僧帽筋(上部)
③大胸筋
④三角筋(前部)
⑤鎖骨下筋
が付着しています。
なので鎖骨が硬くなって圧迫されると肩の関節の動きが悪くなります。
また、鎖骨まわりは多くの血管や神経、リンパが密集している部分なので
鎖骨の圧迫を放置しておくと、血流の悪化によって老廃物が溜まりやすくなり、これが肩こりや首こりの大きな原因につながるのです。
鎖骨まわりをほぐすことで、滞った血流やリンパの流れを促進し、肩こりの改善効果が期待でき
さらには脳の扁桃体の緊張が緩むと言われています。
扁桃体は、人間の本能的な部分を司る大脳辺縁系の一部で
その部分の緊張が緩むことで、体の緊張をほぐすだけでなく、ストレスや疲れを解消する手助けをすることができます。
忙しい人は特に、無意識のうちに体や心の緊張状態を強いていることが多いので、それを効率良くほぐす効果が期待できるのが、鎖骨のマッサージです。
残念なことに鎖骨はアロママッサージ以外では割とスルーされがちな部位ですが
奏では鎖骨もしっかり指圧しています★
鎖骨が緩むだけで、呼吸が深くなるのを実感できると思います。
鎖骨を緩めて
眠りの浅さ、呼吸の浅さ、巻き肩…
リセットしましょう!
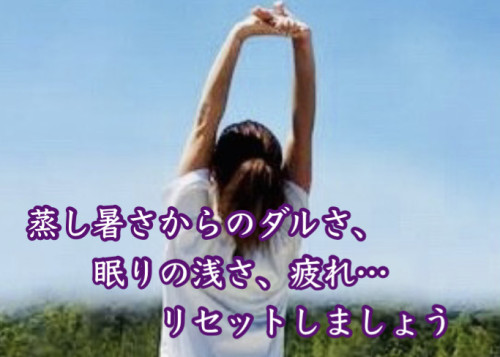
ご予約はこちらから💁♀️⬇️
「つらい」と感じる時は重心を下に
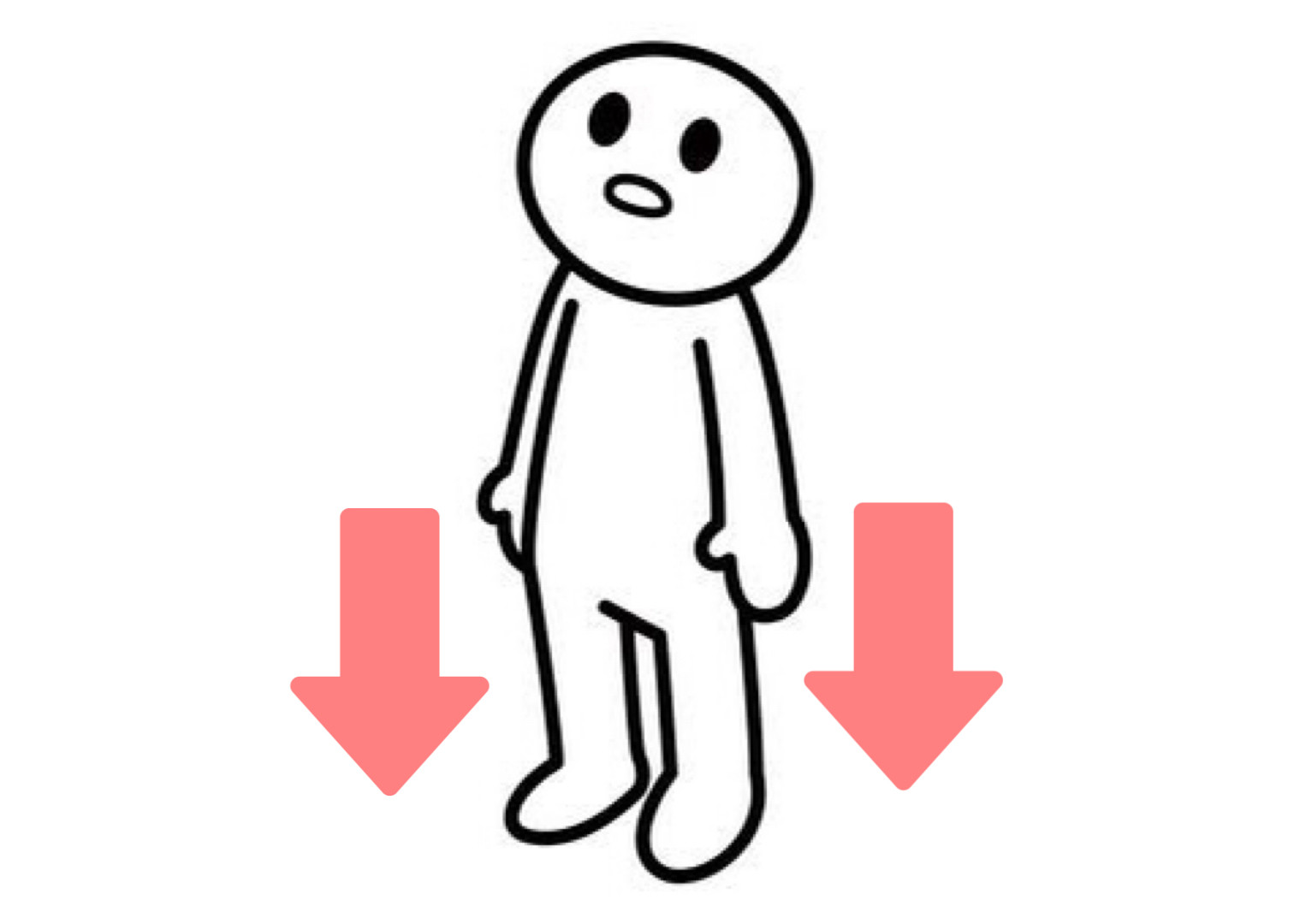
日々のストレスが溜まっていたり、
長い間、頑張りすぎていませんか…?
我慢を強いられることが多い現代社会で、ストレスが当たり前になり、自分がストレスを溜め込んでいることにも気付かない人が増えているそうです。
ストレスを感じている間、体は緊張状態が保たれて、無意識のうちに力が入りっぱなしになり、特に体を動かしたわけでもないのに疲れたり、体のあちこちがこってしまったりするものです。
不安感や張り詰めた気持ちが続くと、いつしか体までこわばり、余計に緊張して、色々考えすぎてしまったり…
心が緊張していると体も「戦闘態勢」になり重心は上に向いてきます。
肩が上がったり、首に力が入ったりするのはそのためです。
言い換えると
「気が上がる」
地に足がついていない
考えすぎてぐるぐるしている
常に緊張状態
常に焦っている...
緊張することを「あがる」というのもここからです。
体感としては
☑︎頭がぼーっとする
☑︎体は冷えているのに顔が暑い
☑︎喋っていても自分が何を言いたいのか分からなくなる
☑︎声が小さくなる
☑︎疲れていることに気付かない
☑︎よくつまづく
☑︎呼吸が浅い
現代人は、気の使いすぎやパソコン、スマホからの情報など頭に色々なことを詰め過ぎて気があがっていると言われます。
こわばった体をリラックスさせるには、
【重心を下】にする意識するくせをつけましょう。
重心を下にするとは?
足の裏でしっかりと地面を感じて、足全体で自分の体をきちんと支えていると意識するだけです。
立っている時には足の裏で地面を感じるように、足全体で体重を支えているような感じで太ももやふくらはぎを意識します。
- 足の裏は右と左のどちらに体重がかかっているのか?
- つま先とかかとのどちらに体重がかかっているのか?
- 土踏まずの部分は、左右どちらが浮いているのか?
- ふくらはぎは左右どちらが緊張しているか?
- 太ももは左右どちらが緊張しているか?
を感じ、足首やひざをほんの軽く曲げることで地面や体重を感じやすくなります。
そして
物理的に「足裏」を地につける状態にすることが大切です。
その為には足の筋肉をしなやかにし、血や水の巡りを良くすること、そして足のアーチをつくることが必要です。
のぼせやすかったり、フワフワする感じかあったり、身体が重い方はまず足の血流を整え、上半身ばかり流れている気、血、水を下にしっかり流してあげると落ちつきます。
気を下げることで、良く眠れたり
体が緩まり
緊張感は解放され全身の呼吸が整います。
呼吸が整い、息が深くなると心も活力が出てくるかもしれません。
足の疲れ、のぼせ感、眠りの浅さは
足のマッサージがオススメ★
頭を良く使う方、たまに「気を下げる」こと意識してみてくださいね◡̈

ご予約はこちらから💁♀️⬇️
