♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ
中秋の名月🌙月とからだ

今日は十五夜(中秋の名月)、
満月でもあります。
中秋の名月とは、旧暦の8月15日の夜に見られる月のことで一年でもっとも美しい月とされ、お月見をする風習がありますね。
今頃は気温が下がりはじめ、空気中の水蒸気が減るので、月がくっきりときれいに見え、
月の高さは太陽の逆のため、夏は低く、冬は高くなります。
秋は低すぎず高すぎず、月を地上から見上げるのにちょうどよい高さなので、とても美しい姿を見ることができるのだとか。
昔の暦は月の満ち欠けを基準にしていたので月は人々の生活に密接な存在でした。
月の満ち欠けは人の体にも影響があるのは確かなことです。
一般的に、月が膨らんでいく時は心身がエネルギーに満ち、活動的になると言われ
満月を迎えると、エネルギーはピークに達して気分が高まり、月が欠けていく時にはエネルギーが減退し、肉体的に疲れやすい傾向にあります。
満月の不調で特に多いのが頭痛だそうです。
これは、満月の時は地球が太陽と月の引力を両面から受けることで、血管が拡張しやすくなるからと考えられています。
満月から新月にかけては、体から余分なものや老廃物が排出されるため、この時期にダイエットをすると効果を得られやすいとか。
昨日、今日はやたら眠いとか、浮腫みやすい、イライラしやすい…
など、もしかしたら月の影響を受けているからかもしれません。
体調の変化を感じたら、その時の気温や天気に加え、月の満ち欠けなんかも気にしてみると面白いですよ。
今日はぜひ月を眺めましょう🌙
脱力のすすめ

日々、肩や体に力が入っていませんか?
緊張したり、慌ただしい時間が増えると
気がつくと体に力が入り
なかなか抜けなくなっていることがあります。
上手く力が抜けないと筋肉が凝り固まって
血流が悪くなり、
肩こりや頭痛にもつながっていきます。
特に仕事のパソコン作業中などは
姿勢が悪くなり、意識と力が上半身、頭部に集まっています。
すると”気”が上に上がっている状態になって、ストレスの多い状態とも言えます。
脱力するためには
一度力をためてふっと抜くこと
です。
一度思い切り力を入れてみましょう。
思い切り力を入れた後に、一気に力を抜く。
例えば肩まわりなら、思いきり肩をすくめて上げた後に息を吐き出しながらストンと肩を落とします。
なんとなく力が入っている状態より、極端に力を入れてそこから力を抜く方が抜きやすく、
それだけでも大分力は抜けます。
余分な力が抜けて、呼吸がゆっくり深くなり気持ちもリラックスすると、
頭も冴えてきたりします。
最近わたしは
「ライオンあくび体操」🦁なるものを知りました笑
ざっくり言うと
口を意識的に大きく開けると、リラックスできたり、脳幹が整うらしいのです。
サウナに行くと、よく大きなあくびが出るのですが、
頭がスッキリする気がします。
力が抜くのが苦手な方は
まず凝り固まった筋肉の緊張を緩めたり、リラックスする時間を作ってあげてくださいね◟̆◞̆
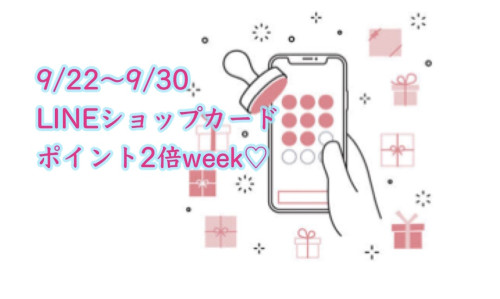
ご予約はこちらから💁♀️⬇️
涼しくなるとやってくる…夏の疲れ

数日前まであんなに暑かったのに急に涼しくなりました^^;
涼しくなった途端、ドッと疲れが出たりしますよね。
やはり、この週末は駆け込みが多かったです。
朝晩涼しくなったりすると、
真夏に冷やし続けたからだが涼しさについていけなくなり、体がだるい、鼻がグズグズする、喉が痛い、寝違え、
腰痛下痢などの症状を引き起こしたりすることがあります。
すると猛暑を頑張って乗り越えてきた夏対応の身体が『あれ? もう暑いの終わり?体温調節どうすれば良いの!?」といった感じで調子を崩してしまうんですね。
知らず知らずのうちに疲れとなって押し寄せてくるような...
こうした不調を引きずったまま秋を迎えると、今度は脾胃と密接に関係している「肺」の働きも弱くなってしまいます。そこに秋の乾燥が影響することで、乾燥に弱い肺の機能はますます衰えてしまうことに…
こうした一連の不調が積み重なることで、慢性的な気の不足や食欲不振などが続き、秋から冬に疲労感や倦怠感、気分の落ち込みなどにつながります。
病気というほどでもないから、とやり過ごしてしまいがちですが、不調を感じたら早めに身体を整えておきましょう!
まずは睡眠、食事
そしてなるべく体を温め、筋肉も心も緩めてあげてくださいね。
大デトックス

昨日は秋分の日でしたが
わたしは先週からものすごい体のデトックス症状出てました^^;
わたし自身
健康だと思っていますが、実は1年以上「後鼻漏」という症状に悩まされていました。
痛いとかではないですが地味〜に結構辛く、
でも意地でも病院には行かず笑
どうしても自分で治したかったんです。
この1年、本当に色んな方法を試しました。
鼻うがい、漢方、サプリ、ツボ…
この半年ほどは3割くらいになっていましたが
この3から進歩しないんです泣
自分では副鼻腔炎なのでは?踏んでいたのですが
先日、あるブログからこの症状が逆流性食道炎から来るというのを見つけ、左の中指を揉むといいとか腕にツボがあるやら、とにかく、自分で押しまくっていたら
すごいことになりました笑
生あくびが止まらず、涙、鼻水、
さらには夜に発熱しました。
でもその後から本当に症状が楽になりました。
鼻の症状なのに、「胃」から来ているなんて!
胃(脾)と肺は深く関係していて
肺が弱れば、鼻に症状が出るのです。
余談ですが
お客様に治らない症状があるとき、症状名+潜在意識
で調べることがあるのですが
わたしの症状が
「心で泣いている」とありました。
確かに去年は色々なことがあり、その後から症状が出始めたので、こちらも一理あるかな?と。。
この仕事をしていても、自分の体のことは
案外わからないものです。
でも、施術者として
自分の体験が、いつか誰かの役に立てば良いなと思っています。
心の傷も同じで
同じ体験や経験をしたからこそ、寄り添えたり
理解できることがあるんだと思います。
だから辛い経験や痛み、苦痛も
きっといつか、あれがあって良かったと思える
学びや感謝に変わるのだと思っています。
というわけで、
体は全部、そして心や脳と体は繋がっています。
改めて
まずは体、内臓を整えること、本当に大切です!
秋分の日

秋分の日。
今年はとにかく暑かったですが
暑さ寒さも彼岸までと言われ9月23日の秋分の日を境に昼は短く、夜は長くなります。
目には見えないですが陽から陰へ変わる時です。
陽は
外側へ向かう、活発に動く
陰は
内側へ向かう、収穫、落ち着く
といったイメージです。
街に溢れる洋服の色も
季節のエネルギーと一致していますよね。
季節と同じように
人も陰陽の影響を受けて生きているので、変化を感じ
陰陽のバランスを整えています。
眠気やだるさ、落ち込みや心のザワザワ、デトックス症状など出やすい時期です。
そして秋は食欲の秋とともに「実り」
色々あったけどよくがんばった、
と「実り」を感じたり
心と体にも栄養をあげ
ほっとする「時」を味わうことも大切かもしれません。
