♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ
春の【フワフワ】感

春になり、暖かくなると「めまい」がしたり
春の風のように
「フワフワする」という方が多くなります。
東洋医学では、これを「気が上がっている状態」と考えます。
気が上がるとは...頭ばかりにエネルギーを取られて思考がとまらなくなったり、落ち着きがなくなったり、足腰がしっかりしない状態を言います。
また春は風が強くなり、東洋医学は自然界と人間は連動していると考えるので、
風は人間の中でも起こり、その風がめまいだとも言われます。
🔹フワフワめまいや気が上がる原因
・肩のコリが強く首筋や後頭部、頭の筋肉も緊張してふわふわしためまいが起こる
・気候や温度の変化で自律神経が乱れる
・心的ストレスにより自律神経が乱れる
そして
考えすぎ=頭の使い過ぎもエネルギーが頭にばかり行ってしまい、
フワフワする原因になります。
フワフワ感を解消するには
上がっている気を
下に下ろしてあげればいいわけですが、
「ふわふわめまい」の解消に効果的なのは「ストレッチ」です。
・両手を肩に添え、左右の肘を前後にぐるぐると回して肩甲骨まわりをほぐします。
・正座をしたまま倒れて太腿の前を伸ばします。
そして足元の血流を良くするため
入浴、足のマッサージも効果的です。
奏では足のマッサージ+ドライヘッドスパ
で春の不調解消、心のリラックス効果も…★
この季節、身体も心もフワフワしがち…
気を下ろす意識をしてみてくださいね。
ご予約はこちらから💁♀️🔽
腸もむくみます!

体の不調の原因のひとつになり得ることが
「腸の環境や状態が悪くなっている」ということ
腸は、体調の鏡です。
腸の環境や状況が悪くなると、そのまま体調に現れ
特に全身のむくみがひどい、便秘、肩こりも…
それは腸がむくんでいる可能性があります。
そもそも腸がむくむのか?という話ですが
食べたものは小腸で栄養分が吸収され、液状となって大腸へと送られ、大腸で水分が吸収されて便になります。
大腸には血管やリンパ管が張り巡らされていますが、腸管の血流が滞ると、腸壁から水分がうまく回収されなくなり、腸管全体がむくんだ状態になるのです。
つまり、腸のむくみは血流の停滞が原因で起こるもので余分な水分が細胞間にたまり、脚や顔と同じように、腸も重くだるい状態になってしまいます。
腸がむくむと、消化吸収が悪くなり、免疫力が落ち、メンタル的にも影響するためよりストレスを感じやすくなったりします。
腸のむくみの原因のひとつは体の冷えです。
体が冷えて血管が収縮すると、血の巡りが悪くなって血中の水分が滞ってしまいます。これは腸にも当てはまります。
そしてストレスも血流を悪くし、腸の水分吸収が悪くなってきます。
腸がむくまないようにするには
ヨーグルトや、みそなどの発酵食品と食物繊維をとること
そして外からの刺激はマッサージや運動などで
血流を良くすることです。
また腸内環境を整えるためには、睡眠時間や食事時間をきちんと決め、毎日なるべく同じリズムで生活することが大切です。
何かと忙しない3月ですが
なるべく生活リズムを整え、健康に過ごしたいものですね。
【脾】を労り、むくみ・疲れにくい体に

季節の変わり目
元気がでない、むくみやすい、食欲がない、肌のたるみなど…何だか調子が良くないという方は
「脾」が弱っているかもしれません。
無理をすることが多い人や、胃腸を酷使しがちな人は「脾」が弱ることで様々な不調を引き起こす可能性があります。
「脾」の働きは
- 消化吸収
- 全身に栄養を運ぶ
- 水分代謝
- 血液が漏れ出ないように統制する
- 内臓を正しい位置に維持する
- 筋肉や四肢を司る
特に大事な役割は栄養の吸収で
吸収した栄養物を「気・血・水」に変え、全身へと運ぶ「運化」という働きをしています。
つまり「脾」が弱ると、まず消化吸収の能力が落ち
消化不良、食欲不振、胃のもたれ、食後のだるさ、軟便や下痢などの症状が起きてきます。
「脾」に負担をかけるのは食事(特に甘いもの)や過労のほか
「思」という感情です。「思」とは考えたり、悩んだりする感情で、思い悩んでいる時には、喉が詰まった感じがしたり、胃腸の働きが悪くなって食欲が落ちやすくなりますね。
そして、ストレス等でイライラしている状態を東洋医学では「肝が高ぶる」と捉えますが
高ぶりすぎた肝は脾の働きを邪魔するそうです。
ある鍼灸師の方がこんな例えをしていました。
肝はジャイアンで、脾はのび太。肝が高ぶる=ジャイアンが強くなると、元々強弱の関係にある脾ののび太が弱る」
だから、その状態を助けるために、ジャイアン=肝を抑え、のび太=脾を助ける処方が必要だとのこと。
脾の負担を少なくするには
- 冷たいもの、甘いものの油もを摂りすぎない
- 水分やお酒を飲みすぎない
- あまり思い悩まない
つい酷使してしまう胃腸をなるべく労りながら
ストレスはこまめに発散して「脾」に負担をかけない生活を心がけてみてくださいね。
自律神経を乱れさせないためには…
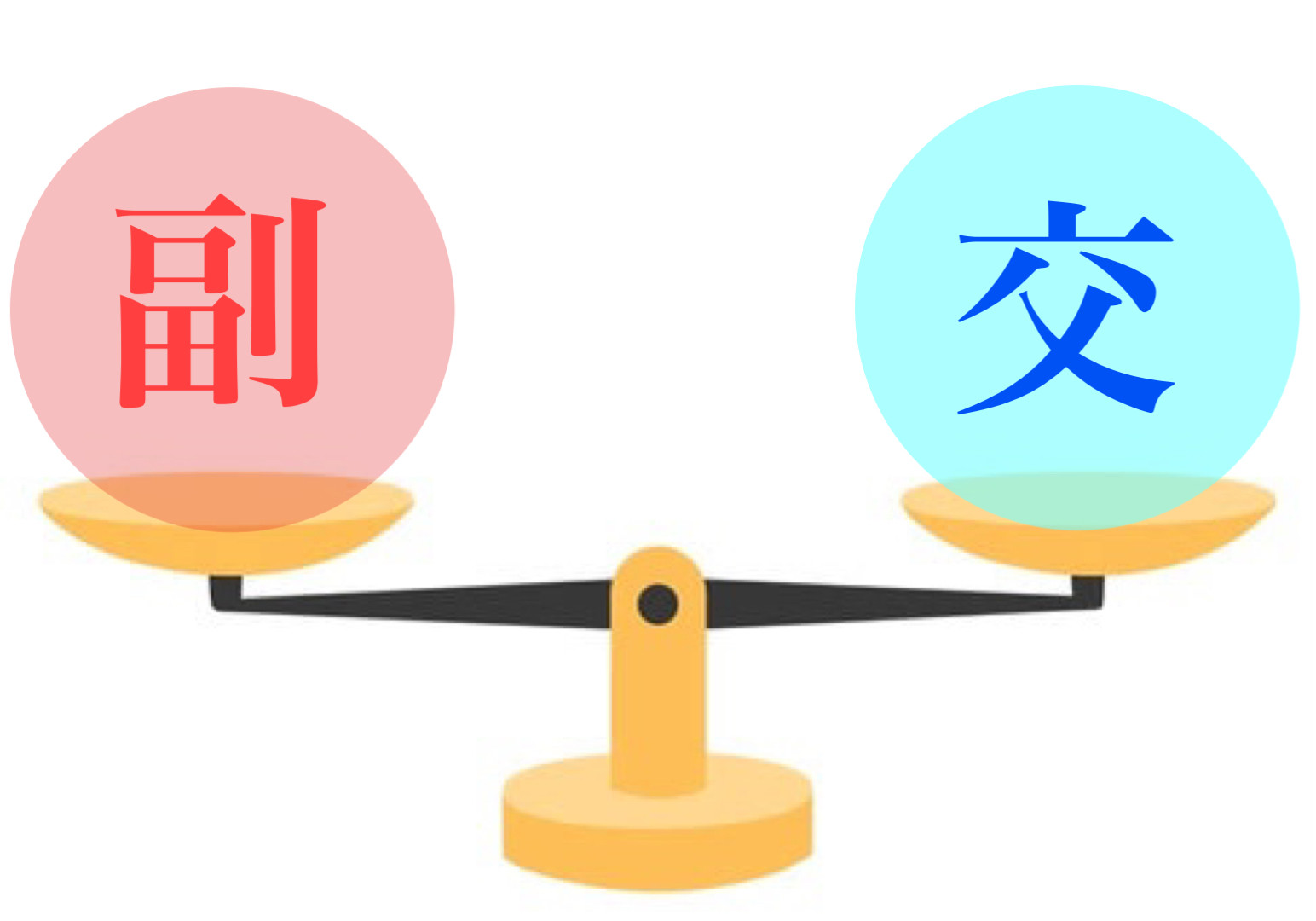
自分の意思とは無関係に24時間働き続け、生命活動を維持してくれるのは「自律神経」です。
血液循環や呼吸、消化、免疫、排泄、体温調節、生殖など、様々な生命維持活動の調整を行ってくれる大切な存在です。
主に交感神経は身体の働きを促し、副交感神経は逆に休ませる役割を持ち、状況に応じてそれぞれが働くことで、自律神経は私たちの身体を常にベストな状態にしようとしています。
例えば暑い時に汗をかいて体温を下げる、食事をした時に食べ物を消化するといったことも、この自律神経の働きの一つです。
この自律神経の働きが乱れると、様々な症状や不調が現れてきます。
自律神経の乱れによる症状
・身体的な症状
身体がだるい、眠れない、発汗、ほてり、動悸(どうき)、息切れ、めまい、頭痛、食欲不振、下痢、便秘など
・精神的な症状
イライラ、不安、やる気がでない、パニックになりやすいなど
自律神経が乱れる原因は
- 睡眠不足
- 不規則な生活
- 偏った食事
- 音や温度、気圧などの外的なもの
- 人間関係や仕事のプレッシャーなどの精神的なストレス
- 過労
- ホルモンバランスの乱れ(更年期など)
- 疾患によるもの
そして、「したい」ことを我慢しているというのも
自律神経の乱れになります。
というのは自分の「したい」は「したい」ことではなく「しなければならない」ではないか?
ということです。
「しなければならない」ことをし続けていると、あたかもそれが自分の「したい」ことと勘違いしてしまうことがあります。
例えば、頭では「したい」と思っているのですが、体はボロボロの状態で疲れ切っていると
これは、「しなければならない」ことを「したい」ことと勘違いしていたりします。
もしかしたら、「休みたい」が本当にしたいことかもしれません。
本当に求めていることは自律神経がしたいことで、それをすることで自律神経は活性化するらしいのです。
でも忙しいとやることが多すぎて、複雑すぎると脳と体がいっぱいいっぱいになって、自律神経がパンクしてしまいます。
パンクしてしまった自律神経には
何をしたらいいのかより、何をやめたらいいのか、が先です。
しんどいこと、嫌いなこと、やりたくないこと
やめられることは一つ一つやめてみる。
生活をシンプルにして、脳と体が落ち着くことだけにして
次は少しずつ、やりたいこと、好きなことを増やしていく…
勇気がいりますが、何かをプラスすることより
「やめること」
大切かもしれません。
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
【桃の節句】の本当の意味

3月3日
「ひな祭り」ですが「桃の節句」とも言われます。
「節句」とは「季節の節目になる日」
お祝いとしての行事だけでなく、昔から日本人が自然の摂理に沿って一年を健康に生きるための知恵が宿っています。
節句はもともと中国の「陰陽五行」思想が日本に伝わったもので、稲作を中心とする日本人のくらしに合わせて取り入れたとされます。
桃の節句は、女の子の成長を祝う日ですが
元来は無病息災を願う厄祓い行事でした。
古代中国には、三月の初めの巳の日(上巳)を悪日として、川辺に出て不浄を除くため水で祓(はらい)をおこなうという風習があったそうです。
陰陽五行の思想では、奇数は縁起の良い「陽」、偶数は縁起の悪い「陰」と考えられ
五節句は、「奇数が重なり大変めでたい日」
その一方で、「陽の気があまりに強すぎて不吉である」と考えられて厄除けや禊がおこなわれていました。
それが、節句行事の始まりとされています。
桃には、邪気を祓う力があると信じられ
中国では子孫繁栄をもたらす霊木であり、その実は不老長寿の仙薬となるという説もあったそうです。
それだけでなく、桃は「百歳(ももとせ)まで生きられるように=長寿をまっとうできるように」という不老長寿の願いがこめられているという説もあり
いずれにせよ、
様々な願いがこめられた大切な日ということですね。
古くから伝わるものには
様々な想いが詰まっているだけではなく
意味があるからこそ、時代が変わっても、受け継がれています。
季節の節目ということで、とにかく寒暖差が激しい
この頃…
何かと忙しい時期でもありますが
体と心のケアも忘れずに★
ご予約はこちらから💁♀️⬇️
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

