♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ
呼吸で痩せ体質、コリ解消?!「横隔膜呼吸」

このブログでも呼吸の大切さはお伝えしていますが、
お客様でご自身でランニングなどをして劇的に身体の状態が良くなった方から、
おススメの呼吸法を教えてもらいました。
呼吸法で
一般的なのは腹式呼吸、胸式呼吸ですが
今回聞いたのは
「横隔膜呼吸」
簡単に言うと横隔膜呼吸は、胸とお腹の両方を同時に使う呼吸で
医学的な見地からも、人間の正常な呼吸法と考えられています。
胸とお腹の境目には横隔膜があるため、両者は自ずと連動して動きます。
生活習慣などの筋肉のこわばりが原因で、横隔膜呼吸ができていない人は約8割。
ちゃんとできると使えていなかった筋肉を覚醒し、あらゆる効果があると言います。
●姿勢が良くなり、スタイルアップ
実は呼吸に使われる筋肉は、姿勢を保つ筋肉と同じなので自然と猫背やお腹のでっぱりも解消できます。
●肩こり、腰痛も解消
骨格が正しいポジションに収まるようになり姿勢が改善されるので、不良姿勢による肩こりや腰痛も減少するメリットが。
●痩せやすくなる♡
お横隔膜呼吸は腹横筋が鍛えられ、代謝が上がってカロリーが消費されます。また、深い呼吸はリンパの流れを促すことにもつながるので、むくみの取れたスッキリしたカラダに♡
なんと
呼吸を変えるだけで...
痩せる!!??
横隔膜呼吸は意外に簡単🎶
横隔膜呼吸のやり方
胸とお腹に同時に空気を入れるように意識しながら息を吸う。この時、肺の膨らみで横隔膜は下がる。
胸とお腹を同時にへこませるように息を吐く。すると、肺の膨らみが小さくなるので横隔膜は上がる。
あれ?実は腹式呼吸と胸式呼吸のミックスです笑
「横隔膜呼吸」難しく考えず上手に行うコツとは
「力を入れない・固めない・リラックス」
横隔膜呼吸はしっかり胸部が動くのですが胸部がうまく動かない人は肋間筋(ろっかんきん)をほぐす マッサージを。
胸がうまく前後に動かないのは、ストレスや緊張が原因で肋間筋が固くなっている証拠です。
鎖骨周りや肋間筋を緩めると呼吸も深くなります。
呼吸するだけで痩せ体質になったり肩こりや腰痛まで良くなるなんで
まさに侮るなかれ「呼吸」
そして深い呼吸はメンタルを整える効果もありますので、呼吸を整えることは
簡単なのに良いことずくめ♡
上手くできない方はサロンでも一緒にやりたいと思いますので声をかけてくださいね☺️

ご予約はこちらから💁♀️⏬
アロマとマッサージで認知症ケア

実は先日、知人から声をかけて頂き、
介護施設でアロマハンドマッサージの講習と脳デトックスの施術をしてきました。
今回の目的は「認知症」ケア。
認知症とは
脳細胞の死滅や活動の低下によって認知機能に障害が起き、日常生活・社会生活が困難になる状態の総称です。
認知症=物忘れのイメージですが記憶の消失だけでなく理解力や判断力にも大きく影響します。
認知症やパーキンソン病などの脳の病気と、匂いの感覚である「嗅覚」の関係が注目されています。
香りによって認知機能を刺激することで病気のリスクの軽減や予防効果があると言われているのです。
嗅覚と脳の関係
人間の五感の多くが、その刺激を脳幹を経由して大脳に伝えるという神経経路を持っています。しかし、匂いを感じる嗅神経は脳幹を介することなく大脳から直接分岐しており、匂いの刺激を直接大脳に届けることができます。
そさて匂いの刺激を受け、情報として感じとる働きのある部位を嗅覚野と呼びます。嗅覚野は大脳辺縁系の中の、嗅内野という部位の近くにあり、その嗅内野が記憶を司る海馬のすぐ近くに位置します。
つまり、嗅覚野が受ける匂いの刺激はすぐそばにある嗅内野に伝わり、そしてそこから海馬へと伝達するのです。
認知症の場合、まず嗅覚から衰え始めると言われています。
感覚は刺激を受ければ受けるほど活性化し、反対に使わなくなったら衰えます。
それは脳の認知機能も同じで嗅覚が衰えることで、脳の認知機能に伝わる刺激も小さくなり、認知症の発症へとつながりやすくなってしまうのです。
逆に常に認知機能へ刺激を与えることで、認知機能が衰える速度は遅くなり、
匂いを嗅ぐことで常に嗅覚野が刺激され、認知機能の維持が期待できるのです。
ラベンダーとオレンジが◎
ラベンダー+オレンジの香りには鎮静効果が
あり、心やカラダの安らぎ効果が高いとせれます。
特にラベンダーにはたくさんの効果が
https://izumi-kanade.com/info/2601147
何かを嗅いだら昔の記憶が蘇ったり
香水を嗅いだら特定の人を思い出したり…
という経験があるかもしれません。
そしてマッサージをすることも認知症ケアには大きな意味があります。
ポイントは「オキシトシン」
人に触れられた時などに、脳から出る幸せホルモンで、その癒やし効果のパワーは大きく、認知症の徘徊が減ったり、血圧が下がる、脳を活性化するだけでなく
関節の痛みや日ごろのストレスを大きく緩和することが分かっています。
つまり、認知症だけでなく
ストレスケアやリラックスの為にも
香りとマッサージは効果的なのです。
私がこの仕事を始めてから、私自身が前より元気に健康になったのは「マッサージを施術しているから」というのも一つの理由だと思っています。
最近、物忘れが多い
ストレスが溜まっている
眠りが浅い…
そんな方は香りを利用してみるのも良いかもしれません。
奏のアロマトリートメントも何気に隠れ人気です★男性もokですので心と身体をリラックスさせたい方は試してみてくださいね◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️⏬
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
本日雨の日クーポン☂️使って下さいね◟̆◞̆
https://izumi-kanade.com/coupon
決めること

昨日は多くの人がラグビーに釘付けになり、
結果はどうであれ、スポーツから日本中が夢と感動をもらったのではないでしょうか。
私はルールがわからないながらも、こういう風に国が一丸となって盛り上がるって素敵だなと思いました。
主将リーチマイケル選手の座右の銘は
「神に誓うな、己に誓え」という言葉だそうです。
実はBUMP OF CHICKENのボーカルの言葉のようですが
リーチ選手はあるインタビューで
「神様にお願いするのではなくて、自分の力を信じて、自分で決めて努力するだけ。人生は自分の力で切り開いていくものだから...」と言っています。
自分がどうありたいか、何をしたいか...
決めることって大切です。
私が読ませて頂くブロガーさんがよく
「覚悟の法則」と言っています。
心の中で決めてしまうと…
びっくりするようなカタチで
現実が動いてしまうことがある。
そうなったらいいなあ!
ふんわり思っている時期は
それはそれで楽しいものですが
「どんなことがあっても
ブレずにそれを求め続けていこう!」
と心から覚悟を決めてしまうと…
行動するためのエンジンが
かかり、
ちっちゃな変化が起き始める
(ブログから引用させてもらってます)
私自身好きなことを仕事にしていて幸せだと思う反面、
時に自分の行き先がわからなくなったり、何が正しいのか、自分って何か?
ってブレてしまう時もあります。
だけど昨日改めて
「いちばん大切にしたいもの」は何かってことに気づかせてもらう出来事がありました。
変化する時はちょっとした勇気が必要です。
それから、最初から上手くいかなかったり、途中でぶつかる壁もあります。
仕事もプライベートも趣味もスポーツもおんなじで、
だけど未来は自分の気持ち次第でいくらでも変えられるし、作っていけるんだと思います。
でも大切なのは繰り返される「今」。
目の前の人、目の前のもの、出来事を大切にしていこうと思えました。
どんな明日に来月に、1年後にしたいでしょうか…
いつも本当にありがとうございます。

ご予約はこちらから💁♀️⏬
表参道マッサージ整体・奏・24時間オンライン予約
自分で作る特効薬「セロトニン」

最近よく耳にする“幸せホルモン”と言われる「セロトニン」
心のバランスを整えてくれる脳内物質で心と身体を安定させ、幸せを感じやすくする働きがあります。
ちゃんとセロトニンが分泌されていると、
ポジティブな気持ちになったり、活動的になるうえに、アンチエイジングや直感力を高める効果もあります。
脳内物質・セロトニンとは?
セロトニンは脳内で働く"神経伝達物質"のひとつで、
・感情のコントロール
・神経の安定
と関係しています。、
その働きは主に5つ。
1【大脳の覚醒の状態を調整する】
朝起きて頭がすっきりしていく状況はセロトニンによって起こるもので、目覚めが悪くいつまでも頭がボーッとしている人は、セロトニンが不足している可能性があります。
2【意欲を促す】
大脳の内側に大脳辺縁系という、意欲や心のバランスに関わる領域があって、そこにセロトニンが分泌されるとポジティブな気持ちがわき起こり、分泌されない場合はネガティブな感情になります。
3【自律神経へ働きかける】
自律神経は、夜寝ているときは副交感神経が優位で、朝目覚めてセロトニンが分泌されると、交感神経が優位に切り替わって、血圧や代謝が上がるなど身体が活動に適した状態になります。
セロトニンが分泌されなければ、身体がいつまでもだるい状態になります。
4【姿勢筋へ働きかける】
朝起きると目がパッチリして背筋が伸びるのもセロトニンのおかげなのです。
不足すると、背中が丸まったり、どんよりした表情になってしまいます。
5【痛みのコントロール】
セロトニンには痛みの感覚を抑制する働きがあるので、欠乏すると些細なことで痛みを感じやすくなります。
セロトニンは心と身体を元気にしてくれるいわば“特効薬”。
不足すると脳機能の低下からさまざまな不調が現れて、身体や心のバランスを崩しやすくなります。
セロトニンが不足する理由
セロトニンが不足する理由は
日光・運動・スキンシップの欠乏などがあります。
現代社会では、これらが極端に足りないとも言われているのです。
そして一番の原因は、パソコンとスマホ。
通勤中もスマホ、会社ではパソコンと
液晶画面を眺めていると知らない間に息を詰めて呼吸も浅くなります。
セロトニンが活性する生活習慣
太陽の光を浴びる
日光が網膜を刺激して、直接セロトニンを活性化させます。朝は少しでも日光に浴びましょう。
リズム運動
ダンスなではなく、「歩行」「呼吸」「咀嚼」などの日常生活レベルの運動です。
ヨガや太極拳。歌を歌ったり、楽器を吹くのも呼吸のリズム運動になります。
人や動物との触れ合い
メールやSNSではなく、実際に会って会話したり、団らんすることに意味があります。
肌で触れることは人間の本能として
幸福や充足感を得られるそうです。
人間の身体は本来太陽が出ると自然に起きて、食料を探すために自然の中を歩いて、身体を動かして、人と触れ合って生きてきたため、その中でストレスになるような出来事があっても、自分の身体から出る物質で薬に頼ることなく克服してきました。
生活が便利になればなるほど、その本来の力を失ってしまっています。
セロトニンという自分でつくるお薬をしっかり出せるようになれば、
心も身体ももっともっと元気になれるかもしれません☺️

ご予約はこちらから💁♀️⏬
表参道マッサージ整体・奏・24時間オンライン予約
脳に悪い習慣・良い習慣
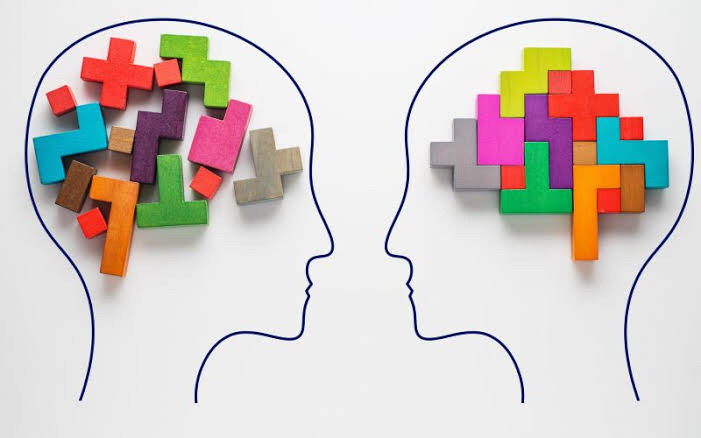
体に良い習慣と悪い習慣があるのと同じように「脳」にも良い習慣と悪い習慣があります。
いつもしている普段の何気ない行動が実は脳に悪影響を与えている場合があるのです。
それが脳の働きを劣化させる原因になります。
逆に脳に良いことをすれば記憶力が高まったり、やる気がアップしたり、幸せ度が高まったりします。
●「好き・嫌い」が大きく脳の働きに影響する
脳は何か情報を受け取ると、まず最初に「自己保存」の本能で
2つの方法で、自分の脳を守る反応を起こします。
1、「A10神経群」と呼ばれる中枢で「好き・おもしろい」と感じて脳の働きを高める
2、「嫌い・つまらない」と感じて脳の働きを止める
そしてA10神経群を経た情報は、「前頭前野」に持ち込まれて判断・理解されます。
その時に前頭葉の「脳細胞の活動」と「入ってきた情報の活動」がどれくらいマッチングするかという「同期発火」によって、その正当性を判断し、理解するようになっています。
・苦手、嫌いなことが覚えられないわけ
「嫌い・つまらない」と感じる情報は、マイナスのレッテルが貼られているので同期発火が起きにくく、理解し難く、覚えられません。
・好きなことはどんどん覚えるわけ
「なるほど!」と同期発火した情報は、「統一・一貫性」の本能によって、「これは筋が通っている!自分もやってみたい」という気持ちを起こす「自己報酬神経群」に伝えられます。
それが「視床」や「海馬回・リンビック」を経て、自分の考えを生み出し、記憶につなげられていきます。
そして繰り返し考えることで新しい発想が生まれます。
脳に悪い習慣
1.ものごとに興味がない「無関心脳」
2.グチが多い、笑顔が少ない「グチ脳」
3.コツコツ、マニュアル重視「ど真面目脳」
4.我慢ばかりしている「我慢脳」
どれかひとつは皆さん当てはまるかもしれませんが、実は脳に良くない習慣なのです。
脳に悪い習慣を改善して脳力アップ!
1無関心脳タイプ
→「知りたい」本能を磨く
脳は「知りたい」と興味を持つことで発達します。
「知りたい」という本能を磨くには、「興味がない」「つまらない」という否定語はNGです。
自分の守備範囲でないことに対しても「おもしろそう」と興味・関心の幅を広げ、前向きに臨むことで、習熟度や発想力がアップします。
まずは色々なことに興味を持ちましょう。
2グチ脳タイプ
→「笑顔」と「感動」を大切に♡
「疲れた」「もうムリ」といったグチは、A10神経群がマイナスのレッテルを貼って脳の働きを落とすので、意識的に使うのをやめましょう。
また、感動することは、判断力や理解力アップにつながるので、なるべく感動する映画などをみたり感性を磨くと○。
またA10神経群は顔の表情筋とつながっているので、口角を上げて笑顔をつくるだけでも、脳の機能がアップします!
3コツコツ脳タイプ
→「目標130%」を目指す
目標への達成率を上げるためには、言われたことをコツコツやるのではなく、ゴールを目指して一気に仕上げる姿勢が必要です。
その際、「もうゴールだ」と安心すると脳の血流が落ちますが、「ここからが勝負」と気を引き締めると脳の血流が上がります。
目標は高すぎると脳が「ムリ」と判断してしまいますが、人の能力は130%まで引き上げられるという実験データがあるので、「100%~130%を目指す」という明確な目標を掲げて進むと、集中力が増して脳の達成率がアップします。
4我慢脳タイプ
→「前向き」に取り組む
ものごとを修得するには、我慢するというスタンスではなく、「これを覚えると自分の役に立つからしっかりやろう」という前向きな姿勢で取り組むと学んだ情報にA10神経群でプラスのレッテルが貼られ、自己報酬神経群が働いて、情報が強くインプットされます。
何かを覚える時は、名前や数字だけを暗記するより、声に出したり、対象のイメージを他の事物と関連付けるなど複数の情報を重ねると記憶力が高まります。
そしてやはり脳に良くないストレス
ストレスホルモンであるコルチゾールは、脳の記憶を担当する海馬の細胞を攻撃します。結果、脳細胞の一部が萎縮し、記憶力が低下します。
「脳」が変わるのは難しいように思いますが、実はちょっとした習慣や思考を変えるだけで、変わります。
脳が変わると、持っている能力がさらに発揮したり、ヒラメキが良くなったり、
運が良くなったり、モテたり…笑
するそうです♡
まずは
・マイナスな言葉をつかわない→プラスな言葉をなるべく使う
・色んなことに興味を持つ
・目標をもつ
・笑う
・リラックスする時間をふやす
心がけたいものですね☺️
身体がお疲れの方はまずは身体を労ってあげてくださいね。

ご予約はこちらから💁♀️⏬
表参道マッサージ整体・奏・24時間オンライン予約
