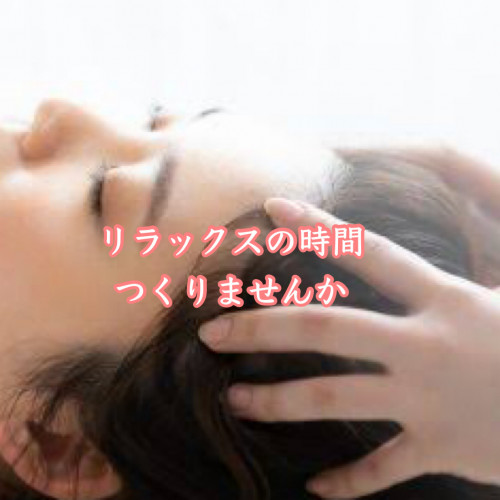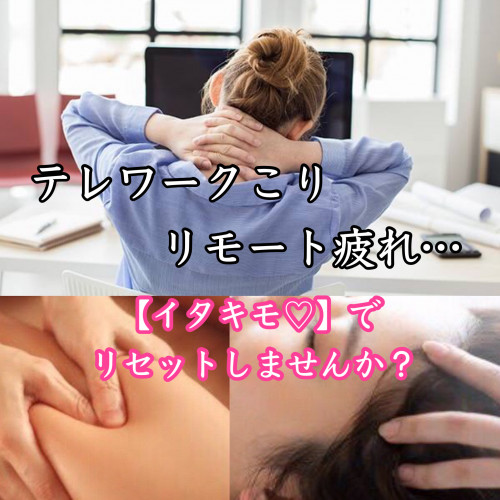♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ
【秋土用】の体と心

急な寒さのせいもありますが、この時期、
体調がすぐれない、気持ちが落ちやすい…
それは今「秋土用」だからということもあるかもしれません。
秋の土用は
10/20から11/6まで
土用といえば夏のウナギのイメージですが
「土用」とは、立春・立夏・立秋・立冬の約18日前の日を指し
立春・立夏・立秋・立冬とは、昔の暦で季節が始まる時期のこと。かつての季節の変わり目の時期が、「土用」になります。
昔から季節の変わり目を快適に過ごすための知恵である様々な風習がおこなわれていました。
そして土用は土のエネルギーが最も強まるときで、
本来の季節のエネルギーを土が奪ってしまうため、
「体内の機能が低下する」と
昔の人たちは考えました。
「土用どんより」なんて言われることもあり
夏(前の季節)に溜まった疲れが表面化しやすい時期です。喉を痛めたり、咳が止まらなくなったり、夏とは違う体調不良を起こしがちに。
秋の土用は、青いものを食べると良いと言われます。
青い食べ物?というと、珍しいもののように思いますが秋に旬を迎える「青魚」のことで
秋刀魚、イワシ、サバなど、この時期は脂がのって栄養たっぷりです。
また、「辰の日(たつのひ)」に「た」のつくものを食べるといいとされています。
辰の日 10月23日、11月4日
「た」のつく食べ物としては、大根、玉ねぎやたこ。これらも滋養のあるものです。
土用の時期には、新しいことや旅行などは避けた方が良い、という言い伝えがあります。
季節の変わり目は体調を崩しやすいので
無理をせずゆっくり過ごすようにしましょうという教訓が込められていたのかもしれません。
逆に言うと土用は次の季節に備えるための
「調整期間」
この時期に心身のデトックスをしたり、
食事や睡眠を整えておくことで、冬の寒さに負けない体に★
コリ、疲れ、むくみ…早めにケアしてあげてくださいね。
ご予約はこちらから🔽💁♀️
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
健康も幸福度もアップする【入浴】

気温が低くなってきて、温活を始める時期です。
実は私…ここ最近、肩こりやむくみなどの不調が
ほぼなくなり、
理由のひとつはお風呂です。
なんとなく「湯船に浸かったほうがいいんだろうな」と思っていましたが
私はそのメリットを驚くくらい体感してしまいました。
なんと入浴でしか得られない健康効果がある
と言われます。
温熱作用、静水圧作用、浮力作用、粘性・抵抗性の4つ。
すべて浴槽の湯に浸かることで得られるといいます。
温熱作用
湯船に浸かることでカラダが温まり、血管が広がって多くの血液が全身を巡り、酸素や栄養が必要な場所に運ばれ、老廃物は回収されます。
浮力作用
浮力の法則で浴槽の中では体重が陸上に比べて約10分の1になり、重力から解放されることにより関節や筋肉への緊張がゆるみ、リラクセーションが促されます。
浸水圧作用
水圧がかかることで全身がマッサージされたような状態になり、水圧と温熱作用によるダブル効果で血液循環が促されるという仕組み。とくに下半身のむくみに有効です。
粘性・抵抗性
浴槽に浸かった状態で手足を動かすと水の抵抗が加わり、重力以外の負荷がかかり、粘性・抵抗性による負荷は陸上の3〜4倍。小さい動きで適度な負荷が得られます。
温熱作用や静水圧作用で血液循環が促され、体内の老廃物や炎症物質が排出され
→浮力作用で筋肉の緊張が取れてリラックスでき
→粘性・抵抗性による重力以外の負荷が筋肉を適度に刺激します。
入浴による1℃の差がカラダを左右する
体は1〜2℃体温が変わるだけで、体調が大きく変化します。
42℃以上の熱い湯に入ると、戦闘モードをつかさどる交感神経が高ぶります。
血圧は上がり、脈拍は早まり、筋肉は緊張します。一方、内臓の働きは弱まり、食欲は一時的に減退します。
熱めのお風呂やシャワーに入るなら、朝がおすすめで交感神経が優位になり、眠気モードから活動モードに切り替わります。朝から体の活動性が高まることで、1日の消費カロリーが高まり、効率の良い自然なダイエット効果も期待できます。
40〜41℃程度のぬるめの湯は、リラックス状態をもたらす副交感神経を優位にします。
血圧は下がり、脈拍はゆっくり、内臓の働きが活性化して消化が促されます。
就寝前やリラックスしたいときはぬるめのお風呂がベストで入浴から30分〜1時間後に体温が下がるタイミングで心地よい眠気が。
ちなみに、人間の体は体温が1℃下がると、基礎代謝や免疫機能が下がり、体内酵素の働きが鈍くなり、肥満、感染症などさまざまな不調や病気を引き起こすと考えられています。
そして…
湯船につかることを習慣にしている人は毎日シャワーで済ませている人に比べて、1.35倍も幸福度が高いと言われています。
一番メリットを得やすい入浴法は
40℃で10分から15分の全身浴。全身を湯舟に浸けることで、血流が3~5倍程度改善すると言われているそう
<入浴前>ノンカロリー、ノンカフェイン、ミネラル入り飲料を200~300ml飲む
<入浴中①>40℃のお湯に5分程度、しっかり肩まで浸かる
<入浴中②>体や髪の毛を洗って、再度5分程度お湯に浸かる
<入浴後>体をふいて10分以内に保湿する。
失った水分・ミネラルを補給するため、ミネラル入りむぎ茶などを200mlほど飲む
お風呂をわかすことすら面倒であれば、足湯だけでもいいので、とにかく寝る前に体の末端を温めてください。
お風呂や温泉は日本の文化です。
昔の人も健康に良いことや、幸福度が増すことも
直感的にわかっていたのかもしれません。
寒くなるこれから
体も心も温めていきましょう♡
ご予約はこちらから💁♀️🔽
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
全てのモノのもと【プラーナ】

世の中には目に見えるものと見えないものがあり
目に見えないものも確実に作用しているのだと
思うことがあります。
ヨガをされている方はご存知かもしれませんが
「プラーナ」
というものがあります。
プラーナは「呼吸」と訳され、アーユルヴェーダでは「生命力」ともいわれます。
私たちの体のなかにも存在し、外側にも空気のように存在します。
ざっくり言うと
人が活動するために必要な「力」のことです。
車でいうとガソリンのように、人間を動かし生かしてくれるエネルギー源であり
『天の氣』『地の氣』『人の氣』
という3つからプラーナを取り入れています。
天の氣…呼吸で取り入れる酸素が体を健やかに動かし、酸素と二酸化炭素の交換によって生かされています。
地の氣…「地の氣」と呼ばれる食事も欠かせない栄養素や大地が発する気のこと
人の氣…自分の意識、触れ合う他人の意識、または経験や情報などによって、私たちは意識的にも無意識にも「人の氣」を取り入れて活動し、毎日の中で良くも悪くも影響を受けています。
これら3つの「気」をバランスよく保つことで快適な暮らしが得られ、
どれか一つでも足りなかったり、良い気でなかったら身体のバランスが崩れると考えます。
プラーナは『意識を向けたところに集まる』という法則があり意識を向けたそのとおりに流れていきます。
人は皆、手からプラーナを放出していて『手当て』という言葉がありますが、不調のあるところに手を当てると痛みが緩和する現象のもこれにあたります。
プラーナを整える方法はシンプル!
呼吸を整えることです。
吐く息に意識を向ける。お腹をへこませて息を出す。
吸う息は勝手に入ってくるため、意識しなくてよい。
30〜50回を1セットとし、終わった後は必ず休む。
また不安や緊張、ストレスを感じるときは、下半身を使ってプラーナを下に落とすことが大切です。
体は本来、上が軽く、下は安定している状態の『上虚下実 じょうきょかじつ』が理想ですが、
今は体を使わず頭を酷使することが増えていて、エネルギーが上がりイライラしたり頭痛や肩こりに悩むことも多いですよね。
そんな時は運動で下半身を使ったり、下半身の巡りを良くしたり
呼吸が浅いと感じる方は
呼吸に関わる筋肉を緩めてあげることも大切です。
呼吸、整えましょう◟̆◞̆
ご予約はこちらから🔽💁♀️
霜降(そうこう)の過ごし方

季節は秋から冬に向かっていて
一年を各四季をさらに細かく六つに分けて、太陽や月の動き、四季の流れに合わせて生活するのが体にも心にも良いとされる【二十四節】
10/23〜は
二十四節気の【霜降〜そうこう】に入ります。
朝夕にぐっと冷え込み、霜が降りはじめる時期を指します。
乾燥した冷気を吸いこむことで、肺に負担がかかりやすく、呼吸器系のトラブルや疲労や元気が出ないなど、“エネルギー不足”に気をつけたい時期です。
また夏から秋、冬に向かう季節であることから、
そのギャップにむなしさを感じたり
くよくよと悩みがちになりったり
同じことを何度も考えたり
寒さも増してくることから血液の循環も悪くなり、カラダの冷えも相まって心身のバランスがくずれがちです。
もし今、体や心が
ちょっとお疲れだったとしたら…
気学や節気で観ていくと
今、ちょうどそういう影響が起こりうる時期でもあるから、かもしれません。
ココロの状態をすぐに変えること難しいかもしれませんが
なるべく体のコンディションを良い状態に保つことが心を安定させることにも繋がります。
人は寒くなると体に力が入り、
どうしても思考も感情も硬くなったりします。
この時期は
とにかく温める、無理をせず頑張りすぎない
"気持ち安らかに過ごす..."を心がけたいものです。
今週から一気に冷え込み
疲れも出る頃ですが、疲労やコリは蓄積する前に
リセットしてくださいね◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️🔽
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
腰痛対策【腹圧】を高める
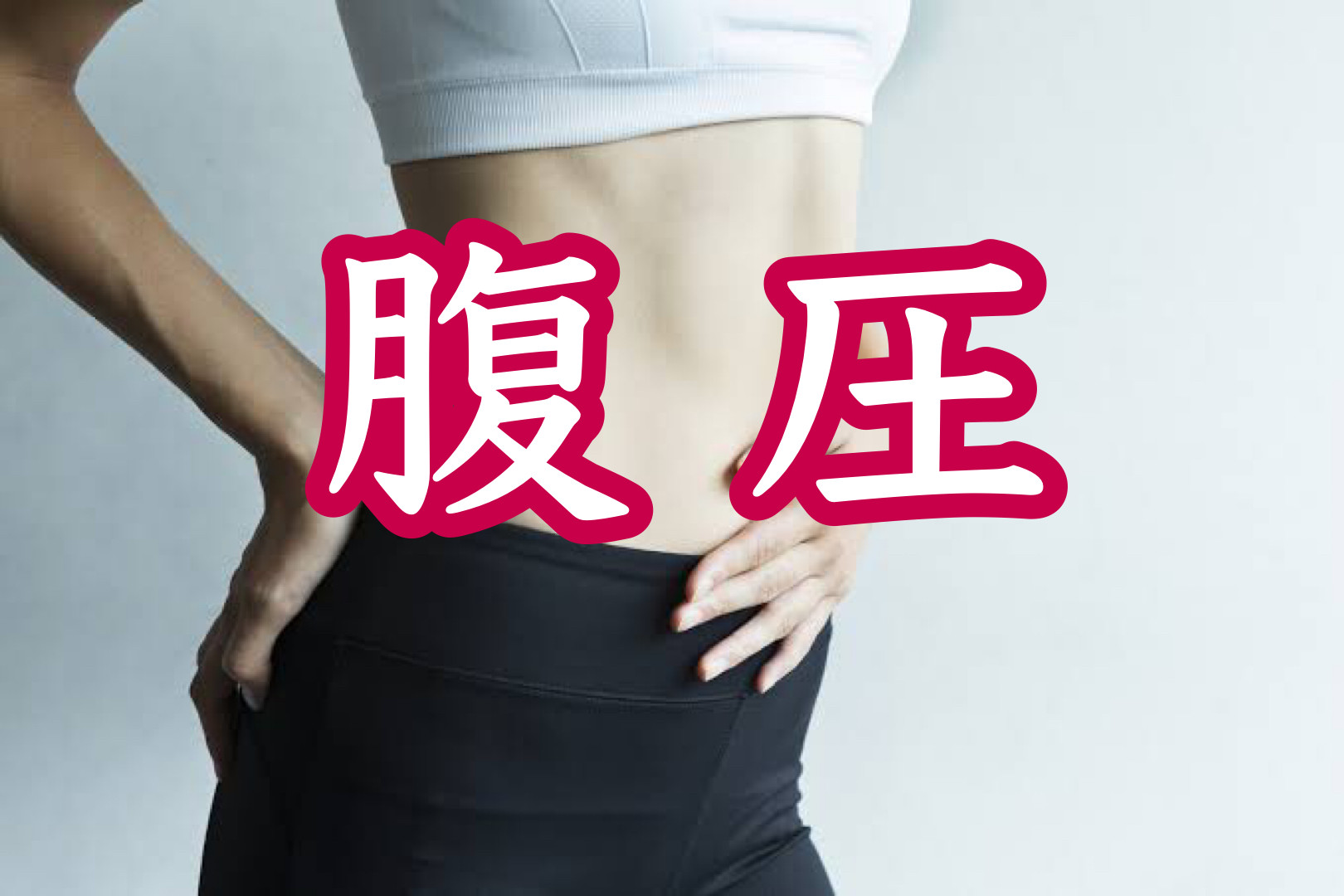
トレーニングやヨガなどで「腹圧を高める」
と言ったりします。
実は「腹圧」は腰痛やダイエットとも深い関係があります。
🔹腹圧とは
お腹の圧力と書いて、腹圧。
人間の腹部には内臓を収納している空間があり、これを腹腔といい
腹腔の上部を横隔膜が、腹筋下部を骨盤底筋が、腹筋の後ろ側は多裂筋(腹、横から前にかけてが腹横筋という具合に腹腔は筋肉に覆われています。
これらの筋肉を使って腹腔にかかる圧力を高めると、「腹圧が高い」状態になります。
腹圧が高い状態は、いわば体幹部が筋肉でできた
コルセットで巻かれているような状態で
安定が感じられます。
ざっくり言うと
「腹圧が高い」は上半身がお腹に乗って安定している状態
「腹圧が低い」は上半身がお腹に乗らずグラグラとして不安定な状態です。
🔹普段こんなことありませんか?
⚫︎なるべく座りたい(立ってられない)
⚫︎足を組みたくなる。
⚫︎寄りかかりたい。
⚫︎気づいたら寝転がっている。
当てはまる方は腹圧が低下しているかもしれません。
🔹腹圧が低下する原因
腹圧は些細なことで低下してしまいます。
座りっぱなしのデスクワーク、イライラや不安などのストレス、運動不足、食生活、睡眠などのバランスを崩すことによって、ストレスが蓄積していくと、腹圧のコントロールに狂いが生じてきてしまいます。
まず
「腹圧を高めたほうがいい」といわれている理由の一つは「姿勢が安定する」ためです。
腹圧の役割の一つは「姿勢を保つ」ことで
腹圧を高めて姿勢を正しくできれば、体に無駄な力が入らなくなり、エネルギーを効率よく使えるようになるんだとか
エネルギーが効率よく使われるといことは
痩せやすい、太りにくいことにもつながります。
また、腹圧が高くなることで
腹部の引き締め効果や腰痛予防、内臓の位置をもとに戻すことも期待できます。
さらに、背筋も伸びるため、腰への負担が軽減されて腰痛を緩和するともいわれているのです。
メリット1.体幹が安定して姿勢が良くなる
メリット2.ぽっこりお腹が解消できる
メリット3.腰痛を防ぐ事ができる
🔹腹圧を高めるには?
ドローイン
ドローインとは呼吸法の一種でこれを行うことで腹部全体の筋肉を収縮させることができ、筋肉の収縮をコントロールしやすくなるそう。
5回を1セットとして、1日に2~3セットを目安に
- 仰向けに寝転がって、膝を60~90度くらいに立てておく
- 両手は太ももの横で、上向きにしてリラックスさせておく
- ゆっくりと息を吐きながら、4秒間かけてお腹を凹ませる
- ゆっくりと息を吸いながら、お腹をもとの位置に戻す
腹圧が高まることで「なんとなく調子か良いかも」と気づくこともあるかもしれません。
朝起きた時や、寝る前などに行ってみましょう。
そしてまず、硬くなった筋肉を緩めることも
大切です。
腰痛、肩こり…ご相談ください◟̆◞̆
ご予約はこちらから💁♀️🔽