♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ
もしかして、春バテ!?
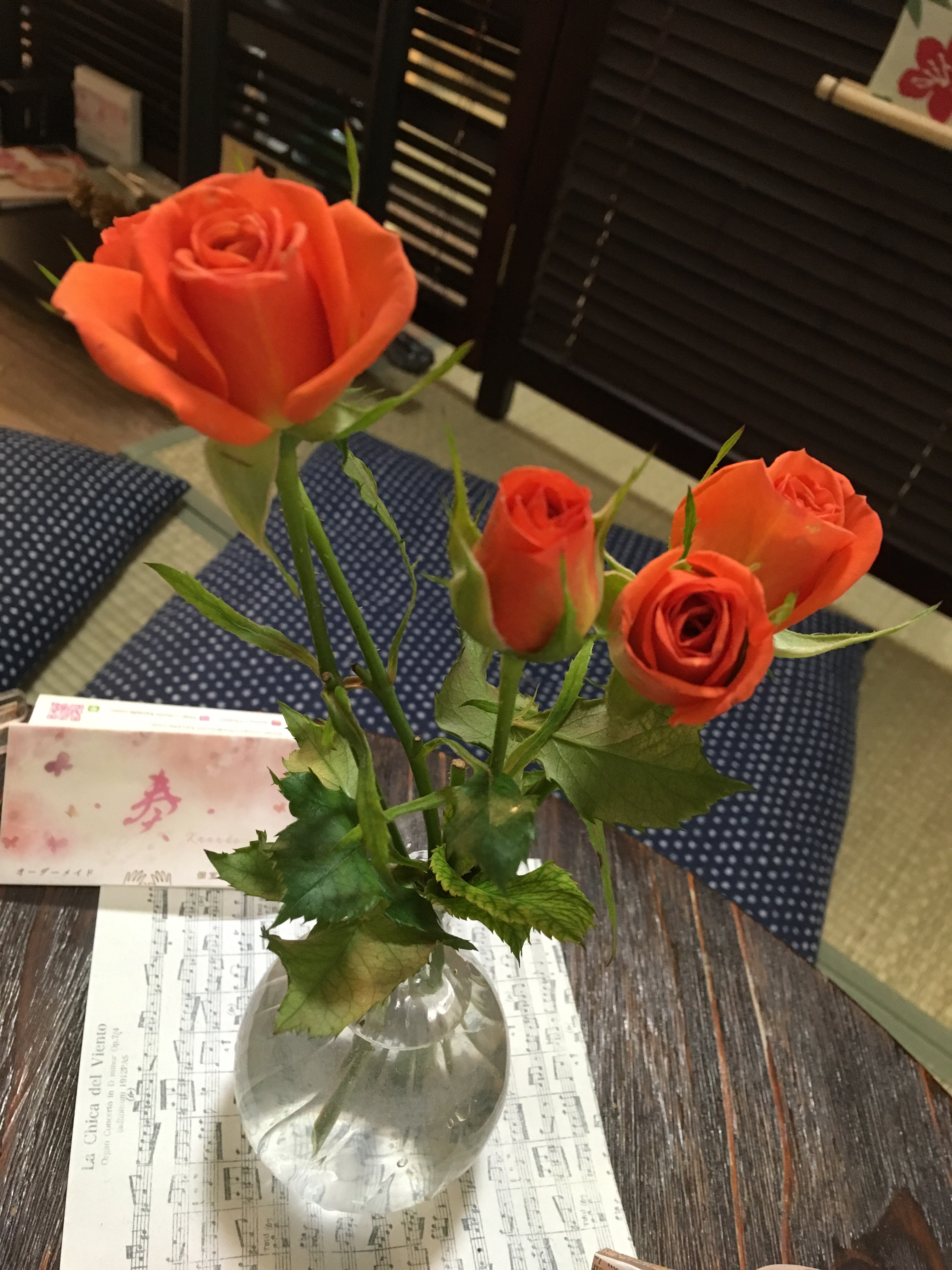
春が近づいてきましたね。
春といえば
「ワクワク」しますか?
それとも、「何となく憂うつ」でしょうか?
春は出会いと、別れの季節。
新生活が始まったり、環境が変わることが多いので、希望や、何となく淋しさや気の重さも感じることもありますよね。
春の始まりは三寒四温と言われ、激しい寒暖差に身体がついていかず疲れてしまう方がとても多いようです。
最近は、「春バテ」という言葉まであるそうです。
特にこんな症状
・いくら寝ても眠たい
・頭痛
・イライラ 憂鬱
・気分の落ち込み やる気が出ない
・目のかすみ、渇き
・肌の乾燥 かゆみ 肌が敏感
・髪のパサつき
春は「肝」が調子を崩しやすい季節。
ここで言う「肝」とは
肝臓など臓器のことではなく
「解毒・代謝」
「気を巡らせる」
「血を作り、蓄え、全身に巡らせる」
働きのことを指します。
春は、動物や植物も人間も生き物も成長し、新陳代謝が活発になり
冬に溜めた毒素をデトックスする季節。
「解毒・代謝」の働きが活発になるゆえに不調をきたしやすくなるのです。
不調をきたすと
・気の巡りが悪くなる
→憂鬱、情緒不安定になるといった症状
・気が下から上に逆流する
→イライラ、怒りっぽい、頭痛、のぼせやめまい
・血を蓄える機能の低下
→目の渇き、皮膚の乾燥、髪のパサつき
これが春のダルさ、プチ鬱などになるのです。
春を快適に過ごすには
1.気をじゅうぶん巡らせる
2.血をじゅうぶん補う
具体的にどうするの?
「気を巡らせる」には身体を動かすのが
1番!
といっても簡単な運動で十分なのです。
ストレッチやヨガ、散歩、
そしてマッサージをされることも同じような効果があります。
頑張りすぎず、気持ちが良いなと感じる程度が続けるコツです。
香りを楽しむことも効果的
アロマやお香など好きな香りやリラックスできる香りを嗅ぐことで脳が活性化したり、気持ちが落ち着きます。
「血を補う」にはやっぱり睡眠
血は夜作られると言われています。
布団の中での携帯チェックも睡眠の質を下げます。
夕方以降はカフェインを控えましょう。
食事からのアプローチ
【気を巡らせる食材】
◎香りの強い食材
菊花、ニラ、たまねぎ、ニンニク、春菊、セロリ、しそ、八角、バジル、三つ葉、クレソン、ローズマリー、パクチー、フェンネル
◎柑橘系
みかん、グレープフルーツ、レモン
◎クコの実
「血を補う」には
◎赤い食材
クコの実、なつめ、小豆、赤身の牛肉、カモ肉、マグロ、レバー
◎黒い食材
黒米、黒豆、黒ゴマ、黒キクラゲ、ぶどう、プルーン
◎野菜類
ほうれん草、金針菜
◎ナッツ類 胡桃、クコの実、松の実
◎魚介類 アサリ、イカ、カキ、タコ、ホタテ
「整体観念」という考え方があります。
私たちの臓器はそれぞれ単体で働いているわけではなく、お互いに影響しあい、組織や器官が互いに作用しあって生命活動を維持しているということです。
また身体は自然界との関わりとも深く、
気候の変化などに自分たちの環境や食生活をあわせ、自然と共存していくことが大切であり、自然と自分とのバランスが崩れたときに病気になると考えることができるのです。
つまり「人は森羅万象と一体だ」という考え方です。
日本は四季があり、その季節に衣服や食べ物を合わせるように、
身体も季節に合わせることも必要になります。
もうすぐ花が綺麗に咲き、ポカポカ陽気のウキウキな春です。
身体と心を整えて、心地良い春を過ごしたいものですね。

〜表参道マッサージ整体サロン ・奏・〜
表参道駅徒歩2分 渋谷、原宿駅徒歩8分
和室の空間
肩こり、腰痛、頭痛、ストレス をリセット
指圧ベースの整体マッサージ
ドライヘッドスパ マタニティ整体マッサージ
アクセスバーズで脳をデトックス
不通則痛とは

頭痛、神経痛、生理痛..
辛いですよね。。
辛いのを我慢するくらいなら良くないとわかっていても鎮痛剤を飲んで痛みを抑えてしまう人も多いと思います。
「痛み」や「炎症」は
原因物質=プロスタグランジンが関与していると言われ、
鎮痛剤は、このプロスタグランジンの生成を阻害することで、「痛み」や「炎症」を止めています。
原因物質が作られなければ、症状がおさまりますが、一方で副作用もあります。
鎮痛剤で多い副作用は、「胃もたれ、胃痛」などの消化器症状。
そして鎮痛剤の作用としての「解熱」は炎症部位の熱を下げることは痛みには有効ですが、炎症部位以外の熱も下がってしまう恐れがあります。
熱が下がると痛みの症状が長引く、慢性化する場合もあるのです。
長引く痛みや慢性化している場合はどうしたらいいのでしょうか?
東洋医学では、
「不通則痛(ふつうそくつう)」という言葉があります。
言葉とおり「通りが悪ければ、則ち痛みが生じる」
通らないとは停滞、渋滞があるということ。水や空気など自然の物質はもちろん、政治、経済など、道路も停滞や渋滞が起こると全てがうまくいかなくなります。
これは人の体も同じことで
3つの通りが悪くなると、不調がでます。
身体を維持する3つは
「気・血・水」
「気」とは、身体を維持する生命エネルギーのことです。元気・生気・やる気なども含まれます。
「血」は、主に血液。
身体の栄養や潤いを与える物質
「水」は、「血」以外の身体を潤す体液のことです。汗、唾液、涙、尿、消化液などのことをいいます。
気やエネルギーの停滞が起これば、胸が詰まったり、お腹が脹ったりします。
血の通りが悪ければ肩こり、高血圧などが起きます。
また津液(しんえき)と呼ばれる体液が停滞すれば、むくみなどの症状が見られます。
この流れの停滞の原因は様々
体質、不摂生、生活習慣、過労、ストレス、加齢、運動不足、気候変化など…
薬を頼らず「痛み」とうまく付き合うためには
まずは何が痛み、停滞の原因なのかを見定めることが必要です。
安易に、「鎮痛剤」を使用して、体温を下げ、血流を悪くすることは
「痛み」だけでなく、自分自身が病気を治す力=免疫力も下げてしまいます。
基本的には痛みは
血の巡り、水の巡り、気の巡りが悪い、
もしくは「足りない」ことが原因で起きます。
見極めポイント
気の巡りが悪い
・体がだるい
・疲れやすい
・食欲がない
・風邪をひきやすい
・胃もたれしやすい
・冷えやのぼせがある
・急に顔が赤く、熱くなる
・急な頭痛や腹痛に襲われる
・手足に汗をかきやすい
・焦燥感に襲われる
胃腸の不調から気が不足している場合が多いです。忙しさや加齢に伴っても気が不足します。体を温め、気を補うものを摂りましょう。
食材では、豆類、ヤマイモなどのいも類、牛肉、鶏肉、豚肉、えび、うなぎ、穴子、鯛、鮭、まぐろ、たら、かつお、もち米、くるみなどがおすすめです
血の巡りが悪い
・アザができやすい
・手足が冷える
・肩こりがひどい
・髪の毛が抜けやすい
・顔色が青白い
・皮膚が乾燥して荒れやすい
・貧血になりやすい
・爪が割れやすい
・唇が乾燥する
・目がかすむ
・足がつりやすい
・集中力がない
コリや運動不足で血が順調に流れず体の一部で停滞したり、は栄養不足で起きます。
黒豆、ひじき、レーズン、プルーン、人参、レバー、カシューナッツ、クコの実、ほうれん草、鮭、さば、さんま、かつお、まぐろ、たら、うなぎ、鶏卵、レバーなども血を補う作用があります。
水巡りが悪い
・むくみやすい
・関節痛があり、手足がしびれる
・めまいや立ちくらみがする
・胃がむかむかして、嘔吐する
・鼻水が出やすい
・下痢しやすい
・のどが渇きやすい
水はけが悪い状態なので、水分調整をし、胃腸を強くする必要があります。
小豆、大豆、黒豆、黒米、ハト麦、山芋、昆布、わかめ、もずく、なまこ、あさり、ナス、きゅうり、春雨、きくらげ、きのこ類などをとりましょう。
体の不調だけでなく、心の不調がある場合もバランスが取れていない証拠です。
本来「身体は健康になるようにできている」のです。
身体はいつも健康に向かって進んでくれていて
不調というサインで様々なことを教えてくれます。
食べ物のバランスが乱れてるよ!
生活習慣が崩れているよ!
その考え方はストレスになるよ!
と生き方や考え方の軌道修正を教えてくれているのかもしれません。
何かを良い方向に変えるためには
健康分野に限らず
どんなことでも行動が必要です。
受け身なだけでは、変わらないこと、
行動すれば何かが変わること、
私も最近実感しています。
身体、心と上手に付き合っていきたいものですね。
巡りを良くしたい方、マッサージに行くことも行動のひとつです笑
お待ちしています♡

深く呼吸をすること

呼吸が浅いとか深いとか、
普段あまり意識をしないかもしれません。
でも疲れやすかったり、やる気が出なかったり、集中力がなかったり…
もしかしたら、その原因は「浅い呼吸」にあるかもしれません。
深い呼吸ができること…
語呂合わせはでなく
息(いき)をすることは
生きる(いきる)ことの一部です。
身体は生きるために必要なエネルギーを取り出すために酸素を取り入れ、燃えかすとなった二酸化炭素をはき出すために呼吸をします。
1回の呼吸で400~500mリットルの空気を吸い、1日に約3万回も呼吸をしています。
口や鼻から入った空気は、気管を通って肺に入り、このとき肺の中では、一瞬で空気の中の酸素を血液の中に取り入れ、いらなくなった二酸化炭素を出しています。
だから空気の良いところにいることはとても大事なのですね。
なぜ酸素が必要?
細胞内にあるミトコンドリアで酸素とブドウ糖が結びついて、生命活動のエネルギー(ATP)を作り出します。
酸素やブドウ糖が足りないとエネルギーを作り出せないので呼吸が浅いと疲れやすいということに繋がります。
また、脳は他の臓器と比べて10倍もの酸素が必要とするため
呼吸が浅いと脳へ十分な酸素が行かず、頭がボーとしたり、眠くなったりします。
そして自律神経が乱れて緊張状態が続くために不安や焦りを感じるようになります。
つまり
呼吸が浅い状態が続く
→酸素やエネルギーが不足→
倦怠感・頭痛・不眠・食欲不振→
自律神経のが乱れる→
血流が悪くなり免疫力や白血球の働きが低下
→病気になりやすい
鼻呼吸&口呼吸
基本呼吸は吐くときは口で吐き、吸うときは鼻で吸います。
意識して呼吸をする時は、必ず息を吐く方から始めてください。息を吐かないと新しい空気ははいりません。
腹式呼吸&胸式呼吸
・腹式呼吸
普段の呼吸は自律神経が支配していますが、吐く息に重点を置き、副交感神経を刺激することで深いリラックス効果などが得られます。
ヨガ、瞑想などや声楽の肺活量を増やす目的で使います。
・胸式呼吸
胸式では息を吸う時に意識して交感神経の方を刺激します。交感神経は活動を促進させるので、体や頭を目覚めさせたり、エネルギーの消費活発にします。
交感神経が働き出し代謝を高めるので、ピラスティスでよく用いられます。
リラックスする為には【腹式呼吸】
腹式呼吸の方法
① 背筋を伸ばしリラックスした姿勢になる。
*肩甲骨を引き下ろすように首を伸ばすと背筋が伸び、腹筋は引き締まります。
*また、アゴを軽く引いて、胸はそらし過ぎないようにしましょう。
②息を口からお腹をへこませるようにゆっくりと吐き切る。
③ 吐き切ったら、ゆっくりと鼻から 無理にお腹を膨らませずに吸います。
寝付きの悪い人へのお薦め呼吸法
6秒吐く ⇨ 1秒止める ⇨ 6秒吸う ⇨ 1秒止める 繰り返し
ゆっくりとした深呼吸を3~5分続る。特に吐くときに意識を集中。
筋肉と呼吸
また背中や肩甲骨、鎖骨、横隔膜付近の筋肉が硬くなっていると呼吸する時に動く筋肉の可動域が少ないため、呼吸が浅くなります。
逆に深い呼吸による効果は、酸素が脳に行く量が増えるだけではなく、呼吸を支える筋肉がよく動くことにより、身体の柔軟性もあがります。
また心の状態も呼吸に影響し、
人は心身がリラックスし気持ちが落ち着いている時は、自然と深い呼吸をしています。
反対に落ち着きがない時、感情が乱れた時、呼吸が浅く短くなります。
つまり、呼吸は心と身体を繋ぐものなのです。
酸素が必要になるとあくびをする、身体が固くなると伸びをしたくなる、という呼吸は身体の自然な働きです。
イメージも大事
朝や何か気持ちを切り替えて始める時には「元気が出る」って思いながら呼吸したり、
また、眠る時には大好きなことや幸せなことをイメージして呼吸をしたりすることも効果的です★
また、筋肉は、息を吸った時に固くなり、息を吐いた時に柔らかくなる性質を持っているので、マッサージを受ける時も呼吸を深くすることを意識すると
緩み具合が変わるかもしれません◟̆◞̆
私はなるべくお客様の呼吸に合わせるように意識をして指圧をしています。
施術者と受ける側の呼吸が合うことで
お互いの緊張がほぐれ、無理に力を込めなくても心地良い圧になります。
一生し続ける呼吸。
たかが呼吸、されど呼吸です。
皆さんも少し呼吸を意識してみてくださいね♪
腹式呼吸がよくわからない方はやり方をお伝えしますので聞いてみてください★

引き算する考え方

新しいものがどんどん増えて、どんどん便利になって、
それがないと「不自由」になってしまった今。
私たちは
いつも最新のもの、流行を追いかけ
足りない、足りないと欲しがるように、ないものにプラスする足し算の考え方で生きています。
でも本当はマイナスした方がいいもの
「引き算」の考え
=しなくて良いこと
考えなくてよいこと
食べなくて良いもの
をマイナスするのも実はとても大事なことです。
断捨離とデトックス
断捨離という言葉が流行りました。
言葉のとおり、断って捨てて離れる
「要らないものを手放す」こと
日本人は「捨てる」という言葉がゴミに直結するせいか、あまり良い事のイメージはありませんが
「手放す」ということは「必要なものを受け取る」ことでもあります。
ここ数日の私のテーマである
「本当に大切なこと」を見定め
自分に必要のないものは手放す
心の中は人によってキャパがある程度決まっているので、容量オーバーになると
必要なものさえ入ってこなくなります。
身体も同じで、
要らないものを溜め込んでいると、必要なエネルギーや水も入る余地がありません。
当然ながら疲労を溜めていたら良いエネルギーは入らないし、良い出会いや、良い出来事も起こりにくくなります。
濡れたスポンジが水を吸収できないように、要らないものは絞らないといけないのです。
だから身体に良いものをプラスして食べる事や、運動も大切ですが
「それを引き算したら健康になれること」も
実際多いのではないでしょうか?
食べものや飲み物かもしれませんし
考えすぎてしまうことかもしれませんし、イライラすることかもしれません…
シンプルに自分に必要なものは何かを
絞っていくと、モノも人も情報も感情も
大切なものだけが残る気がします。
私は2月は色んな意味でデトックス期だったと感じています。
本当に大切なもの、人、想い、と
私にとって必要ないものがハッキリした気がします。
今まであったものを手放した瞬間は
不安ですが、そこに必ず何か必要なものが入ってきます。
それが健康だったり、幸せだったり、大切な人だったり…
さぁ明日から3月なので
身体の老廃物も、要らない感情もデトックスしましょう🦋

〜表参道マッサージ整体サロン ・奏・〜
表参道駅徒歩2分 渋谷、原宿駅徒歩8分
和室の空間
肩こり、腰痛、頭痛、ストレス をリセット
指圧ベースの整体マッサージ
ドライヘッドスパ
マタニティ整体マッサージ
アクセスバーズ東京サロン
たからもの

ここ最近、お客様と色々な話をいていると私もたくさんの気づきがあります。
そして毎日の出来事の中にたくさんのメッセージが隠れています。
私はだまだ視野が狭く、色々なことに無知です。
だからこそ誰かの言葉がとっても嬉しかったり、逆に上手に消化できないこともあります。
今年になって、本当に大切なことって何だろう?とか幸せって何だろう?って問いかけ続けてきて、
「禅語」の本を久しぶりに開きました。
禅といえば、
座禅、ジョブズ、マインドフルネス…
禅語は、禅宗の僧侶たちの逸話や経典などから取られた言葉です。
明珠在掌(めいじゅたなごころにあり)
という言葉があります
明珠は、計り知れない価値があるもの。
在掌は掌(手のひら)にある。
"そんなすばらしい宝物をすでにその手に握りしめていながら、いったいどこを探しているのか"
という意味です。
大切な宝は
家族かもしれないし、仕事かもしれないし、夢や希望、それから自分自身かもしれない…
当たり前になりすぎていることがたくさんあって
幸せは人それぞれであり、
実は、自分が宝ものを持っていることに、私たちは、なかなか気づきません。
昨日と重なりますが
「大切にしているものは何か」
どうしてそれを大切に思うのか、と掘り下げて考えてみると
色々な気づきがあると思います。
他人をうらやむことなく、
目の前にあるやるべきことに、
全力で取り組むこと。
探しものは探してる時には
見つかりません。忘れたころに出てきます笑
ちょっとした至福のとき
家に着いての一杯のビール、熱中できる仕事や趣味、美味しいご飯、行きつけのお気に入りのお店、誰かの優しさ…
そんな日常のちょっとしたところに
幸せはあります。
今日もステキな1日になりますように★
奏通信8号をアップしました♪
https://izumi-kanade.com/free/tsushin

〜表参道マッサージ整体サロン ・奏・〜 表参道駅徒歩2分 渋谷、原宿駅徒歩8分 和室の空間と水の流れる音 肩こり、腰痛、頭痛、ストレス をリセット 指圧ベースの整体マッサージ ドライヘッドスパ マタニティ整体マッサージ アクセスバーズで脳をデトックス
