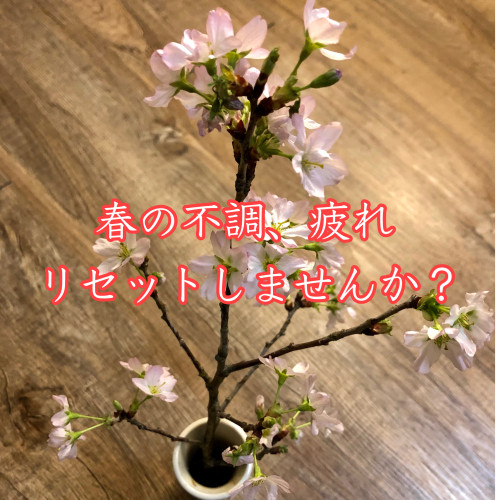♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ
脳のオーバーヒート【頭部内熱】が自律神経を乱す

考えごとをしすぎたり、忙しすぎて
頭に熱がこもったような感じがする
ことがありませんか?
発熱したときのように、おでこを触っても熱く感じるわけではなく、
カラダにこもる熱(うつ熱)が特に頭に集中することを
頭部内熱といいます。
この原因は常に頭を使い過ぎて体ののバランスを崩しているからであり
頭の使い過ぎ→頭が疲労→
脳がオーバーヒートして自律神経が乱れる
ことにあります。
脳は体の状況を五感(視覚・聴覚・平衡覚・味覚・嗅覚)で感知し、その感知した情報を元に体を動かしたりコントロールしていますが
入ってくる情報と、出力の仕組みがうまく循環していると、心身は正常機能した状態です。
現代社会の生活では
入ってくる情報が急激に増え脳が緊張して
情報処理に追いつけず自律神経が乱れてしまうのです
簡単に言うと脳のオーバーヒートで
頭部内熱は
・頭痛
・めまい 立ちくらみ
・耳鳴り
・不眠症
・不安症
・慢性疲労症候群
・胃腸障害
・アレルギー症状
・イライラ
・ドライアイ 眼精疲労
などの原因になっていることもあります。
頭の熱を下げる方法は2つ
頭の熱を全身から逃がす:全身の血行を良くする
熱を直接下げる:頭を冷やす
頭を冷やす方法は簡単です。
保冷剤などをタオルで包み
頭に当てる場所は耳より上の部分。
ココを冷やすことで脳にこもった熱は下がっていきます。 オデコや耳の上・後ろ頭など冷やして気持ちい場所が良いですね。 冷える+心地よさで自律神経は整っていきます。
注意としては首に当たらないようにすることです。
首を冷やすと体温が下がりすぎる傾向になってしまいます。
そして頭部内熱は
特に足の血流を良くして下半身に血流を流してあげることが大切です。
なので、本来は
頭だけ、上半身だけの施術はあまりオススメしません。
上部だけ血流が良くなると
頭に熱がこもって「のぼせ」の様な症状が起きやすくなるからです。
体の巡りを良くして
脳のオーバーヒート、解消しましょう。
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
アロマのコースについて

今月からアロマのコースを変更しました。
…といっても
90分120分コースは料金は変わらず全身オイル施術、
ご希望により指圧を混ぜることが可能です。
60分は部分コース(足裏、ふくらはぎ、背中、デコルテ)でハーフパンツ着用して頂いての施術となります。
料金は
60分7900円
90分9900円
120分11900円
そして、使用するアロマオイルをさらに品質の良いものに変えました。
ひとつは漢方配合のアロマ
リラックス用と呼吸改善用、ホルモンバランス用の
3種
もうひとつは
私のオリジナルブレンドの脳が整うアロマ
オレンジとラベンダーは認知症予防やリラックス効果、鎮静作用があるとされますが
ここ数年、ずーっと品質かつ香りの良いラベンダーオイルを探していました。
「ラベンダー」と言っても
ツンツンするようなものや、フローラル感が高いものなど色々あるのです。
やっとたどり着いたラベンダーとオレンジと
企業秘密のオイルをブレンドしています。
もうひとつはミカエルザヤットというメーカーのもの、感情などに働きかけるチカラが強いものです。
(ミカエルザヤット使用の場合+500円)
ご希望がない場合は基本、オリジナルブレンドのものを使用します。
アロマトリートメントは男性も受けて頂けます܀❀ .*゚
この時期
リラックス効果の高いアロマトリートメントは自律神経を整える作用も★
頑張りたくても、頑張れない…のは【気虚】?

肺虚、腎虚に続いて
今日は「気虚」についてです。
『気』は体を流れる水や血と違って、目には見えないものですが
元気の源である“生命エネルギー”であると同時に、精神をコントロールする気持ちの“気”でもあり
さらに体のすべてを動かしコントロールする“機能”でもあると考えています。
「気」の働きが不足している状態のことを「気虚」と言い
「元気」「やる気」「気力」などの「気」が不足して弱っている為、
何をするにも力が出なかったり、仕事や外出、遊んだりするのも億劫になっている無気力状態で
いわゆる「頑張りたくても頑張れない」ときは、気が不足しているのです。
また、「気」はウイルスなどの外敵からカラダを守るための防衛機能をコントロールしている
ため、気虚になると防衛力が落ち、外敵の侵入を防ぐことができないことにより、風邪やインフルエンザなどの感染症、花粉、ハウスダストなどによるアレルギー症状にかかりやすくなると言われています。
そして、温める力も弱まるのでカラダが冷えやすくなり、手足の冷えを感じ、低体温になりやすくなります。
原因はさまざまですが、
胃腸で「気」が作られると考えられるので、
胃腸の消化吸収力が低下すると、食べたり飲んだりしたものを効率よく「気」(=エネルギー)に変えることができなくなるのが大きな要因です。
ここに偏った食事、暴飲暴食や過労などが相まって
ますます気が足りなくなります。
ちょっとしたことも気になってしまう繊細な神経のタイプの人や
妥協が許せない完ぺき主義者であったり、嫌なことにも我慢して心に溜め込んだりする傾向がある人は
「気」が不足しがちに…
その他にも原因として、過労や睡眠不足、ダイエットなどが挙げられます。
気虚の場合、
消化吸収力をさらに低下させる冷たいものはできるだけ控え
また、「食べないと元気が出ない」と、無理やり食べ物を押し込むようなことはせず、「温かくて、消化のよいものを、腹八分目」で胃腸をいたわること、
過労や睡眠不足に注意することも大切です。
気虚の一番の養生はとにかく『休むこと』です。
体にとって一番の充電方法は“睡眠”なので
時間よりも"深く眠る"ことも大切です。
起きている間も、リラックスを心がけるようにし
好きな音楽を聴いたり、映画を観たり、どちらかといえば身体をあまり動かさないでも楽しめる「趣味」もおすすめです。
適度な運動も必要ですがハードな運動は気を消耗するのでNGです。ストレッチ、ヨガやゆっくりとしたウォーキングなどが良いとされます。
病は気から…
といわれますが「気」は生きるためにとても重要な存在です。
色々なことに気をつけながらも、気を使いすぎず
「気」を大切にしましょう。
ご予約はこちらから💁♀️🔽
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
元気がない、やる気が出ない…は【腎虚】?
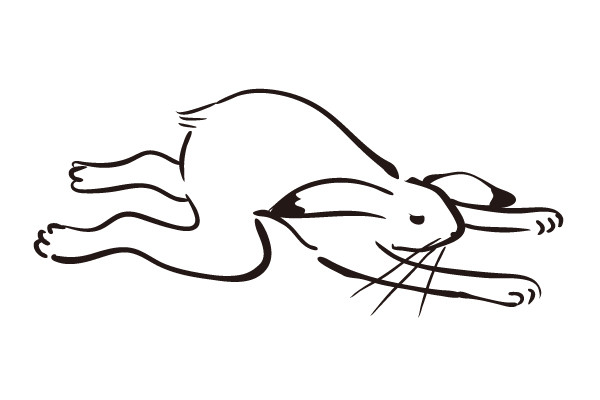
昨日は息苦しさの「肺虚」についてでしたが
今日は「腎虚」についてです。
疲れがたまりやすく、食欲も減退気味、
ボーっとしていることが多く、何もやる気が起きない…
いわゆるプチ鬱的なのは腎がお疲れ=腎虚なのかもしれません。
「腎」は腎臓そのものを意味するものではなく
幅広い働きをしています。
生命力の源となる『腎精(じんせい)』を貯蔵し、
毛髪、耳、骨、歯、腰を養い、脳下垂体、副腎、性腺、甲状線、すい臓などのホルモン系や免疫などにも関与し、五臓の根源ともいうべき重要な臓器とされています。
腎は生を受けたときにもつ本来のエネルギーを持っており
人は腎とともに成長し、年とともに衰えると考えます。
よく言われる「男性は8に倍数、女性は7の倍数」
で変化するというのはこのことで
エイジング(加齢)はまさしく腎の衰え=腎虚とも言えます。
現代は加齢というにはまだ早い若い人たちにも
腎虚体質の人が多いそうです。(若腎虚)
腎虚になると
「腰が痛い」「足腰に力が入らない」「耳鳴り、めまい」「難聴」「むくみ」「かゆみ」「冷え」「手足のほてり」といった症状が出てきます。
なんで「耳」の症状?なのかといえば
東洋医学では「腎」は「耳」につながっているという解釈があります。
人間の身体は会社組織のように、いろいろな部分と連絡し合って働いているのです。
腎虚の原因としては加齢だけでなく
ストレスや人間関係の悩み、過剰な肉体疲労、食の乱れやホルモンの影響などにあると考えられます。
腎を元気にするには
黒ごま・黒豆・昆布といった黒い食材をとること
そして
心臓は拍動のたびに心筋を収縮させて大量の熱を生み出し、血流に乗せて体中に送るので
多少心臓が高鳴るような「高揚感」=ワクワク感は体に不足した熱を補うために良いとされます。
やる気が起きないときこそ、
ワクワクすることを探してみる
というのも大切かもしれません。
体や心がどこか優れないな…という時は
筋肉をほぐして身体をリラックスさせるのも必要なことです。
何かと忙しい4月…
「あまり無理をせず」もポイントです。

ご予約はこちらから💁♀️🔽
呼吸が浅くなる時は…【肺虚】?

不安なことがあったり、忙しい時、ストレスがかかると
「呼吸がしにくく、何だか息苦しい」
ということがあるかもしれません。
眠りが浅い原因にもなります。
それはストレスや不安が肺機能を攻撃し
自律神経が乱れる「肺虚」という状態で
弱っている状態のことを「虚」といいます。
「虚」とは字のごとく、むなしいこと、うつろなことを意味し
生きて活動する上で、本来あるべきものがない状態といえます。
肺の機能が低下し、肺虚になると大気からエネルギー生成できない状態となり
自律神経が乱れ、呼吸器のトラブル(息苦しさ、咳、気管支炎など)が起きたり、過剰なエネルギーや水分を外に排出してしまい、肌のトラブルを招いたり、免疫力の低下を引き起こします。
すると体のバリア機能自体が低下し
体だけでなく、心のエネルギーも落ちてしまい
心も不安定になります。
「肺」が弱っている時は、「悲しみ」として現れ、
逆も然りで悲しみすぎれば、肺が弱ります。
そんな時は
まずはゆっくり休み、疲れをとって
緊張状態を緩め、自律神経を整えることが先決です。
そして、浅く早くなっている呼吸を
整えることが大切です。
私たちが意図的にその動きを調節できるたった1つの臓器は肺です。
肺自体を自在に動かすことはできませんが、肺と接している肋骨の筋肉=肋間筋や横隔膜を呼吸によって伸ばしたり縮めたりして内臓をマッサージすることができます。
だから、呼吸はとても大切なのです。
鎖骨付近や肩甲骨をほぐして
呼吸を深くできる体にすることで
体も心も安定するかもしれません。
ご予約はこちらから💁♀️🔽