♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ
10月10日【目の愛護】を

10月10日は目の愛護デーです。
10.10を横にすると、人の顔の目と眉に見えるからだそうです。
漢方などでは
「目には五臓六腑の精気が集まり、その力によって物をよく見ることができる」という理論があるそうです。
また、「目は肝に蓄えられている血の栄養によって働く(目は血を受けて能(よ)く視る)」とされ、目と肝には深い関わりがあります。
「肝」が弱ると「目」に症状が出て、
逆に、「目」を酷使すると「肝」が弱り、消耗します。
そして「肝」の働きは、解毒や代謝以外に
「蔵血(ぞうけつ)」という「血」を蓄える働き、
貯蔵した「血」を「疏泄(そせつ)」という巡らせ、血流を良くする働きがあります。
疏泄は「血」だけでなく「気」や「水」の巡りにも関係しています。
「血」を蓄えることで精神状態も安定するので、
「肝」の働きの中には情緒の安定にも関係します。
よく「疳(かん)の虫」といいますが疳は肝からきていて
肝が不安定になると癇癪を起すのです。
つまり
「目」を酷使すると、「肝」に貯蔵している「血」を消耗して、巡りが悪くなるのです。
さらに
「気」「血」「水」の巡りが悪くなり、
「気」の巡りの悪さで、肩こり、首凝り
「血」の巡りの悪さで、冷えや血行不良
「水」の巡りの悪さで、むくみ
が生じます。
このように目の疲れによって、目だけでなく全身に影響を及ぼします。
目のケアをしましょう!
・目を閉じる時間を増やしましょう
起きている時はずっと目を酷使しています。睡眠以外に
1日10分ぐらいホットタオルやアイマスクで視界をふさいでみてください。
強制的に目を休めましょう。
・マッサージ
温めた後は目の周りや眉毛の下の骨のあたりを親指のはらを使って
イタ気持ちいいくらいの強さでおしましょう。
・食べ物
ブルーベリー、なつめ、黒ゴマ、黒米、ひじき、黒きくらげ、レバーや赤身の肉・魚です。
赤や黒色の食材が「血」にいい食材です。
よく杏仁豆腐の上にのっている赤い実のクコの実は不老不死の食べ物と言われ、
これも目に良いそうです。
目の疲れもご相談ください◡̈

ご予約はこちらから💁♀️🔽
こころの回復方法

体の疲れは寝れば回復しますが
「こころ」が疲れている…と感じることがあると思います。
残念ながら、こころの疲れは睡眠だけでは回復できないケースがほとんどです。
寝て、忘れる
これができる人限定です^^;
こころには「エネルギーの法則」というものがあるそうです。
この法則はいたって単純で「注目するところにエネルギーが流れ、エネルギーが流れたところが肥大化する」というもの。
当たり前ですが悩みや、苦しみ、怒り、悲しみがあると、それを何とか取り除くために、その感情に注目してしまいます。
すると、その「悩み」にエネルギーが流れてしまい「悩み」や「苦しみ」が肥大化して、こころの中を占領してしまいます。
逆に言うと
楽しい、嬉しいことに注目できれば、こころのの中で、楽しいことがどんどん広がっていくというわけなのです。
全く関係ない行動をすることで気を紛らわせるという「気ぞらし法」と心理学で呼ばれる方法があります。
考えにとらわれないで済むように敢えて体を動かす(行動する)のです。それは、ストレッチでも、部屋の片付けでも、散歩をしたり、何でも良いのです。ただ、そのときに、嫌なことを考えないで済むように、その行動に集中するようにしてください。
それでも悶々とするときは
「誰かに話す」こと
最近の脳の研究では、不安は扁桃体という脳の領域が興奮したときに起こり、その興奮を収める方法は、言語情報だということがわかったそうです。
つまり、言葉にして口に出すだけで、扁桃体の興奮が抑えられて、不安などが収まるということです。
心の中にため込んでいることを言葉にして吐き出すだけで、問題は解決されなくても、気分は確実に楽になることが実証されています。
話す相手を選ぶことは大切ですが…^^;
わたしは何か悶々とする時は
神社に行ったり、カメラを持って出かけたりしますが
きれいな花や景色を見ると、心が変わったりするものです。
ストレスを溜め込みやすい方は自分なりの「気ぞらし方法」をいくつか決めておくのも良いかもしれません。
なるべく楽しいこと、嬉しいことに
エネルギーを使いたいものですね。
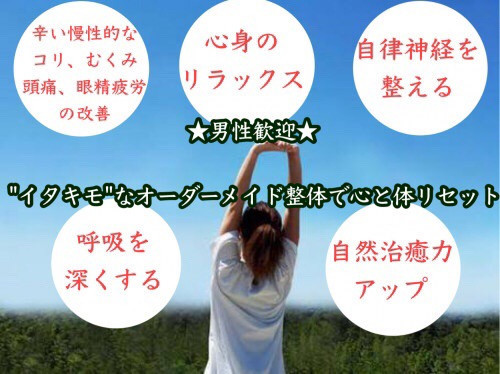
ご予約はこちらから💁♀️🔽
Cool head, Warm heart

英語の諺のようなものに「Cool head, Warm heart」というのがあるそうです。
直訳すると「頭は冷たく、心は温かく」という意味ですが
優しい気持ちや思いやりを持ちながら、冷静な思考を忘れないように、ということを説いています。
日本では昔から「頭寒足熱」が健康に良い状態だと言われていますが
東洋医学でも、「水昇火降(すいしょうかこう)」という言葉があります。
水昇火降とは、人間の心臓にある火のエネルギーが下に降り、腎臓にある水のエネルギーが上に昇ることで
水昇火降の状態だと、人は頭が涼しなり、気分がスッキリし、お腹は温かくなり、内臓の動きが活発化し、疲れにくくなる
というわけです。
「頭にくる」「カッとなる」「頭を使いすぎる」
と頭に血が昇り、熱くなり、お腹から下が冷たくなるので本来のバランスが乱れます。
また
寒くなると寒さにつられて不安や悲しいことを思い出したり、心が陰鬱になったりしやすく
心や体のバランスが乱れている時は
負のスパイラルを生みやすくなるので
まずはお腹や体を温めることで、エネルギーのバランスが整い出します。
不安な時、お風呂に入ったり、毛布に包まれたり、スープを飲んだりすると、ほっとして幸せな気持が増える体験は、あると思います。
物理的にあたたかいものを意識して身体の中に取り入れていくことで、身体はもちろん、心も温まるのは本当なのです。
体、こころ、温めましょう!

ご予約はこちらから💁♀️🔽
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
メンテナンス

突然寒くなり
体や心の疲れを感じやすい時期かもしれません。
気温や環境の変化…
毎日いろんなことがある中で
機械も故障することがあるように
心身も悲鳴を上げることもあります。
「頑張る」と「疲れた」はセットで
我を張っているために、気を抜いた瞬間どっと疲れたりします。
体が痛い時
心がしんどい時、
一時的に
何かに頼ったり
誰かに話を聞いてもらったりすることも
大切なことなんだと思います。
元気でエネルギーがある時は
受け入れられることが
疲れてエネルギーが下がっているときほど
受け入れられなかったりします。
そんな時は下がったまま動くより
必要なエネルギーを充電することが先決なのかもしれません。
「メンテナンスする」とは
見直すこと
振り返ること
次に活かすことをすること
前に進むことだけが大切じゃなく
ときに立ち止まってみることも必要なことです。
立ち止まってみると
前に進んでいるときには見えなかったモノが見えたり
気付かなかった感覚に気づいたり
思考の断捨離や整理できたり…
それが
「整える」ってことなのかなって思います。
寒い連休になりそうです。
体を温めてご自愛のもとお過ごしください◟̆◞̆
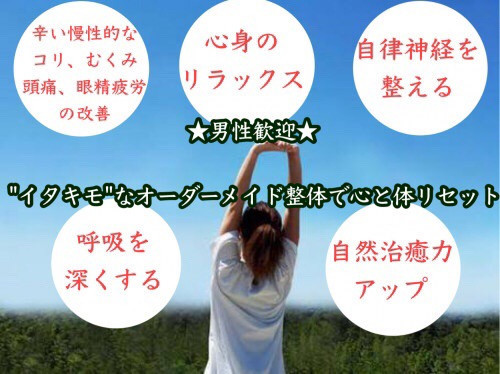
ご予約はこちらから💁♀️🔽
現代病になりつつある【脳疲労】

考えることが多すぎたり、悩み事などであれこれ思い悩むと脳の働きが低下していき
「脳疲労」を引き起こします。
情報があふれている今、パソコンやスマホ使用などにより、脳疲労のリスクは高まっていると言われています。
夜中に目が覚める、身体を使ってないのに疲れている、考えがまとまらない、食べ物が美味しく感じない、異常に食欲が増した…
などは脳疲労が原因かもしれません。
そして脳が疲労してくると、
感情が鈍くなったり、集中力が低下したり、思考力や判断力が低下したり、物忘れが多くなったり…と様々な症状が見られます。
脳疲労の主な原因は、
•頭が熱くなる(血液が脳に集まるため)
•眼精疲労
•ストレス
ストレスをなくすというのが根本的な解決策ではありますが
まず、頭を冷やすという原始的な方法も有効だそうです。
アイスノンや、シート、氷枕などでおでこや頭のてっぺんを冷やすと脳の働きが休まるといいます。
昔からよく冷静になれというとき
「頭を冷やして来い!」なんて言われますが
高ぶった気持ちを落ち着かせるという意味でも
理にかなった方法なようです。
さらに目元を温めると、眼精疲労が回復します。
もちろん睡眠をしっかりとること、
栄養のある食事をとることも重要です。
脳疲労が気になる方は特化したコースもありますのでご相談ください★

ご予約はこちらから💁♀️🔽

