♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ
脳も心も体も癒す【手】のケア

肩首、足、腰…マッサージをしたりケアすることがあると思いますが、
毎日当たり前のように使っている手。
もしかしたら一番頑張っている部位なのにあまりケアをすることはないのではないでしょうか。
離れた場所にありますが、手と脳はとても関係が深い場所です。
手を揉みほぐすことによって、脳の働きを円滑することが研究で実証されています。
人の脳にはワーキングメモリーと呼ばれる、短期記憶をつかさどる場所があり、様々な情報を一時的にここに記憶し、色々なことを判断しています。
忙しすぎたり考えることが多すぎると、脳がオーバーワーク状態となり、ストレスを感じたりイライラしたりして、ワーキングメモリーが正常に働かなくなります。
手にマッサージで刺激を与えることでワーキングメモリーがよりスムーズに機能するらしいのです。
手は「第二の脳」と言われ、手に刺激を与えることで脳のバランスが良くなり、ワーキングメモリーに負担をかけにくくなるのです。
そして
1.皮膚への効果
血行促進、マッサージの摩擦により皮膚の再生をスムーズに行うことができる 。
2.循環器機能への効果
手の毛細血管や毛細リンパ管を刺激し、血液とリンパ液の循環がよくなる。冷え性、むくみの改善や新陳代謝・免疫機能の向上につながる。
3.筋肉、関節への効果
循環器系の影響で血行がよくなり、筋肉の緊張がゆるむ。関節の動きもスムーズに。
4.自律神経への効果
ハンドマッサージのリラックス効果で副交感神経を刺激し、自律神経を整える。快感や幸福感を感じるホルモン(オキシトシン)の分泌も促してくれる。
実は、わたしのマッサージを始めるきっかけは
ハンドマッサージなのです。
整体院の前は美容室の受付をしていましたが
そこでカラーやヘッドスパ中のお客様にハンドマッサージをやらせてもらっていました。
何の特技も取り柄もないと思っていた私は
とてもやりがいを感じ、美容師さんのように
自分の手で何かできるようになりたいと思うようになりました。
というわけでハンドマッサージは私の原点でもあります。
そして、素敵なご縁で
ご自身でハンドクリームをプロデュースした方との出会いがあり、商品を置かせて頂くと同時に
こちらのハンドクリームを使ってハンドマッサージをさせて頂くことにしました。
お好きなアロマを混ぜて、手の平から肘まで
15〜20分程度。
香りとともに、普段頑張っている手を労って
心も脳もリラックス♡
しばらくキャンペーンにてプラス料金なしで
全ての整体コース、
アクセスバーズは90分以上から組合わせ可能です♪
ハンドマッサージ、ドライヘッドスパ、鎖骨指圧、
オイルフットの「末端ケアコース」も作りました★
(90分以上のコースは末端ケア+指圧が可能です。)
ご来店後にお伝えください◡̈
ご予約はこちらから💁♀️🔽
秋の物悲しさには理由がある

秋になると、どこか物悲しい、センチメンタルな気分になる…
哀愁の秋なんて言われ
秋はとても好きな季節ですが、なんとなくわかる気がしますね。
でも秋の物悲しさにはちゃんと理由があります。
季節のイメージ自体も関係していそうですが、物理的な面では、秋になると気温が徐々に低下するほか、日照時間が減少することなども影響しています。
気温の低下が生命維持において不安を抱かせやすくなることと
日照時間の短さによってセロトニンが普段より分泌されにくくなり
日照時間の長さや気温は、体感だけでなく心にも影響を与えます。
例えば、「なんとなくやる気が出ない」と感じることが多かっり、孤独や不安を感じやすくなったりすることもあるそう。
動植物にとっては秋は冬眠(休眠)の準備期間ともいえるので、夏から秋になることで、冬が近づくことを肌で感じ始める。
という本能的なものもありそうです。
もうひとつ東洋医学では、秋の季節に対応する感情(五志)は「悲しい」と「憂い」とされています。
この感情が強くなると、特に「肺」の機能が失調し、さらには肺に関連する鼻や喉、肌の不調にもつながります。
活動的になる夏ですが
秋分を過ぎると陰の気が増えるため
だんだんと意識は内側に向いていきます。
行動するよりも、静かに、穏やかに過ごす
それは自然の流れに沿ったことなのです。
秋はペースを落としてゆっくり歩み
冬に向けてスローダウン
そんな感じでしょうか。
寒暖差が大きく、夏の疲れもドッと出る頃
季節の巡りにあわせて、心も体も変化します。
疲れは蓄積する前にリセットしてくださいね。
本でストレスがダウン!?【読書療法】
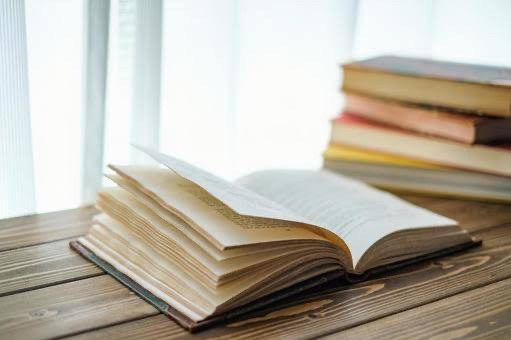
「読書の秋」
本を読むことは好きですか?
実は読書自体に癒しの効果があり
海外では読書セラピー(ビブリオセラピー)や
読書療法が存在するほどです。
歴史的にも古代ギリシャの図書館のドアには
「魂の癒しの場所」と記されていたといいます。
イギリスの調査によると、音楽鑑賞や散歩、お茶やコーヒーを飲む、ゲームで遊ぶなど様々なリラックス法のうち、もっとも効果的な方法が読書であることがわかりました。
ストレスレベルを68%も引き下げたそうです。
なぜ?かというと
読書で得た新たな視点をもとに自分がとらわれている思考パターンを分析し、より良い認知を身につけていく
例えば物語の中で自分と同じ問題を抱える登場人物に共感するときに、自分の問題を内省し
登場人物が最後に幸せになったとき、自分も同様に幸せになれると感じたり
また、登場人物が困難を乗り越えたとき、そこから問題解決の新しい方法を学べたり
また情報が文字だけに限られていると想像がふくらみ、自由に情景を思い描くことができます。
余白が多い分、物語を自分の状況に沿った解釈で受け入れることができます。
わたし自身が感じることは
本の中のセリフに心に響くことが多々あったり
単純に「続きが気になる」というワクワク感も
読書の醍醐味?です。
ただ、疲れている時に、あまり複雑な本を読むと頭が疲れてしまうというのも事実です^^;
癒し効果を求める場合はハッピーエンドの物語がオススメです。
とはいえ読書習慣のない人が急に読書をするとなると抵抗があるかもしれません。
まず1ページや1段落、○分と決めて
食事を済ませた後や、夜布団に入ったとき、帰りの電車に乗ったとき、など毎日する行動に繋げて本を開くことで習慣化しやすくなります。
美味しいものや季節を感じながら、
秋を楽しみましょう★
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
【肺活】で体や心を強くする

昨日の続きで「肺」の話です。
呼吸の質が、健康状態に大きく左右するということは最近よく言われていますが
ひとは呼吸によって取り入れた酸素と食べ物から取り入れた栄養を結合させることで、生きるエネルギーを生み出しています。
数日食べなくても生きていけますが、数分呼吸ができないと人間は生きていけません。
呼吸で酸素を取り入れることは、それほど脳や体にとって大切なことなのですが
たっぷり酸素を吸えていない人が多いといいます。
座りっぱなし、運動不足など…現代のライフスタイルなどで肺の機能の衰えが大きな原因です。
肺の機能が弱まると、血液中に酸素を充分に取り込むことができず全身の細胞や脳が酸素不足になり、疲労やメンタルトラブルの一因になったり
ま 足りない酸素を補おうと呼吸の回数が増えて浅くなります。
浅い呼吸は自律神経のバランスを崩すことになり
様々な不調が出てくるわけです。
肺も筋内と同じように、鍛えることができます。
肺活のポイントは肺を収めるかご状の骨格である「胸郭(きょうかく)」
胸郭には呼吸のために使われるさまざまな筋肉がくっついていてこの「呼吸筋」を鍛えることで、胸郭のスムーズな拡張が促され、深い呼吸ができるようになるんだとか。
肺を鍛えるトレーニング
1.足を肩幅に開き、まっすぐに立つ。
2.両手を頭上に伸ばして、手首を交差させる。
3.鼻から息を吸いながら、腕を上に伸ばす。
4.口から息を吐きながら、体を右へ倒す。
5.鼻から息を吸いながら、体をまっすぐに戻す。
6.口から息を吐きながら、体を左へ倒す。
呼吸しながら筋肉をのばすと、胸郭全体のストレッチになります。5回を1セット 毎日1~3セット行うと良いそう。
肺が弱って呼吸が浅くなり交感神経と副交感神経の働きにメリハリがなくなると、自律神経を乱し、負のスパイラルとなって、免疫力も落ちてしまいます。
逆を考えると、肺が元気でしっかり呼吸できれば
自律神経が整い、免疫力もアップ⤴️
温活、腸活、肺活…
やることは色々とありますが、毎日の生活を健康に
穏やかに送るためにはちょっとずつの積み重ねが
大切なことかもしれません。
意外な【肺と腸】の関係
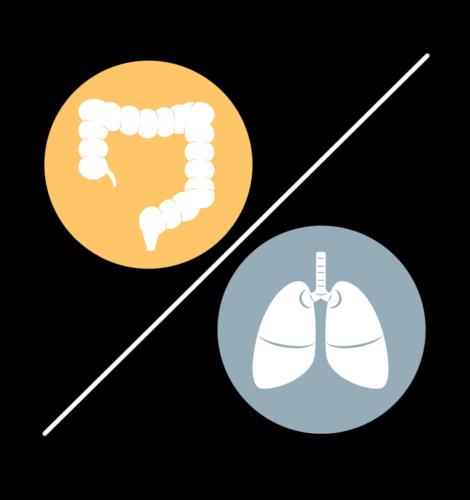
秋の気配が感じられますが、暑い時とは違った
不調が出やすくなる頃かもしれません。
気温が下がり空気が乾燥してしてくると、
肺は呼吸によって体内の水分量を調整します。
大腸は消化された食べものに含まれる水分を吸収し、腎臓に送って循環させます。
つまり秋に重要な臓器は「肺」と「大腸」
実は肺と大腸には「リンパ」が網の目のように張り巡らされています。
リンパ管には沢山の免疫細胞があり、空気や食べものなど外界から入ってくものから、からだを防衛する役割をしています。
そのため、肺と大腸は最大の免疫器官なのです。
リンパの流れが悪いと老廃物がうまく排出できずに、毒素が溜まって
アレルギー症状や鼻炎、口内炎、むくみ、便秘や軟便などは、免疫機能が低下しているサインかもしれません。
そして東洋医学では肺と大腸は表裏の関係で、肺を良くすると大腸も良くなるといわれ
その逆もまた然りです。
食欲の秋ですが、
暴飲暴食などで腸が疲れたり弱ると、同時に肺も弱るので
・外からの刺激(冷やすことや菌など)から守ること
・中からの刺激(食べ物の質や温度、量)が
とても大事ということです。
重複しますが…
体が冷えていると花粉やウィルスなどの邪気から体を守ることが出来なくなってしまいます。
まず体を冷やさないようにすることが
バリア機能を高める第一歩です。
そろそろ温活、
そして肺、腸を大切にしましょう!
ご予約はこちらから💁♀️🔽
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku


