♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ
クールダウン

8月最後の日、
毎年言ってますが…笑
今年はとても暑かったので、疲労感を感じている方も多いかもしれません。
8月が終わると、秋に向かいますが
体も心も頭も、夏の熱が溜まっています。
暑い季節のエネルギーは身体だけでなく心にも影響します。
テンションが上がりすぎたり、興奮しすぎたり、心にも熱がこもりやすくなります。
でも、上がったものは必ず下がり、
差が激しいテンションの降下はやる気の減退や心にモヤを作ることにもなります。
なので
熱くなっているものを鎮める、クールダウンが
必要です。
一度、落ち着かせ、次に行くために。
神経は思ったより、休ませるのが難しいものです。
気が高ぶって、疲れているはずなのに、かえって眠れない
なんてこと、ありますよね。
自分なりのクールダウン方法を持っておくことをお勧めします。
ストレッチ、ヨガ
散歩をする
ペットとくつろぐ
マッサージをする
湯船につかる
音学をきく
瞑想…
ストレスやイライラなどを無理になくそうとするのではなく
それを感じたら、早めに気づき、クールダウンするための方法を用意しておくことは大切です。
特に体の疲労がたまっているときは、気持ちのコントロールがより難しくなるので
早め早めの休息を心がけて、
月末、夏の疲れをクールダウンしましょう。
9月クーポンもアップしています★
ご予約はこちらから💁♀️🔽
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
⚠︎【寒暖差疲労】注意報

昨日あたりから急に気温が下がり、
過ごしやすいとはいえ、こういう時にドッと夏の疲れが出る…なんて方も多いかもしれません。
季節の変わり目に体調を崩しやすいのは
気温の変化に体がついていかない=寒暖差疲労を起こしているからです。
体温を調整する機能は、自律神経が担っており、暑い時は手足などの末端の血流がよくなることで放熱や発汗を行います。
逆に寒いときは、無駄に熱が放散しないよう血管を収縮させるというシステムが働きます。
そのシステムに肝心な自律神経は外気温の変化によるストレスで乱れやすいもので
うまく自律神経のスイッチが入らなくなると、体温調節がうまくいかず疲労がたまりやすくなり、全身の倦怠感につながることも…
寒暖差疲労を起こしやすいひとつの原因は
「血行不良」です。
秋口になり外気温が下がったり、夏場の冷房や冷たいものの飲食で身体が冷えてくると、手足の末端の血管も閉じていきます。
すると体中の血流が滞り、それに伴った頭痛など痛みや不快感とも深くつながっているのです。
寒暖差疲労の簡単にできる対策は、
「循環を良くすること」「体を温める」ことです。
➀軽めの運動
➁お風呂に浸かる
➂適度な休息
④温かい食事、飲み物
今月も残り2日…
夏が終わるのは少し寂しい気もしますが
血行を良くして、食欲、芸術の秋を楽しむ準備をしましょう!
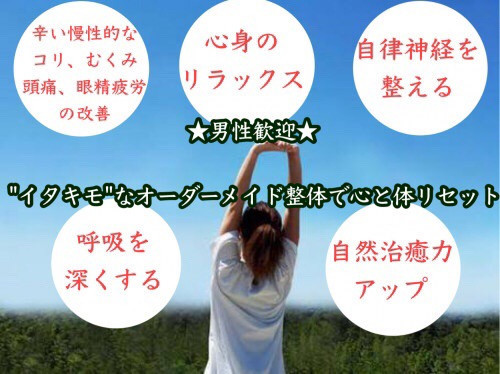
ご予約はこちらから💁♀️🔽
右脳と左脳のバランス

人の身体の機能を司る脳。
人には利き腕と同じように“利き脳”が
あるといわれます。
よく
「絵が上手だから右脳派」
「数学が得意だから左脳派」とか
右脳は芸術脳、左脳は言語脳
などと言われたりしますが
右脳・左脳の特徴から
右脳はアナログ脳、左脳はデジタル脳と呼ばれることがあります。
つまり
左脳は論理的・分析的で言語を司り、右脳は直観的・感性的で空間的な思考を司っているということです。
|
右脳の能力 |
左脳の能力 |
|
隠された意味(比喩)を読み取る |
話す |
|
顔を認識する |
読む |
|
左側の身体ならびに資格空間の統率 |
書く |
|
空間の知覚 |
言語的な記憶の統合 |
|
“道を探す”能力 |
抽象的な分類 |
|
視覚的結末 |
音楽的能力 |
|
音楽的感覚 |
連続的な細かい手作業 |
|
記憶統合の形成 |
一度に一つ以上のものを見る |
|
絵の適切な形成 |
左右を見分ける |
|
|
絵の詳細 |
そして
右脳と左脳は思考方法が違います。
右脳はイメージで思考するのに対して、左脳は言葉で思考します。
言葉で考えられる事が、思考だと思いがちですが、
実は私たちは普段からイメージで思考をしています。
でも右脳と左脳は、片方だけを使うという事はなく、「偏りがある」という表現が正しいかもしれません。
「デジタル脳」である左脳は堅実的で真面目な脳です。
でも左脳は右脳に比べて容量が少ないのですぐにパンパンなってしまうのです。
それ故、多くの情報を詰め込むとパンクしてしまいストレスの原因になってしまいます。
「アナログ脳」の右脳は
目や耳で入った情報を感覚で記憶し、見たり聴いたりして感じたものを、クリエイティブな発想やアイディアに変える能力があります。
つまり右脳が活性化すれば左右のバランスがとれ、それぞれの特性を活かすことで、使いすぎた左脳のストレスを打ち消すことができます。
もっと言うと
右脳を活用すると脳の中がリフレッシュされて仕事で主に使う左脳の働きがよくなります。
右脳を活性化のメリット
・判断力の向上
・記憶力の向上
・クリエイティブな能力の開花
右脳を活性化するには?
1 体の左半身を使う
左手でご飯を食べてみる、左手で字を書いてみる、左足から歩きはじめてみるなど普段右でやっている動作を左にしてみる。
2 音楽を聴く
右脳を鍛えるためには、歌詞の入っていないクラシック音楽が良いとされ、中でもモーツァルトが抜群だそうです。
3 瞑想をする
瞑想で「呼吸に集中させて、心を無にする」ことで左脳的な機能である言語や思考をストップさせて、右脳的機能である感覚を研ぎ澄ませることができます。
結局は大事なのはバランスです。
脳はPCのやような高機能を持っているのに普段人間の多くは、その3%や10%も使いこなせていません。
右脳が開花すると、左脳の100万倍以上のスーパーコンピューターが活動することになり、脳全体も使われていない領域が活性化し始めるそうです。
何だか、ぼーっとする、やる気が起きない、アイディアがわかない…
そんな時は右脳を使うことを意識すると良いかもしれません◟̆◞̆
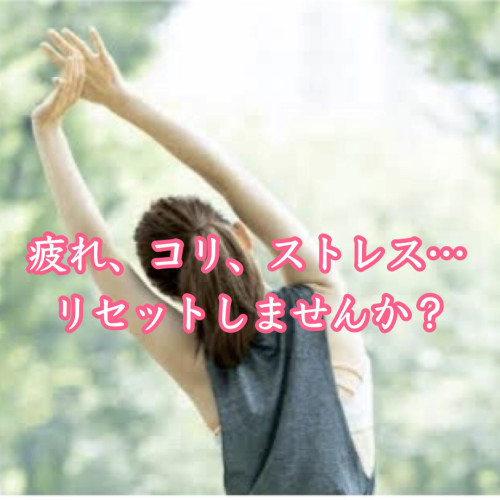
ご予約はこちらから💁♀️🔽
体の声を聞くこと

日本人は責任感が強く、真面目で勤勉、
限界を超えるまで頑張ってしまう傾向にあり
自分が疲れていること自体に気づけない...
人が多いといいます。
だからこそ「体の声を聞く」ということはとても大切なことかもしれません。
体の声とはどいういうことなのかというと…
体の感覚には運動感覚のほかに
内臓感覚(内部感覚)と言うものがあります。
この感覚があるからこそ
体が発するSOSのサインをキャッチすることができます。
「外部感覚」は、目、耳、鼻などいわゆる五感で
これらは、野生で敵や危険から身を守るために必要なものでもあるため、意識を向けやすいです。
「内部感覚」は
血圧の変化を感知する「圧受容器」、体の傾きなどを感知する「三半規管」
感覚としては重苦しさ、胸苦しさ、息苦しさ
抽象的に言うとソワソワするとか、
ドキドキするとか、
なんとなくの違和感…
いわゆる第六感はこの内部感覚だという説もあります。
この内部感覚にしっかり意識を向けるためには
外部感覚は刺激が強く、意識を内部に向けようとする際に、邪魔になってしまうことが多々あります。
外部感覚の五感の中でも、最も多くの刺激を受けているのが「視覚」です。
人は目からの情報をとても頼りにしており、実際に人の認知機能に与える影響は80%が視覚情報とも言われています。
現代社会は目からの刺激や情報が多すぎて
体はしょっちゅう私達にメッセージを発信していますが、そのメッセージを受信できる余裕がないのです。
だから、体の声を聞くことができなくなっています。
目からの情報を少し遮断し
意識的に、内部感覚を感じ
食生活、睡眠、運動、精神状態…
本当に自分の体が欲しているものは何か
そして一番大切なことは、
何か不調があるとき
なぜこの症状が出たのか?
ちゃんと自分の体に聞いてみると
多分本当の答えは、自分の体が知っているのだと思います。
まず、いま
本当に体が必要としているものは何でしょうか?
胸の緊張を緩める

呼吸が浅いとか、
寝つきが悪い、胃腸の調子が良くな
という方がとても多いです。
ずっと座りっぱなしでパソコンを見ていたり
身体が冷えたり、緊張やストレスを感じると
「胸」が緊張してしまいます。
その胸の緊張が頭まで強張らせて
・頭痛
・イライラ
・自律神経の乱れ
につながるだけでなく
肺の動きも悪くして、呼吸も浅くなってしまいます。
胸の緊張を緩めるには
「肋骨」の動きが大切で
「肋骨を上げる」方法が効果的だそうです。
肋骨は
鳥かごのように
内蔵を包んでいる12本の骨で
いわゆる「あばら骨」です。
この肋骨が下がっている人が多いそうで
原因は、
パソコン、スマホ、読書、車の運転など
日常生活で背中を丸める動作が多いからです。
この姿勢が続くと
肩関節が前にずれ、首が前のめりになり、
あごが前に出て、胸が狭くなります。
そして、肋骨が下がります。
肋骨が下がると肩がこりやすくなり
・左右で肩の高さが違う。
・肩がいつも凝っている
・呼吸が浅い、深く呼吸ができない。
・脇腹を触られるとくすぐったい
当てはまる方は肋骨が下がっているかもしれません。
逆にいうと
「肋骨を上げる」ことで胸の緊張を緩めることができます。
🍀肋骨を上げるセルフケア「肋骨締め」
・長めのタオルor 手ぬぐいを用意。タオルを10cm程度の幅に折り、背中に当て、肋骨のいちばん下あたりに持ってきて、ギュッと巻きます。
息を吸い、吐きながらお腹を凹ませ、同時に締めていきます。
・タオルを巻いた状態でまずは深呼吸。左右の手を肋骨に当てます。
鼻から息を大きく吸い込み、口から息を吐きます。
10秒に1回のペースで、最低3回。
・足を肩幅に開いて立ち、両手を骨盤に沿わせるように置き、左右の親指で腰の骨を押しながら体を後ろに反らします。気持ちいい範囲で10秒キープ。
この肋骨締めにより、内臓機能の向上、くびれができるなどの効果と
ゆっくり深い呼吸をするようになるため、息苦しさや呼吸の浅さ、ストレスを緩和できる可能性があります。
奏では直接肋骨を触ることはあまり
しませんが、肋骨は肩甲骨とも繋がっているため、肩甲骨を緩めることで肋骨の矯正にも繋がります。
肋骨、意識することは少ないですが
下がった肋骨が上がると
頭痛やコリや呼吸、睡眠の浅さ…少し楽になるかもしれません。
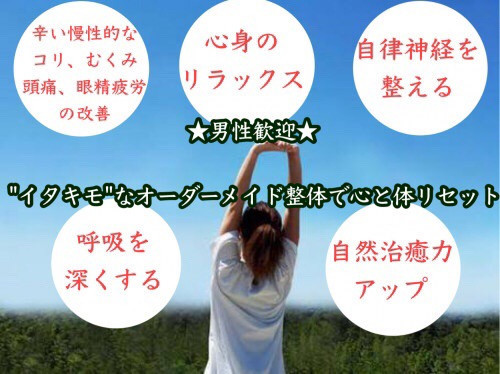 ご予約はこちらから💁♀️🔽
ご予約はこちらから💁♀️🔽
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
