♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ
肩甲骨の可動域を上げるメリット

痛みやコリが出やすいけれど自分では手が届かない
「肩甲骨」
肩甲骨は、とても特殊な形をした骨で
腕や肩の動きだけでなく呼吸にも大きく影響します。
肩甲骨は【体を支える】ためのものであり
【腕の可動域を広げる】役目がありますが
肩甲骨には非常に多くの筋肉が付着しているため、
おかげで自由度の高い動作が可能になります。
肩甲骨が硬いということは、肩甲骨が肋骨に癒着してまっている状態です。
肩甲骨は、肋骨の上を滑るようにして動くので
肋骨と肩甲骨が癒着して固まっている場合、肩甲骨は肋骨の上を上手く滑ることが出来ず、可動域が狭くなってしまうのです。
すると
- 肩が凝りやすい
- 呼吸が浅くなる
- 血流が悪くなる
- 周りの筋肉も硬くなりやすい
- 可動域に制限がかかり他の筋肉へ負担が増える
- 五十肩、四十肩に発展することも
- 血行不良により代謝が落ち、太りやすくなる
頭が下がって背中が曲がった姿勢をとり続けていると、背中がガチガチになり、肩甲骨と胸郭の隙間が挟まります。こうなると、肩甲骨が邪魔をして胸郭がうまく広がらないため呼吸が浅くなります。
肩甲骨がスムーズに動くことで
まず、呼吸の質が上がります。
- 血行がよくなり代謝があがる
- 筋肉の緊張から起こる頭痛の改善
- 姿勢がよく見える
- 肩コリ、首コリの軽減
肩甲骨周辺筋肉が硬くなると、肩甲骨が肋骨に張り付く形で固まってしまうので
有効なのが肩甲骨を肋骨から「剥がす」ストレッチです。
→肩甲骨はがし
残念ながら肩甲骨は、自らスライドすることはできますが、はがれることはできません。
なので人に剥がしてもらうことで可動域があがり
セルフストレッチではできないメリットがあります。
肩甲骨を剥がしたい!
マッサージの全てのコースに肩甲骨はがしがついています♪
アクセスバーズのお客様もご希望があれば
リクエストしてくださいね◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️⬇️
心と体がバラバラな時は…

忙しすぎて、色々考えることが増えたり
心配ごとがあると
そのことで頭とこころがいっぱいになって
「心ここにあらず」になったり
体が浮き上がって、先の方に行ってしまいます。
また楽しいことやワクワクしすぎるこも
心がフワフワからだを離れて浮かび上がってしまいます。
体と心が離れがちになると
集中力が低下し、うっかりミスが増えたり
つまづきやすくなったり
体が置き去りになるので
ケガをすることも増えたります。
新しい環境や生活の中で
どんなに忙しくても、ワクワクしていても
心と体を一致させることが大切です。
よくゾーンに入ると言いますが、そのためにはこの「心身一体」になり、余計なことは何一つ考えずに
一点集中することだと言われます。
そのためには、それは一つ一つの行動を「ゆっくり、丁寧に」を意識することです。
「早く、雑に」を繰り返すと益々「早く、雑に」なり「ゆっくり、丁寧に」を繰り返すと、ある時から「早く、丁寧に」なり
スポーツ、楽器、書道など全てに共通する上達のコツなんだそうです。
・靴をしっかり揃える
・ドアを丁寧に最後まで締める
・物を静かに置く
・お札の向きを揃えて入れる
そんなことが、心と体を一致させる訓練になるそうです。
また心と体が離れていると気づいたら
大きな深呼吸を数回くりかえして、意識をからだの中に向けるようにしてみてください。
心と体、一致させましょう。
 ご予約はこちらから💁♀️⬇️
ご予約はこちらから💁♀️⬇️
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
イライラ、不安、だるさ…春の不調と〇〇の関係

新生活や寒暖差…
変化の多い春は自律神経のバランスを崩し心身に不調が出やすい季節です。
そして実は
いつもはあまり意識することがないかもしれない部位ですが
「肋骨」が、自律神経と大きく関係しています。
肋骨の可動域は意外と高く
肋骨は呼吸と同時に開閉したり、胸椎と共にねじりや前後屈方向へも動きます。
肋骨の下に、ドーム状についている筋肉(横隔膜)が上下に動くことによって、呼吸し
体に酸素などが送られますが
ストレスや姿勢の乱れ、運動不足などから肋骨の動きが悪くなると、呼吸が浅くなるのです。
自律神経というのは無意識下ではたらく神経ですが唯一、意識的に調整できるのは呼吸です。
肋骨の動きが悪くならないようにするには
肋骨周りの筋肉を緩めることが大切です。
呼吸には背中、鎖骨などの筋肉も大きく関わっているので、これらをほぐしてあげることで
呼吸が楽になります。
春の不調…
肋骨周りの筋肉を緩めて
呼吸を深くできるようにすることで、楽になるかもしれません。
呼吸の浅さ、ご相談ください◟̆◞̆

ご予約はこちらから💁♀️⬇️
頭と体のバランスを保つには

昔の生活は畑を耕したり、歩いて移動したり
頭より体を使うことが断然多かったと思います。
現代の生活は逆に頭ばかり使うことが多くなりました。
健康に過ごすためにはどちらもバランスよく使うことが大切で
「一読、十笑、百吸、千字、万歩」
どういうことかというと
毎日これをすることで元気に過ごせるよ!
という意味です。
本来は「高齢者の方」がということですが
若い人にも必要なことだと思います。
一読: 一日1回文章を読む
十回: 一日10回笑う
百吸: 一日100回深呼吸する
千字: 一日1000字書く
万歩: 一日10000歩を歩く
私自身は最近、読書ブームなのですが
本を読むことはとてもおすすめです。
最近、心から笑うことが少なくなったと感じますが
笑うことは、免疫力もあげます。
そして深呼吸、大事です。
深呼吸すると、副交感神経の緊張が高まり、神経の高ぶりが治まり筋肉の緊張も緩みます。
書くという行為は書く前にいろいろ頭の中を整理したり、物事のとらえ方を普段から考えるようになるとちいます。
千字、万歩は毎日というのは
なかなかハードルが高いかもしれませんが
頭、体…バランスよく使いたいものですね。

ご予約はこちらから💁♀️⬇️
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
TOO MUCH SITTING!
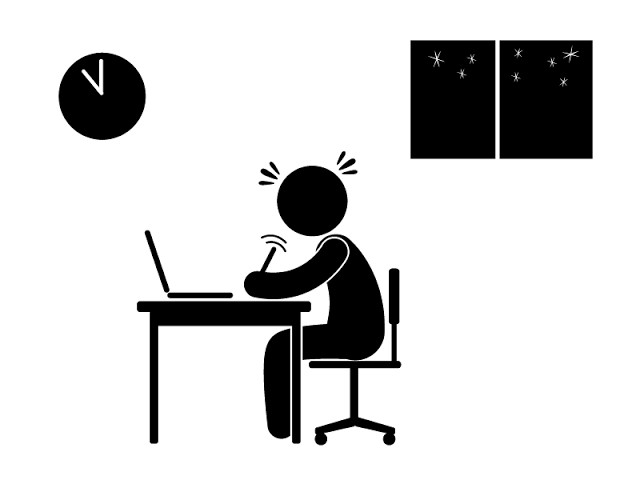
1日にどのくらいの時間、座っているでしょうか?
TOO MUCH SITTING(座りすぎ)というフレーズが世界中で言われているらしいのですが
1日に座っている時間は、日本人が世界で一番長いと言われています。
長時間のパソコン作業、自宅でじっとテレビを見たり、スマホをいじったり…。知らず知らずのうちに陥っている「座りすぎ」状態による身体と心への健康被害は、実は想像以上に大きいようです。
長時間連続して座り続けることで筋肉の約7割が集中している下半身の活動が低下して代謝が悪くなり、肥満血流が悪くなることで様々な不調や病気の要因になりかねません。
「Sitting is the New Smoking!」=座りすぎの生活はタバコを吸うのと同じくらい悪いとすら言われるようになりました。
そして恐ろしいことに、座りすぎは体だけでなく
メンタルにも影響し
座りすぎは不安症を発症するリスクが増えることが
わかっています。
ある研究で
心の健康(メンタルヘルス)は平日の睡眠、座位行動、身体活動のバランスが関連していることが分かり
この結果を基に、座位時間を1日当たり60分減らして、その60分を睡眠に充てると、メンタルヘルスの不調が11〜26%ほど低くなる可能性が示されました。
つまり座っている時間を1時間減らして
その1時間を睡眠に当てると、精神的不調が改善するというわけです。
とはいえ…デスクワークの方は仕事の時間を簡単には減らせないですよね。
まずはなるべく日常生活の中で「歩く」「動く」ことを心がけ、寝る前にストレッチをしたり、睡眠時間を増やすことも大切かもしれません。
座り仕事の皆様…本当にお疲れ様です!

ご予約はこちらから💁♀️⬇️
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
