♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ
肩こりや首こり…ここを見落としてます!

最近、スマホが進化するにつれて重くなっていたり
指や手首にかかる負担が増していると言われます。
なぜか腕が重だるい…なんてことはありませんか?
親指付け根と反対側の小指側掌にある厚みのある箇所をそれぞれ母指球、小指球といいます。
その箇所と箇所に挟まれた、手相で言う生命線の終わり辺り、親指と小指の先をくっつけようとした時の谷間辺りに、手首と掌を行き来する神経や血管の通り道、手根管があります。
ここが狭まると手や指がだるくなったりひどい時は痺れるような感覚があったりします。
それによって腕全体が、いや体全体が影響を受け
- 腕の筋肉が緊張して内側にねじれる
- 肘の動きが硬くなる
- 二の腕の筋肉が硬くなる
- 肩の関節が内側にねじれて脇が開く(肩関節の内旋・外転)
- 胸の上のほうの筋肉(鎖骨のまわり)が緊張する
- 首を支える筋肉(胸鎖乳突筋や肩甲挙筋)が緊張する
- 頸や肩甲骨の動きが悪くなり、肩や背中がこる
このように手の疲労から連動して起こるのが「手からくる肩こり」です。
というわけで
腕や手はこんなにも使っているのに、あまりケアすることが少ないかもしれません。
奏のオイルハンドマッサージは何気に隠れ人気です★
ぜひリクエストしてくださいね。
毎日頑張ってくれている手や腕も労ってあげましょう!

ご予約はこちらから💁♀️⬇️
「張る」という症状からわかること

お腹が張る、脇ばらあたりが張る、こめかみが張ったように痛い、など「張る」という症状…
東洋医学では「張る」症状は、気滞(きたい)と判断します。
気滞とは字のごとく気が滞り
気という概念は目には見えないのでわかりにくくはありますが簡単に言うと「身体のエネルギー」=元気のもと
です。
体内を流れる気がスムーズに回っていない状態で、気の流れが止まるなど全身に回らないことや、本来の流れとは逆に、下から上へと逆流することで様々な変調を来たします。
原因としては精神的なストレスやダメージが大きいと考えられます。
常に精神的にプレッシャーを感じている、人間関係で悩んでいる、最近不幸なことがあったなど、ごく身近なことが原因になったりもします。
自分ではそれなりに毎日を過ごしていると思っていても、几帳面だったり、優しくて気を遣う性格の方、時間に追われていたり忙しくて常に脳がオンの状態であれば、ストレスを感じていなくても気滞が生じます。
また人によっては、寒さや暑さ、湿気や照りつける日差し、騒音や不快臭など、環境が原因となることもあります。気候や外傷も気滞につながることもあります。
お腹の張り、膨満感、ガスが溜まるなどの症状は冷えや便秘、胃下垂などでも起こりますが、気滞が関係することも多くあります。
何かと「張りやすい」方は気滞を改善するためはまずストレスを発散することが重要です。
リラックスの時間をつくるのも手段ですが
そもそもの思考様式を変えるというのも長い目で見ると大切なのかもしれません。
「考え方は簡単に変えられない」と思いがちですが
考え方は癖なので繰り返すことによって、徐々に思考様式は変化していきます。
・ストレスをため込まない考え方の癖をつける
・体の巡りを良くし、リラックスする
ピンと張っているものを緩ませ
張りすぎない心と体を目指しませんか?
まずは筋肉の張りも解消しましょう。

ご予約はこちらから💁♀️⬇️
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
6月の過ごし方

6月になり、梅雨入りする地域もあり、徐々に蒸し暑い日が増えていきます。
このジメジメとした暑さが胃腸(脾)の働きに影響を及ぼすため、体内に余分な湿気が溜まってしまう時期でもあります。
「身体がだるい」「頭が重い」「やる気が出ない」
という人も多いかもしれません。
身体の中に湿気が溜まると、いわばスポンジが水を吸って重くなった状態なので
ずっしり水を吸ったスポンジのように
身体や頭が重いということが多くなります。
とくに、ストレスなどで胃腸が弱って身体の水分代謝が悪くなっている人は、雨の日など、外からの湿度に影響を受けやすくなりがちです。
体質的に「脾」(胃腸)が弱い人もいますが、現代のストレス社会では、「肝」(自律神経)の乱れから、「脾」の乱れを招くケースもあります。
ストレスが溜まってイライラする→過食気味になって甘いものを沢山食べる→過剰な糖や脂が吸収できずにもたれる→便秘や口内炎などの症状につながる→ちゃんとした栄養を摂っていないので「気血」が造られずエネルギー不足=疲れる
という悪循環です。
胃の弱い方は意識して消化がよいもの、温かいものを選ぶようにしましょう。
そして身体だけでなく、湿気は心にも影響を与えると考えられていますので、この時期は気分が晴れなかったり、思い悩み、落ち込みやすくなる傾向がありますが
自分なりにリラックスできることをしたり
体の巡りを良くし
上手に季節と付き合っていきたいですね。
疲れはこまめにリセットしてあげてくださいね。

ご予約はこちらから💁♀️⬇️
5月31日 5年を振り返って
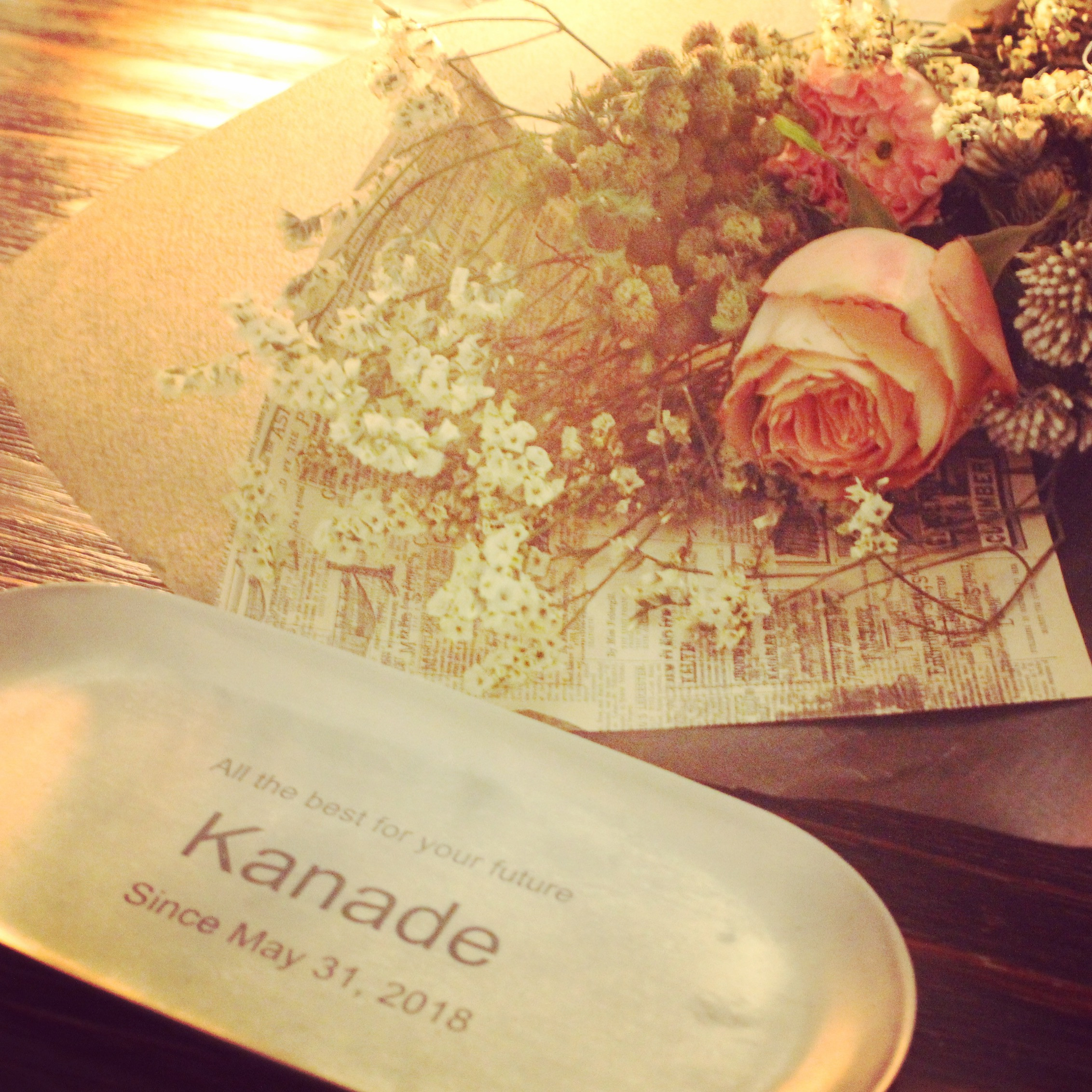
2018年5/31に奏をオープンして、早いもので5年か経ちました。
今年から奏とは別に新しいことも始め、少し新鮮な気持ちでもあります。
無我夢中の5年、
自由にやっていますが、それなりに色々とあり
流れに身を任せるということも覚えました^^;
コロナはなかなかキツかったですね…
そして
去年の今頃からのこの1年はとても意味のある1年でした。
だけど、苦労や大きな悲しみを乗り越えて
はじめてわかること、感謝できることがある
そんな風に思います。
サロンの名前を決めるとき、奏の前後に「・」をつけたのですが
画数的にもありますが
「点と点が繋がる」
そんな意味と、
「美しく奏でる音楽のように心と体を調律する」…そんな想いがありました。
整体師になって10年、
「整体」とは何なのだろう?とずっと考えています。
体の痛みやコリをほぐす
ただそれだけではなく
本当の意味での体を整える(整体)ということは
目には見えない「こころ」も必ず繋がっています。
コンディショニングという言葉があり
本来は競技でより良いパフォーマンスを行うために調子を整えるという意味でスポーツ界を中心に使われていますが
コンディションを整えるには体力・精神・技術・医療・栄養・環境の面からの総合的なアプローチによるコントロールが必要だからです。
コロナ禍の数年の間で
不安や孤独…それまで以上に皆が心と向き合うことになったのかもしれません。
体が元気なことも大切ですが
心が元気だったら、たいてい何とかなるものです。
そして、人のことはコントロールしたり
変えることはできないけれど
自分の体、心、考え方や人生は
変えようとすれば、変えることができると信じてい
ます。
私自身がそうでした。
整体と出会い
たくさんのお客様や人と出会い
大好きな施術をすることができて
本当にありがたいと心から思います。
これからの私は
今までよりももっと深い意味での整体が
できたらと思っています。
去年、いつか言おうと思っていた
感謝の言葉をもう二度と会うことも伝えることもできないという経験をし
だからこそ、これからは自分ができることを
精一杯、心を込めて
やって生きて行こうと決めました。
ここまでやってこられたのは、ひとえに皆様のおかげです。
いつも支えて頂き、本当にありがとうございます。
少しでも心と体がホッと休まるサロンであれたらと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願い致します。
2023年5月31日・奏・いずみ
胸を開く

スマホを見たり、パソコンに向かっているとき、背中が丸まって胸が閉じていませんか?
日常生活で私たちは胸を閉じるような姿勢をとりがちです。
すると胸や鎖骨周りが固まってガチガチになって、肩が内側に入ります。
こうして姿勢が悪くなると
肩がこり、呼吸が浅くなるだけでなく
心がふさぎがちになって
心を開けなかったり
考えていること、感じていることを
ちゃんと表現できなかったり…
そして
不安や心配が続くと
胸が閉じて、息苦しくなり、
咳が出たりします。
「胸襟(きょうきん)をひらく」
という言葉があります。
思っていることを打ち明ける、
心を開く
そんな意味で使われていますが
胸を開くことで、
姿勢を整えるだけでなく、呼吸が深く体の中に入ってくる感覚を味わうことができたり
胸に溜まっているネガティブな感情や不安な気持ちを開放し、心も軽く前向きにしてくれます○
🍀胸を開くセルフケアストレッチ
厚めのバスタオルをこのようにします
・仰向けに寝る
・腰の下に丸めたタオル首を後ろに曲げ、肩甲骨を浮かせる
この胸を開いた状態で大きく深呼吸をします。
普通の生活では、胸を開く動作は少なく、最初は違和を感じるかもしれませんが、首や肩周りの筋肉のストレッチにもなります。
心と体、つながっていますが
まずは体が先。
胸を開くことは
心を開くことにもつながります。
ちょっと
不安でソワソワしたり、
ふさぎこんだり
思考がいっぱいの時
敢えて胸を開いてみてください。
胸まわりが硬くなって呼吸が浅いと感じる方は
鎖骨周りを緩めてあげると
呼吸が深くできるようになります。
呼吸の浅さ、胸の硬さご相談ください◡̈

ご予約はこちら💁♀️⬇️

