♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ
整体とアロマトリートメント

肌寒いこの季節になるとアロマトリートメントがジワジワと人気です。
アロママッサージが大好きで、
いろんなお店で受けたことがある方と
アロママッサージ未経験の方と
結構ふたつに分かれる気がします。
実はアロマの施術も大好きな私。
今日は整体とアロマの違いやメリットについてです。
ざっくり言うと
整体は「圧す」
アロマは「流す」イメージで
刺激の方向性が違います。
整体は、コリに真っ直ぐに力が伝わり、
オイルは波のように横へ力が継続的に流れます。
🔹整体のメリット
1. 血行を良くして、代謝、自然治癒力を上げる。
2. 深い部分の筋肉をしっかり解せる。
3. 手軽に受けられる。
4. ストレッチなどでバランスを整える。
5. 強い圧が入れられる。
とにかくガチガチで身体が、重い、痛い、辛い、という方にお勧めです。
🔹アロマトリートメントのメリット
1. 血行を良くして代謝、自然治癒力を上げる。
2. 精油の香りで癒し効果がある
3. オイルの成分が肌から吸収して様々な効果がある
4. 手の体温と摩擦で、整体よりもむくみが取りやすい。
アロマは精油を塗ることで、成分を肌から吸収し、血液やリンパなど内側にまで効果が浸透します。
また精油の香りによって脳や呼吸器にも影響を与え、ホルモンバランスを整えたり心を落ち着けてリラックスさせる効果などかあります。
精油とは
エッセンシャルオイルとも言われ、自然植物の花や葉、木部、果皮、樹皮、根、種子などの部分に存在する天然の液体でその植物そのものの成分が凝縮されています。
天然純度100%のものだけが「エッセンシャルオイル(精油)」と呼ばれ、何かが混ざっていたり、植物の香りに似せて作られたものとは明確に区別されます
精油の作用 - 心や体のバランスを整える
心や体への作用
- 鎮静作用:こころと体を鎮静し、リラックスさせる作用
- 鎮痛作用:各種の痛みをやわらげる作用
- 鎮痙作用:筋肉の緊張を緩める作用
- 消化・食欲増進作用:胃腸の消化活動を高めたり、食欲をます作用
- ホルモン調整作用:ホルモンの分泌を調整する作用
- 刺激作用:こころや体を刺激して、元気にする作用
- 強壮作用:身体各部、全身の働きを高める作用
- 免疫賦活作用:免疫力を高める作用
- 利尿作用:尿の排泄を促進する作用
アロマの吸収経路は3種類
①「鼻から脳へ」鼻で香りを感じることで、脳まで届き、ホルモンの分泌を促したり、免疫力をアップさせたりします。
②「鼻から肺へ」吸い込む空気に含まれる香りの成分が、肺・血管を通して身体中に運ばれます。
③「肌から毛細血管へ」肌に触れた香りの成分は、毛細血管に吸収され血液に乗り、身体の各組織・各器官へと運ばれて働きます。
奏のアロマトリートメントは
私がもともと指圧ベースの手技から始めた為
指圧の要素も入れながらの施術です。
意外にも男性のお客様も多いです。
・精神的なストレスが多くリラックスしたい
・血流が悪く冷えやむくみが気になる
方には
アロマもオススメです。
最近は個人的にどっぷり精油にハマっている為、精油も飲むことができるほどのものを使用しています★
がっつり、ガチガチな体を解されたい方も
心身ともにリラックスしたい方も
ご相談ください◟̆◞̆
ご予約はこちらから💁♀️
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
頭蓋骨を緩めて肩こり、腰痛、頭痛解消

長年悩んでいる肩こりや腰痛、頭痛。
患部を押したりもんでも改善しないのは
その痛みが「頭蓋骨のゆがみ」から来ている場合があります。
そして
その「頭蓋骨のゆがみ」は
根本的な原因は「姿勢の悪さ」です。
デスクワークなどでいわゆる前傾姿勢を長時間続けると、相続よりはるかに首や肩の筋肉に負担がかかっています。
人の頭の重さは、約4~5㎏。
ボウリング球と同じくらいの重さを
体の最上部に置いて日々生活しています。
頭部を全身で支えるときにポイントとなるのは「骨盤」です。
骨盤の向き、角度によって頭の位置が決まるからです。
長時間座り続けていると、骨盤は徐々に後ろに傾き、尾骨が前方に入り込むように骨盤が後傾すると、腰が曲がり、背骨はゆがみ始めます。
すると首が前に出て、頭蓋骨はあごを突き出す角度となり、
この状態だと頭には最大5倍以上、27㎏ほどの負荷がかかります。
首と肩でこんな重さを支えようとするので
頭痛、めまい、肩こりなどの症状が引き起こされてしまうのです。
また
全身からの情報は脳でキャッチされ、脳から全身へ指令を出し、私たちの体は正常に動いています。
その情報の受け渡しに必要なのが「脳脊髄液」です。
脳、脳脊髄液、頭蓋骨は全身と強いつながりがあり
頭蓋骨がゆがんで脳脊髄液の量が減ったり、循環が悪くなったりすると、頭痛やめまい、首の痛み、耳鳴り、視力低下、倦怠感などの症状にもつながります。
まずは
・姿勢を正しくすること
・頭蓋骨を緩めること
が解消のカギになります。
骨盤をきちんと立てたよい姿勢を保つことが大切です→詳しく、https://izumi-kanade.com/info/3283411
🌿手軽で簡単なセルフケアは
「前頭筋(おでこ)ほぐし」
前頭筋は考え事の多い方や目の疲れから凝りやすいといわれています。
・テーブルに肘をついて手のひらでおでこを包みます。大きく円をかいてほぐすだけ。
手のひらに頭を乗せる感じにして首頭の力を抜くのがポイントです。
おでこ全体をくまなく、ほぐします。
ヘッドマッサージは頭皮が温まり、血流改善にもなり、頭蓋骨を覆う骨膜がほぐれ、首周りの疲労も取れます。
後頭部の頭と首のつなぎ目周辺、
表情筋と頭蓋骨のつなぎ目あたり=こめかみの側頭筋の周辺は
頭の疲労回復ポイントです。
この辺を手のひらでグルグルマッサージするのもオススメです。
でもやっぱり頭のマッサージは人にやってもらうのが1番…
ヘッドマッサージでリラックスすると脳疲労やストレスが解消され、
脳に余力が生まれ、ヒラメキが起きたり
仕事がはかどったり、集中力が上がったりするかもしれません◡̈
ヘッドマッサージは120分クーポン、指圧、アロマなどのコース内で組み合わせ自由です★
頭の疲れ、リセットしませんか?
📱24時間オンライン予約
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
直前や夜間でも、返信を待たずに予約できます★✉️の行き違い防止の為、オンライン予約をご利用頂けると大変助かります。
**************************
マッサージ整体・奏・kanade アクセスバーズ東京青山表参道
表参道駅2分
指圧ベースの整体マッサージ、ドライヘッドスパ、リフレクソロジー、ストレッチ、アロマトリートメント
…夜遅くまで営業★男性も歓迎★
免疫アップの為にも血流改善しましょう✨
こころの不調は気の乱れから?

日々のストレス、不規則な生活リズム、運動不足、さわしなさ...
様々なことからイライラやクヨクヨなど気分の落ち込みを感じたりというメンタルのプチ不調。
「性格」ではなく“気の乱れ”から来ているかもしれません。
🔹身体からくる心
東洋医学の考え方のひとつに「気血水(きけつすい)」という概念があります。
体内には「気・血・水」の3つの要素があり、それらの正常な働きによって臓器や各組織が正常に動き、心身の活動が営まれるという考え方です。
「気」:生命活動のエネルギー。血や水を動かし、自律神経系・内分泌系に関わる。
「血」:体内のいわゆる血液。
全身に酸素や栄養を運んだり、ホルモンバランスを調整する。
「水」:リンパ液や汗、尿、鼻水など、血液以外の体液。免疫力に関係する。
これら3つが満たされて、体内を過不足なく、スムーズに循環している状態を“健康”と捉えます。
🔹気の乱れ
気虚(ききょ):元気がない・うつ・食欲低下・下痢と便秘の反復・夕方のにぶい頭痛・むくみ・浮遊性めまい、風邪をひきやすい、考えてもしょうがないことを考え続けるなど
気滞(きたい):喉がつまる・呼吸がしにくい・お腹がはる・ガスがたまる、ため息が多い、不安・焦燥が強いなど。
「気」は「元気」や「やる気」の気です。
川に例えると気の量は「川の水」の量で
気の量が多く元気であれば、川の流れはスムーズで、川(体)に流れ込んできた嫌なことも病原体も、すぐに体外へ排出してしまうので、ストレスもたまらず病気にもなりにくくなります。
逆に量が少なくなり勢いがなくなると、
悪いものが身体に溜まって、流れは停滞し、
不安が強くなるのも特徴です。
これが健康だけでなく「運気」にも関わってくるとか…
四季の移り変わりや環境の変化、生活習慣・食習慣の乱れ、ストレスなど、バランスが乱れる理由はひとつではありません。
気の乱れを整える方法はシンプル!
・深呼吸で自律神経のバランスを整える。
・自分なりのストレス解消法を見つける
呼吸についてはhttps://izumi-kanade.com/info/3198909
自分なりのストレス解消法…
案外深く考えたことがない方もいるかもしれません。
今年はリフレッシュするにも制限がある中
いかに
「手軽」に「時間をかけず」「簡単に」
できることをリフレッシュやリラックス方として取り入れることが大切です。
運動、入浴、香りの良いアロマやお香、
音楽、瞑想など…
からだもこころも
それを本当に調整できるの自分自身であり、
「自分を大切にする」「自分をケアする」
ことが、こらからより重要になっていくのではないでしょうか。
忙しい毎日の中でも気軽にできる心地よいセルフケアで気の巡りを整え心身とも健康を目指したいですね。
巡りが気になる方もご相談ください◡̈
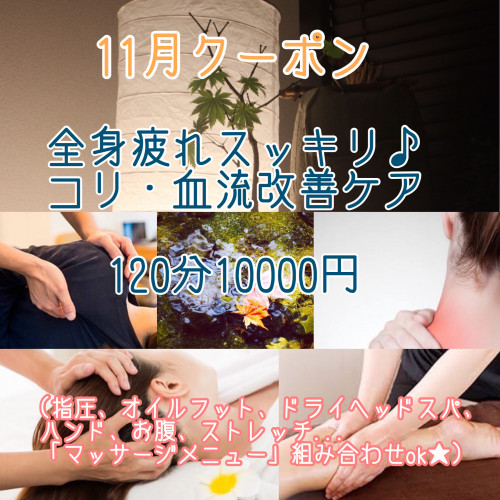
ご予約はこちらから💁♀️🔽
📱24時間オンライン予約
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
直前や夜間でも、返信を待たずに予約できます★✉️の行き違い防止の為、オンライン予約をご利用頂けると大変助かります。
**************************
マッサージ整体・奏・kanade アクセスバーズ東京青山表参道
表参道駅2分
指圧ベースの整体マッサージ、ドライヘッドスパ、リフレクソロジー、ストレッチ、アロマトリートメント
…夜遅くまで営業★男性も歓迎★
その疲れ…寒暖差疲労!?

朝晩の冷え込みが厳しくなってきましたが、
11月は、1年のうちでも気温の変化が激しく、
体調を崩す人が増える時期でもあり
寒暖差が激しくなと「なんだかいつもより疲れている気がする」と感じる方が増える傾向にあります。
だるい、眠れない、食欲がない…
秋に起こるこの症状は「寒暖差疲労」なんて言われます。
🔹寒暖差疲労のメカニズム
人間の体は寒ければ温かく、
温かければ熱を冷まそうとします。
気温差が激しいと
頻繁に熱をつくったり、逃がしたりするため、身体はより多くのエネルギーを必要になります。
熱をつくったり、熱を逃がしたりするのに
関係しているのは自律神経系です。
交感神経と副交感神経を上手に切り替えて、暑い環境にも寒い環境にも適応できるように体温調節をしますが
しょっちゅう温度に変化があると、自律神経がオーバーワーク状態にになってしまい、交感神経と副交感神経がバランス良く切り替えにくくなります。
この急激な自律神経系の切り替えは、自律神経を疲労させます。
さらに寒暖差疲労に拍車を掛けるのが
PCやスマートフォン
同じ姿勢を長時間とることで、骨格がゆがみ、自律神経を出す信号が通る背骨にゆがみが生じてしまい、自律神経がうまく機能しなくなります。
すると
身体の冷え、めまい、頭痛、肩こり、顔のほてり、冷えに関しては特に手足など四肢の末端が冷えやすくなります。
メンタル面では
食欲がなくなる、睡眠障害(眠れない、夜中に目が覚める、朝早く目が覚める)、イライラする、落ち込みやすくなるなど
様々な影響が出ます。
🔹寒暖差疲労対策
なるべく常に身体を温かい状態に保ち、寒さを感じにくくすることです=温活
身体が感じる温度が安定していれば、体温調整のためのエネルギーを使わないので
自律神経の機能が低下しにくくなります。
🌿ポイント1
首元を温める
首には自律神経に関わる大切な役割を果たしているのと、太い血管が通っていることから重要な部位です。
首が冷えると自律神経は緊張状態になります。寒さや冷えを感じたときは首をあたためることが効果的です。
蒸しタオルなどを使い首を温めましょう。
蒸気温熱は体に多くの熱を伝え、皮膚を深く広く温めることができます。
また手首、足首など首がつく部位を温めること温まった血液を全身に効率よく回すことができます。
🌿ポイント2
軽い運動
ストレッチや散歩などの軽い運動は血液の循環を良くします。
散歩や入浴後にストレッチをするなど生活の中に軽い運動を取り入れてみましょう。
そして寒暖差疲労以外の疲労を軽減すること
も大切です。
例えば体が凝って、筋肉が硬くなると
本来負荷がかからない箇所に大きな負担かかかり、疲労がたまってしまいます。
まずは筋肉をほぐすこと
そして血流を良くすることで疲労感の軽減になります。
秋の不調でお悩みの方はご相談ください◟̆◞̆
ご予約はこちらから💁♀️🔽
📱24時間オンライン予約
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
直前や夜間でも、返信を待たずに予約できます★✉️の行き違い防止の為、オンライン予約をご利用頂けると大変助かります。
**************************
マッサージ整体・奏・kanade アクセスバーズ東京青山表参道
表参道駅2分
指圧ベースの整体マッサージ、ドライヘッドスパ、リフレクソロジー、ストレッチ、アロマトリートメント
…夜遅くまで営業★男性も歓迎★
免疫アップの為にも血流改善しましょう✨
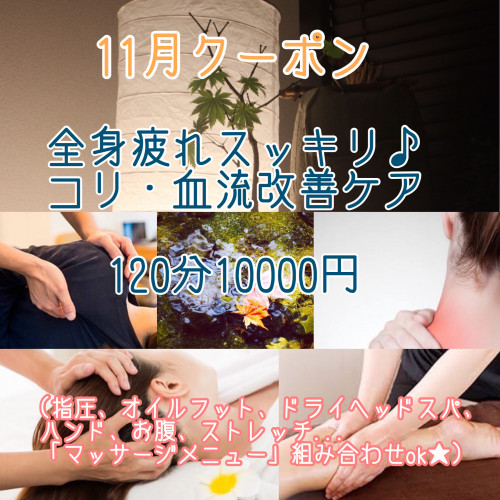
****🍂11月クーポン🍂*****
【全身スッキリ♪コリ・血流改善ケア120分 ¥10000】
(指圧、オイルフット、ドライヘッドスパ、お顔、お腹、ハンド、ストレッチ組み合わせ自由)
おひとりおひとり、その時その時の
お身体の状態に合わせた施術とご自宅でのセルフケアやストレッチなどもお伝えできればと思います。**************************
潜在意識と健康

私が最近、興味があることと言えば
もっぱら「潜在意識」についてです。
潜在意識という言葉、最近よく聞くようになりましたが
願望実現的なことだけでなく健康、痛みなどにも深く関係しています。
🔹潜在意識とは、
過去の経験などによって無意識のうちに蓄積された価値観、習慣、"思い込み"からつくられた
「自覚されていない意識」
呼吸などの生命維持・条件反射・習慣など
簡単にいうと「無意識」にやっていること
「本当の気持ち」や「心の底から信じていること」なので
本能のままに行動する時に
影響を及ぼしていて
自分でコントロールをすることが
できません。
逆に
🔹反対の顕在意識は
意識することができる部分で
思考をしたり、物事を判断したり、
何かを思い出すなど…
自分でコントロールできます。
実は私たちの意識のほとんどは
潜在意識に支配され、
顕在意識 の部分が 3~5%
残りの95%以上が潜在意識
言い方を変えると、
潜在意識が人生に大きな影響を与えています。
痛みを例にすると
腰痛があるとき
当然『治って早く楽になりたい』と思います。
でも
すぐに戻ってしまう
なかなか治らない
色んな所に行っても治らないのは
顕在意識では「治りたい」と思っているけど
潜在意識の方では違うことを意識してしまっているんです!!
例えば
・忙しいから時間がない
・通うのがめんどくさい
・慢性的だから治らない
・誰にやってもらっても無駄だ
のような事を潜在意識が考えています。
そんなはずはない!と顕在意識が思っていたとしても、潜在意識は思っているんです。
じゃあどうすればいいの?
潜在意識は「否定語」が理解できません。
たとえは
『〇〇(嫌いなもの)は食べたくない』と考えたとすると
潜在意識は
『〇〇(嫌いなもの)』と『食べ』に反応し、
勝手に
『〇〇を食べる』という現実を作ります。
目の前に現れる
『たくない』方は認識はされません。
"心配事が叶ってしまう"方は
「好きなものを食べたい」
という思考より
「嫌いなものを食べたくない」
という思考回路が強いのです。
この思い込みや潜在意識を変えるために
1番大切なことは
「自分が使っている言葉を変える」ことです。
潜在意識は言葉の
否定語が区別できないうえ、
「他人と自分」も区別できないと言われます。
他人に向けられた言葉も自分に向けられた言葉も同じように自分に作用し
心の中で話す言葉も口に出して発声する言葉も同じです。
ネガティブな言葉を自分や他人に使えばネガティブを
逆に、ポジティブな言葉を使えば、ポジティブなことを自分に与えていきます。
それが「言霊」と言われるものです。
話が長くなりましたが
「雨が降らなければいいな」と思うのと
「お天気になるといいな」と思うこと、
「病気になりたくない!」と思うのと
「健康でありたい」と思うのとでは
同じようで、全然違うのです。
まずは言葉を変えてみることで
体の状態までも変わってくるかもしれません。
ご予約はこちらから💁♀️
直前や夜間でも、返信を待たずに予約できます★✉️の行き違い防止の為、オンライン予約をご利用頂けると大変助かります。
📱24時間オンライン予約
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
**************************
マッサージ整体・奏・kanade アクセスバーズ東京青山表参道
表参道駅2分
指圧ベースの整体マッサージ、ドライヘッドスパ、リフレクソロジー、ストレッチ、アロマトリートメント
…夜遅くまで営業★男性も歓迎★
免疫アップの為にも血流改善しましょう✨
****🍂11月クーポン🍂*****
【全身スッキリ♪コリ・血流改善ケア120分 ¥10000】
(指圧、オイルフット、ドライヘッドスパ、お顔、お腹、ハンド、ストレッチ組み合わせ自由)
おひとりおひとり、その時その時の
お身体の状態に合わせた施術とご自宅でのセルフケアやストレッチなどもお伝えできればと思います。**************************




