♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ
なぜ体が「こわばる」のか

寒くなったのもあり、最近は体が「こわばっている」方が多く見られます。
そもそも「体のこわばり」とはどんな状態なのかというと
医学的にはこわばり=「筋緊張の亢進(こうしん)」といいます。
筋肉は、例えるとゴムのように弾性があり、適度に伸びたり縮んだりして「筋力」を発揮します。
この「筋力」は、人が重力に抗して姿勢を維持したり、運動したりする際にすぐに活動するために必要なものです。
筋肉が伸びきった状態では弾性がなく、適度な張力を瞬時に発揮することができませんが
硬すぎてもいけません。
適度なテンション(張力)が保たれた筋肉の状態を「筋緊張」といい
使っていない時には緩んでいる弛緩(しかん)状態にあります。
本来は緊張と弛緩が繰り返されるのですが
常に身体に力が入った状態の緊張状態が続くと、弛緩状態が得られず筋肉のいわゆる「コリ」に繋がっていってしまいます。
なぜ緊張状態が続いてしまうのかは
- 姿勢
- 精神状態
が大きく影響するからです。
腰痛や肩が凝りやすい人は、精神的に緊張しやすい性格であったり、肩と腕に負担がかかりやすい姿勢を日常的に続けていたりすることが多いです。
原因となる姿勢や生活習慣、ストレス源を減らすことが肩こりや腰痛を改善するための一番の近道ですが
まずできること、変えることは
「呼吸」です。
★こわばった体を弛緩させる呼吸★
・楽な姿勢で座り、背骨を伸ばしましょう。
・ゆっくりと深呼吸を行い、できるだけ上半身の力を抜いて、できるだけ脳をのんびりと休め、次に息を60%ほど吸い込んだら、ゆっくりと息を止め、鼻をつまんでも構いません。
・喉、首、顔をリラックスさせ、からだの内側で起きるすべての出来事、湧き起こる感覚に意識をむけます。
・少し息苦しくなってきたら、少し息を止めたままキープしゆっくりと吐いて、深呼吸を5回ほど繰り返し、味わいます。
・その間、からだの内側で起きる感覚を優しく味わっておきます。
何かとバタバタしたり、考えることが多かったり
思い悩んだりと
常に体が緊張状態になっていないでしょうか?
1日一回、なるべく眠る前に弛緩する時間を
意識的に作ってあげてくださいね。
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
秒速5センチメートルでリラックス

触れるという感覚である「触覚」には、様々な種類があります。
質感を識別したり、動きを感知したり、
温度や痛みを感知したり...
全身を覆う皮膚には、外界の刺激から身体の内部を守るだけでなく、何かが触れたときに反応する感覚器としての役割があります。
これを “皮膚感覚”あるいは“表在感覚”といい
そして、この皮膚感覚は、触覚や痛覚、温度覚などから成り立っています。
近年、「C触覚線維」という神経が発見され、
毛根にからみつくように線維が伸びており、皮膚表面をさするときに生じる毛の振動を感知し、刺激を脳に伝える役割があります。
そのため触覚によって快や不快、安心感や嫌悪感といった感情を喚起させるという不思議な特徴を持ちます。
そして、脳をリラックスさせる働きを持ちます。
触覚のC繊維が使われると、脳の意識や感情に関係する、脳の島皮質が活発になります。
また、副交感神経が活性化しリラックス反応が得られます。
このC繊維を使う条件は、
「柔らかいこととゆっくりであること」
柔らかい素材に触れていると、C繊維が使われます。
手触りのよいものに触れていると、気持ちがリラックスする、というのは経験したことがあると思いまが
神経には、髄鞘(ずいしょう)と呼ばれる、
電線を包み込む層があるものとないものがあります。
髄鞘がある神経は有髄繊維、
ない神経は無髄繊維といいます。
髄鞘があると、神経は情報の伝達が飛躍的に速くなるので、有髄繊維は情報を速く伝え、
無髄繊維はゆっくり伝えます。
C繊維は無髄繊維です。
情報をゆっくり伝えるので、
ゆっくりとした刺激によって使われます。
ゆっくりとは、具体的には秒速5cmくらい
さらにC繊維が使われると、信頼や愛情をつくるオキシトシンも分泌され
オキシトシンは、脳内ではセロトニンを活性化します。セロトニンは、不安や緊張を緩和し、脳の働きを安定させます。
つまりゆっくり触れる、触れられることによる皮膚への刺激は、手の密着や圧迫、手の温かさ、触れられている位置、なでる速度などが、神経の働きをとおして脳に伝わり、自律神経系、内分泌系、免疫系に影響を及ぼし全身に作用します。
そして、その刺激を心地よいと感じることによって、不安の緩和、孤独からの解放、安心感の獲得、自尊心の回復など、情動面によい影響をもたらすそうです。
ちょっと疲れているとき、
秒速5cm
ご自分の腕を撫でて試してみてください◟̆◞̆
ご予約はこちらから💁♀️🔽
ヒートショックプロテイン効果

海外からは「日本人の肌は、きめ細やかで美しい」と賞賛されるといいます。
それは、日本人は昔からお風呂文化があり湯船に浸かり、体に熱を加える(刺激を与える)ことが日常的にされていたから、ともいわれています。
あまり聞き慣れませんが
ヒートショックプロテインというものがあります。
ざっくり言うと
傷んだ細胞を修復する特徴を持った「タンパク質」で人間の細胞のなかに、もともとあるタンパク質の1つです。
体に熱による刺激が加わったとき、つまり体温の上昇するタイミングで作られる(増える)ことから、ヒートショック(熱ショック)という名前がつけられています。
しおれたレタスを約50℃のお湯に約2分間浸すと、HPSが増えて細胞が強化され、シャキッと新鮮さを取り戻す現象があります。
人間にも同様で、ヒートショックプロテインが出ると、細胞が修復され
その特徴を活かして、免疫力を高める、コラーゲンの生成を増やす、代謝を活発にする、といった健康や美容を促進する効果が期待と近年注目されています。
・日常生活での疲れを軽減
・病気の予防、回復をサポート
・ストレスを防ぐ
・炎症を防ぐ
・鬱の予防
・癌予防
ヒートショックプロテインを増加させる為には熱ストレスで深部体温を38度程度に上げること
なので
少し息がきれるくらいの運動、お風呂、サウナ、岩盤浴、よもぎ蒸しなどが効果的。
細胞は水分を除けば、ほとんどがタンパク質で できています。
ヒートショックプロテインはストレスなどにより細胞の中で増え、構造がおかしくなったタンパク質を修復して元気にしてくれる素晴らしい存在なのです。
日本人は昔から湯治という温泉を利用した治療法を行なってきましたが
このようなことを本能的に知っていたのかもしれません。
寒くなってくる時期、なるべくお風呂に浸かってしっかり身体を温めて寒さに負けない体に★
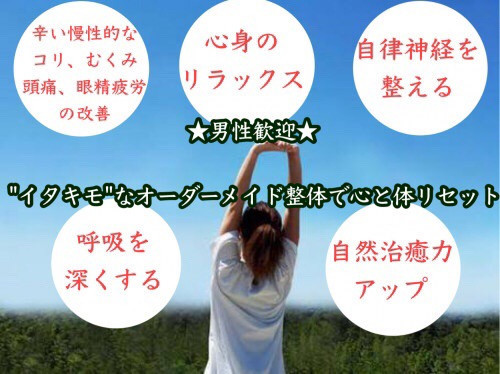
ご予約はこちらから💁♀️🔽
【皮膚】と脳、心、体

あらゆる機能を司る「脳」はとても大事な器官、そして脳と密接に関わりがある第2の脳は「腸」、さらには第3の脳は「皮膚」だといわれています。
生まれる前の母体で細胞分裂する際に脳と皮膚は同じルーツから生まれ、よく似た仕組みを持っていることから『第3の脳』と言われています。
お風呂で「あ~気持ちよいなあ」と感じたり、腹痛時に手でおなかをさすってもらうと「痛みが和らいだ」と感じたりするのは、実は体の表面の皮膚がキャッチしたものなのです。
また、人間の皮膚にはアドレナリンなどの脳内物質を感じとる受容体があるため、様々な感情を作り出す役割も担っています。
そもそも皮膚の役割とは1つが生命を維持するための「防御機能」もう1つが環境の変化を感知する「感覚機能」。
「防御機能」は体液の流出を防ぎ、体外からの異物侵入を防いでくれます。「感覚機能」は、周囲に起こった現象を知らせる機能で、何かを理解するためには不可欠な役割を果たしています。「鳥肌が立つ」などの表現はこの「感覚機能」がすくいとった現象であり、私たちの目には見えない情報を、皮膚は鋭く受け取ってくれているのです。
皮膚が『第3の脳』と言われる理由
「皮脳同根」という言葉があります。
皮膚と脳は同じルーツを持つために密接に繋がっていることを示した言葉です。確かに、ストレスがたまるといつもより肌荒れひどくなったりします。これはただの肌荒れではなく、心から出される危険信号ともいえるのです。
“直感”は、皮膚感覚から?
皮膚には、温かいとか痛いといった感覚をキャッチする神経が備わっていますが、これらの「五感」に加えて「心地よさ」「気持ちの悪さ」「怖さ」などの感覚も実は肌で感じているのです。
例えば「温泉に入ると、気持ちがよい」とか「触ってみたら気持ち悪かった」という感覚は、「皮膚が感じた感情」と言えます。こうして考えると、「鳥肌が立つ」「身の毛がよだつ」「温かい人、冷たい人」「肌が合う、肌が合わない」 など、皮膚感覚で感じた取った現象を表わした言葉が意外に多いですね。
皮膚は、目には見えない情報を受け取る感覚に優れていて、感情のアンテナのような役割を果たしているのかもしれません。
人間の皮膚には、「セロトニン」「ドーパミン」「アドレナリン」などの脳内物質を受け取る皮膚受容体があることから、いろいろなことを感じ取るのです。「セロトニン」は幸せや癒し、「ドーパミン」は快感や意欲、「アドレナリン」は活動的にしてくれる脳内物質であることから、正に「肌で感じて感情を作り出す」ということになります。
赤ちゃんをマッサージすると、赤ちゃんの表情はとても穏やかになり、安心感に満たされていきます。
これは、皮膚に備わった“快”を感じる神経によるもので、赤ちゃんの心が満たされるのはもちろん、脳や全身の発達を促す働きもあるのです。
私たち大人も頭が痛くなったり、肩がこったりすると、無意識に手で患部を押したり、もんだり、さすったりします。
マッサージをすると血行が促されますが、その理由は一酸化炭素という血管を広げる物質が出て、血管の中だけでなく皮膚表層の表皮細胞も一酸化炭素を放出します。
その結果毛細血管が拡張され、疲れを癒した上にリラックスした状態になるのです。
「肌に触れる事で脳に信号が伝わり、触れている筋肉をゆるめなさいと言う信号が脳から発する」とも言われています。
そしてもう一つは触れることによって
脳内から幸せホルモン=オキシトシンが放出されますがオキシトシンの効果というものは、ものすごいパワーがあるそうです。
皮膚はすごい力を持っています。
そしてマッサージの効果=筋肉に働きかけるだけではなく、実は心にも作用するのですね。
大切な皮膚、労ってあげてみてくださいね★
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
ストレスを感じる時、眠れない夜にほぐすべきところ…

ストレスを感じると眠りは浅くなります。
ストレスで眠りづらくなる一因は自律神経の乱れにあります。
自律神経は交感神経と副交感神経から成り、この2つが上手にバランスを取りながら機能していますが、ストレスによってバランスが乱れてしまうからです。
人は緊張状態にあるとき、体が強張ります。
これは活動モードのときに優位となる交感神経が働いているからであり、交感神経が優位になると、筋肉が収縮します。
つまりは日常的にストレスにさらされ、緊張状態にあると交感神経優位に傾きやすく、筋肉も強張りっぱなしで疲れやすく、眠りづらくってしまいます。
筋肉の収縮をもたらす交感神経とは反対に、リラックスモードのときに優位となる副交感神経の働きが眠気をもたらします。
自律神経の中枢は脳にあり、さらに脳は頭蓋、そして筋肉に覆われています。
その構成は、前頭筋、側頭筋、後頭筋、さらに頭頂部を広く覆っている帽状腱膜(ぼうじょうけんまく)と呼ばれる筋膜です。
また人は何かに集中すると歯を食いしばり、こめかみ周辺の筋肉に負荷がかかる傾向にあります。
頭の筋肉が凝り硬くなっているのは疲れている証拠でもあります。
緊張、不安、イライラ…そういった『心のコリ』は頭にダイレクトに表れ、
頭の凝り固まった筋肉をほぐすことで自律神経の中枢に働きかけ交感神経優位に傾いた状態を緩和することができます。
…とはいえ、自分でヘッドマッサージをする気にもなれない。という場合は
簡単なセルフケアで頭の筋肉をほぐす方法があります。
1.500mlペットボトルに45℃程度のぬるま湯を入れる。枕を外した状態で仰向けになり、首の後ろにペットボトルをセットする。
2.全身の力を抜き、4秒かけて息を吸い、6秒かけて吐くという深呼吸を3セット行う
3.次に左を向き、2と同様の深呼吸を3セット。さらに右向きでも3セット行う
4.首の後ろにセットしていたペットボトルを後頭部にずらし、首をゆっくり左右に振る動作を10往復ほど行う
6.最後に深呼吸をもう一度
副交感神経は首の後ろに集中するといわれ、筋肉は温めると弛緩する性質を持つため
ぬるま湯によって筋肉を温めつつ、効率的に首の後ろの筋肉をほぐすことができます。
それでも、やはり人に頭をマッサージされるのは
気持ちいいものです。
頭の筋肉は顔にも続いているので、表情も明るくなり、気になるお顔のたるみにも効果的です。
頭の疲れ、コリ…ご相談ください。
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku

