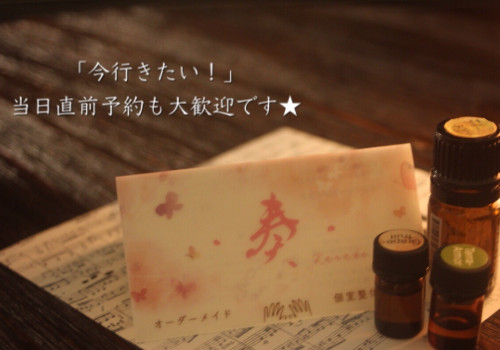♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ
ゆるめる

毎日のお仕事や生活の中で
いろいろな「出来事」があります。
誰でも
楽しい事やワクワクすることもあれば
「ストレス」を感じることもあると思います。
感じている"ストレス"はいったい何なのか?って考えたことがあるでしょうか?
ストレスを感じると体には何が起きてる?
ストレスを感じると
まず自律神経の働きを司る「視床下部」に信号が送られ、交感神経を緊張させます。
次に視床下部から「脳下垂体」へ指令が出され、
腎臓近くにある「副腎髄質」へと信号が送られます。
副腎髄質は、「アドレナリン」を分泌します。
「アドレナリン」は肝臓のグリコーゲンの分解を促して、
血糖値を上昇させ、全身の交感神経を緊張させます。
「ストレスを感じる」とい
ストレス=感情だと思いがちですが
「嫌な感じ」や「イライラ」「怒り」「不安」などの感情を伴うので
ストレスって感情じゃないの?と思うかもしれませんが
実はストレスは身体の生理学的な反応です。
その生理学的反応が感情をうみだします。
生理学的反応は、「闘う」「逃げる」「固まる」の3つの本能的な反応です。
感情は防衛反応なのです。
ストレスを感じるときというのは、ストレスの原因に対応するために、身体では交感神経が活性化して、血管を収縮させて血圧や心拍数を上げ、興奮させることで「闘う」「逃げる」ために必要なエネルギーが生み出されます。
一方、休息しているとき、眠っているとき、リラックスしているときは、副交感神経が働いています。
ストレスと上手に向き合うために
私たちは日頃いろいろなものを
背負って生きています。
これを しなければならない
あれも しなければならない
こうあっては ならない
など。
だけど
社会では必ずしも、自分のやりたいことだけをできるわけではありませんが
「こうしなきゃいけない」ではなく
できるだけ
「こうしたい」と思うことを選択すること。
したいこと、好きなことをする時の
感情「ワクワク」にはすごいパワーがあります。
わくわく脳は
アドレナリンやドーパミン、エンドルフィンなど脳を活性化させる神経伝達物質が出て、エネルギーがあふれ出します。
そしてもうひとつ大切なことは
「自分を整えしっかりと休息と栄養をとる」こと。
自分を整えることとは
バランスの良い食事や睡眠をとり
心身のバランスをとること。
体だけが健康
心だけが健康
ということはないのです。
ストレスを感じている時は
体が無意識に緊張して、構えています。
体を緩めるために
最初にやるべきことは
息を吐きながら力を抜く。
深い呼吸です。
「ゆるめる」という意識をしながら
体中をゆるめると
心の中をゆるめることにつながります。
普段頑張っている人ほど
力を抜くのが苦手だったり、力の抜き方がわからないかもしれません。
心地良い場所、好きな音楽、美味しい食べ物、一緒にいて心地良い人と…
"するべきこと"ではなく
「ワクワク」することに目をむけて
心も体も少しゆるむかもしれません☺️
太ももの筋肉が腰痛の原因?

「腰が痛い....」
その原因は
ウエスト周りや背中が硬くなっているからだと思いがちですが、
実は意外にも痛い場所ではなく、
別の場所が硬いことが原因だったりします。
デスクワークが多い方が
お尻と並んで硬くなるところは
「太もも」
太もも=ハムストリング
が硬いことを"タイトハム"と言ったりします。
腰を下から支えているのがお尻と太もも。
重力から体を支える役割してるので常に負担がかかり、腰の痛みの原因になります。
タイトハムによって股関節や膝関節の動きが悪くなり可動域が狭まり、結果腰への負担が大きくなるからです。
これにもタイプがあり、ふだんの姿勢によって、太ももの前・後ろの筋肉、どっちが硬くなっているかが分かります。
前後どちらが硬くなっている?
1.前屈(前に倒す)が苦手な人
→タイトハム派
お尻の大臀筋と太ももの後ろの筋肉が硬くなっている
筋肉の性質は、使わないところは短縮して硬くなってしまいます。
そのため、猫背姿勢で座っていたり、床にだらりと伸びた座位姿勢でいることで、常にハムストリングが短縮した状態でいることで、ハムストリングは硬くなっていきます。
2.後屈(体を反る)のが苦手な人
→反り腰派
腸腰筋というお腹付近と、太ももの前の筋肉が硬くなっている
筋力の低下で腹筋など「体の前側の筋肉」と、姿勢を支えるべき「体の後ろ側の筋肉」のバランスの崩れが反り腰の原因となります。
太ももの硬さは腰痛だけでなく
「ぽっこりお腹」や「むくみ」にもつながってしまうのです。
太ももの筋肉を緩めるには
まずはストレッチ!!
寝ながらストレッチで太ももを伸ばす
1. 手脚を伸ばして仰向けに寝る。
2. 右脚の膝を胸に近づけるイメージでゆっくりと引き寄せる。
3. 胸に近づけられたら膝を両手で抱える。
4. 無理のない位置で20~30秒キープ。
5. 両手を放しゆっくりと1の状態に戻る。
6. 左脚も同じように2~5を繰り返す。
太ももの筋肉は硬くなっていてもあまり自覚が出ない場所です。
ふくらはぎを揉んでもとれない"むくみ"は意外と太ももの筋肉の硬さが原因の場合も。血液やリンパの通り道が硬くなって塞がっていると、流れが悪くなってしまうのです。
奏では太ももの筋肉もしっかりほぐします★
太ももの筋肉は張りが強いとくすぐったかったり、圧がかかかりにくいのですが
裏技は
「横向き施術」
横向きにで行うことにより、あらゆる角度からアプローチできるので、圧が程よくかかります。
そして太ももやお尻の筋肉は仰向けでのストレッチでしっかり伸ばします。
腰が痛い、重だるい方は
太ももの筋肉を意識してみてくださいね。
 予約はこちらから💁♀️
予約はこちらから💁♀️
隠れた名脇役?!菱形筋とは?

頭痛や耳鳴り、肩こり、眼精疲労、不眠、などさまざまな不調の原因は、実は首にあるとも言われます。
そしてその首を支える筋肉、僧帽筋や肩甲挙筋、菱形筋が大事な働きをしています。
中でもあまり知られていない「菱形筋」(りょうけいきん)
は地味に大切な働きをしてくれています!!
菱形筋は首の付け根から下にある筋肉で、名前の通り菱形のようになっています。
菱形筋は菱形筋は、肩甲骨と脊柱をつなぎ、
左右の肩甲骨を背骨へ寄せ、
簡単にいうと「胸を張る」ための筋肉です。
そして菱形筋は肩甲骨を安定させる
「姿勢」に関係する筋肉です。
菱形筋が硬くなると骨の位置が広がるため
・猫背になる
・呼吸が浅くなる
などの原因に。。
菱形筋をほぐすには?
慢性的なコリは肩甲骨の下部と菱形筋のあいだあたりにあることも多いのですが、
菱形筋は深層にあるため、マッサージだけではほぐれにくい筋肉です。
この菱形筋を緩めるためには
ストレッチ+奥に届く指圧が有効的。
硬く短くなった菱形筋を伸ばして可動域を広げながら、余計な緊張を取り払ってくれるのがストレッチです。
セルフで菱形筋ストレッチ
1肩幅程度に足を広げて立ちます
2手を前で組んで、膝を曲げながら、背中を曲げ、肩甲骨を広げていきます
3頭を手の中に入れるイメージで曲げていきます
4菱形筋が伸びていると感じる体勢をキープします
5息を吐きながら30秒程度行いましょう
そして一番有効なのは
「肩甲骨はがし」。
肩甲骨はがしは、マッサージだけでは届かない深い部分にある固まった筋肉をほぐして血流を促進し、姿勢のゆがみの改善にも…
私は新人の頃、指圧下手だった為、とにかくストレッチを極めよう研究を重ねた為、「肩甲骨はがし」が得意で大好きです♡
今まで聞き慣れなかった「菱形筋」がほぐれると肩の可動域があがり
肩こり、首コリが緩和されるかもしれません☺️
予約はこちらから💁♀️
脳脊髄液の働きと脳脊髄液とは

人間の身体の働きを支配しているのは脳。
脳が正常に機能することはとても大切です。
そしてあまり聞き慣れない言葉ですが
その脳の周りを覆っている液体を
「脳脊髄液」といいます。
脳脊髄液は、栄養を運んだり脳神経の調子を整えたりと、体の健康状態を司っていると言っても過言ではないのです。
脳の内部や、脳と頭蓋骨のすき間を流れている透明な液体で、なんとその正体は、私達の体中を流れている血液が濾過されたものなのです。
脳脊髄液の役割とは?
1.脳と脳神経の保護
頭蓋骨と脳の内部にくまなく満たされ、クッションや緩衝材のような役割を果たしており、このおかげで、私たちは脳に多少の衝撃を受けても耐えられるのです。
2.脳に栄養を補給し、老廃物を排出する
血液が全身を巡って、体中に栄養を届け老廃物を排出するように、脳脊髄液も同じような役割を果たします。
このように、脳にとって非常に重要な役割を果たす脳脊髄液。
重要なだけに、脳脊髄液の流れが悪くなると、体には様々な不調が出てきてしまいます。
実は血液もリンパ液もそして脳脊髄液も体内を巡り循環することで意味を成します。
つまり、流れが滞ってしまうと、それはそのまま体の様々な不調に繋がっていくのです。
具体的に脳脊髄液の流れが滞ると体にはどんな不調が起こるのでしょうか?
1.身体がかたくなる
脳脊髄液の流れが滞ると、背骨に通っている脊髄の流れも悪くなり、筋肉が硬直しやすくなります。その結果、体の柔軟性がなくなります。
2.風邪などをひきやすくなる
自律神経のはたらきを乱し、また、老廃物を体外に排出する作用が乱れてしまうので、免疫力が低下します。
3.頭痛
脳脊髄液の流れが滞ることは、脳内を圧迫することにもなります。
そのため、頭痛を起こしやすくなります。
4.自律神経失調症
自律神経の乱れを引き起こし、動悸・息切れや不眠症、耳鳴り、低体温や手足などの痺れといった様々な症状があります。
脳脊髄液の流れが悪くなる原因は
「頭蓋骨のズレ」と言われています
頭蓋骨は15種類の骨が22個組み合わさり構成されています。
その空間の中に脳が収まり、それぞれの骨の間には関節があり、ごくわずかですが動いています。
健康な状態であれば、頭蓋骨は全体に均一に膨らんだり、縮んだりを繰り返していますが
何らかのズレや隙間が出来たり、頭蓋骨が広がって肥大し頭皮が引っ張られて血管が圧迫するなど影響を及ぼしてしまうのです。
頭蓋骨のズレの原因は
・足を組む
・噛み癖(左右どちらかで噛む)
・荷物を同じ手で持つ
・頬杖をつく
・横向きで寝る
脳は体のすべての器官の「司令塔」的存在です。脳脊髄液が保護している神経だけでなく、肺などの呼吸器官や、胃腸などの消化器官、心臓、目や耳などの知覚器官、生殖器官や泌尿器まで、体中の各箇所の健康状態に少なからず影響を与えます。
脳脊髄液の巡りを良くするには?
まずは頭の筋肉の硬さをとること。
ヘッドマッサージなどで緊張を緩めることにより、頭蓋骨のズレも調整されます。
そして血液とリンパ液の巡りを良くすることも重要なのです。
血液とリンパの流れを良くするにはオイルマッサージなどが有効だとされています。
脳脊髄液の巡りが整うと自然治癒力が高まり、自律神経が整い、副交感神経が働いリラックスもできます。
頭痛や不眠など気になる方は
ちょっと頭を触ってみて硬くなっている場合は
脳脊髄液の巡りが悪くなっているかもしれません。
足を組む、寝る姿勢など日頃のクセを少し意識し、頭の緊張を取るとこを意識してみてくださいね☺️

ご予約はこちらから💁♀️
ファティーグ・ファクターとは

忙しいと「ちょっと疲れたなぁ」と感じても休む時間がなかったり、もっと頑張らないと…とその疲労がどんどん蓄積されてしまうことも。
疲労とは発熱や痛みなどの兆候と合わせて「三大生体アラーム」と言われ、ホメオスタシス(恒常性)の異常を知らせる兆の一つです。
最近耳にするファティーグ・ファクター(疲労因子FF)という言葉
実は、“疲労”というのはハッキリとして正体がわかっていませんでした。
疲れた~の原因は、医学的に明らかになっていなかったのです。
最近そのメカニズムが解明され、
“疲れ”には「疲労因子FF」という物質が関わっていることが分かったそうです。
疲労因子ファティーグファクター(FF)とは?
疲労度合を示すタンパク質のことです。
実は、このタンパク質がカラダに蓄積すると、細胞死(アポトーシス)を促進させ、
心臓病や糖尿病などの生活習慣病の原因になると考えられています。
怖いのは「隠れ疲労」
FFは蓄積されていも、それに気づかないことがあります。
それは、脳内の「報酬系回路」が働くことに原因があり、
「報酬系回路」とは、とても忙しい場合でも、その仕事に並々ならぬ“やりがい”を感じていたり、
使命感や責任感を感じている場合、または、仕事に対して「ご褒美」のような報酬がある場合など
脳が疲労を無視してしまうのです。
実際の疲労と、自覚できる疲労に差があります。
疲労因子FFが生まれる原因
人間が疲労する仕組みはというと…人間が活動すると、細胞の中で大量の酸素が消費されます。
同時に、活性酸素が発生します。
そして、この活性酸素が、細胞をどんどん傷つけ、酸化(=サビ)させていきます。
このとき、FFが発生するのです。
主な疲労原因(ファティーグ・ファクター)
疲労は「身体的疲労」「精神的疲労」「神経的疲労」などが複雑に絡み合っています。
生活スタイルによって原因は人それぞれですが、だからこそ、ご自身の疲労が何を知ることは、大切なのかもしれません。
・意外にも食べ過ぎは疲れの原因に
栄養バランスを整え、食事の質を高めてゆくことは大切ですが、過食による内臓の働きすぎ(身体的疲労の一部)が疲れの一因になるともあります。
疲れた時は栄養のあるものを食べて元気を出そうするよりも、胃腸を一旦休息させるほうが効果的な場合も。食べても調子が回復しない時は、一旦胃腸を休めてみるのもよい方法です。
お疲れは、どのタイプ?
気持ちが疲れを凌駕する人→ 身体的疲労タイプ
朝早くから夜遅くまで精力的に働くビジネスパーソンなどに多いパターン。
肉体疲労が蓄積していることに気が付かない場合があるようです。
生真面目さゆえのオーバーヒート→ 身体的精神的疲労の複合タイプ
生真面目さから手抜きが出来ず、精神的な負荷がかかりやすいタイプ。
人間関係のストレスに悩む方もこのタイプに分類される場合が多いそうです。
スマホやpcなど24時間デジタル漬け→ 神経的疲労タイプ
暇さえあればスマホの画面を見続けている人や、PC画面を見ることが多い人がこのタイプ。
疲労を回復させる方法
自分が疲労を自覚していてもしていなくても、やはり「適切な休養」が必要なのです。
疲労回復物質FR
(ファティーグ・リカバリー・ファクター)
FRは、疲労因子FFが体内に発生すると機能し始め、
FFによって傷ついた細胞を修復、
FFを除去する働きがあるそうです。
FRを増やす方法
少し疲れて、少し休む。
FRはFFが発生すると機能を始めます。
少しだけ運動したり、入浴したりして、軽い疲労感を覚えると、FRが機能するわけです。
やはり睡眠
その最大の特効薬は、なんといっても、夜の心地よい睡眠に尽きます。
疲労が深刻化・慢性化しないように、「その日の疲れはその日のうちに解消」することを目指せたらいいですね。
質の良い眠り、そして自分にとって良い「リラックス法」を見つけ、疲労を溜めない身体作りを心がけてくださいね☺️
 ご予約はこちらから💁♀️
ご予約はこちらから💁♀️
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku