♪明日がちょっと良くなる♪かもしれないブログ
体の潤いの源【津液】

東洋医学では体を流れる色のついていない水(水分)のことを津液(しんえき)と言います。
簡単にいうと津液のはたらきは、
全身を潤すこと
皮膚や毛髪、胃や腸などを潤すとともに、関節の働きを円滑にする管理などをしています。
秋は乾燥が始まるので、この津液が不足しやすくなったり、巡りが悪くなりやすいのです。
この状態を、津虚(しんきょ)といい
どのような症状があらわれるかというと
流れている川の水はキレイですが、停滞して濁ってしまうイメージです。
手足のむくみ、顔のむくみが代表的な症状ですが、お腹に余分な水がたまっていると、お腹のチャポチャポ音や食後に眠くなる、嘔吐や下痢などの症状が現れたり、全身がだるいといった状態になります。
逆に花粉やアレルギー性鼻炎などは余分な水を貯めているための症状です。
津液不足や巡らない原因は
水分をあまりとらないから、という単純なものではなく
寝不足や過労、加齢、生活の乱れなどで起こり
水分を摂るだけでは津液不足が改善されることにはなりません。
血と同じく津液も、夜体が休んでいるときに作られるため、夜の時間帯にしっかり休むというのも大きなポイントです。
また、疲れがたまったり、ストレスなどで気の流れが滞ることで、体の中に余分な熱がこもります。
こうした熱も津液を消耗させる原因となりますので
やはり休息やリラックスも大切なことです。
また、栄養の不足が原因で津液不足になることもあれば、食べ過ぎや偏食など食生活のバランスが悪くなることで、脾や胃の経絡のバランスが崩れ、津液の不足や滞りを生む原因となることがあります。
特に食生活に気を使い津液の精製と運行をスムーズにすることも改善にポイントです。
体の潤いが足りなくなると
心の潤いも足りなくなります。
乾燥の季節「潤い」が不足しないよう
休息、食事…大切にしましょう。

ご予約はこちらから💁♀️🔽
肩こり、自律神経の乱れ…ほぐすべきは〇〇!

寝ているはずなのに、疲れがとれない、だるい、頭が重い…
そんな不調を慢性的に感じている人は、自律神経が乱れている可能性が高いです。
特にデスクワークなどで
肩がこったら肩を揉む、首が疲れたら首を回すということはすると思いますが、実はほぐしてほしいのが鎖骨です。
鎖骨は肩甲骨や胸骨とつながっているので
鎖骨が圧迫されると肩の関節の動きが悪くなります。
そして鎖骨まわりは多くの血管や神経、リンパが密集している部分で
鎖骨の圧迫を放置しておくと、血流の悪化によって老廃物が溜まりやすくなり、肩こりや首こりの原因につながるのです。
鎖骨まわりをほぐすことで、滞った血流やリンパの流れを促進し、肩こりの改善や自律神経を整える効果が期待できます。
その理由は、鎖骨を押すことで、脳の扁桃体の緊張が緩むと考えられています。
扁桃体は、人間の本能的な部分を司る大脳辺縁系の一部で、その部分の緊張が緩むことで、体の緊張をほぐすだけでなく、心の緊張も緩ませることができます。
🌿簡単な鎖骨ほぐしセルフケア
・右の鎖骨の下を押して、圧痛点(最も痛い場所)を探す。
・①を押したまま、首を前に倒し、軽く右に傾けたまま、右側にひねって2分間キープ。このとき鎖骨の痛みが最も楽に感じられる角度を向くよう意識する。左側も同様に行う。
強く押す必要はなく、痛気持ちよい程度で大丈夫です。押している側に顔を向けて2分間じっとしていると、しだいにその圧痛が取れてくるはずです。
もし、それでも圧痛が取れなければ、顔を逆方向に向けてみてください。
症状が体の片側だけの場合でも左右両方行いましょう。お好きなタイミングで、1日3回くらいを目安に。
奏では鎖骨もしっかりと施術しています。
ここが緩むと呼吸が深くなり、お顔周りもスッキリ★
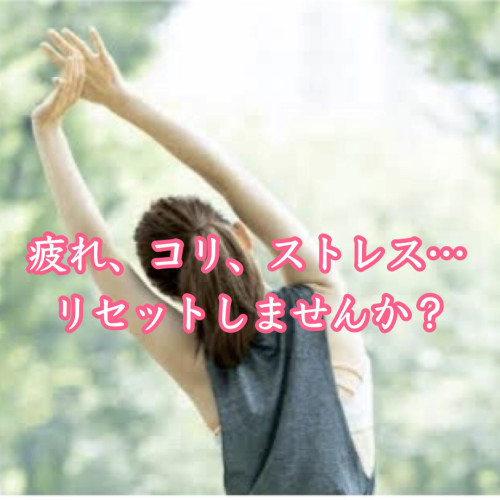
ご予約はこちらから💁♀️🔽
ストレスとの付き合い方【3つのR】

「ストレス」というものは
ネガティブなイメージがありますが、決してストレスそのものは悪いものではありません。
ざっくり言うとストレスは緊張と弛緩でいう「緊張」です。
緊張があるから弛緩があるわけで
その緊張(ストレス)を乗り越えたときに達成感をもたらしてくれたり、自信を持つことや成長する糧になることもあるからです。
でも過剰なストレスは心身にさまざまな不調をもたらします。
・体に起こる不調
頭痛、肩こり、不眠、食欲低下、便秘、下痢、めまい、動悸、など
・心に起こる不調
不安、イライラ、気分の落ち込み、不眠、集中力の低下、など
・行動に起こる不調
飲酒や喫煙量の増加、食欲亢進、欠勤や遅刻の増加、仕事でのミスの増加、など
ストレスへの対処法には「3つのR」が大切と言われます。
①レスト(Rest)-休息・休養・睡眠-
オンとオフを切り替え、休息をしっかりとることが重要です。
栄養のある食事を摂り、夜はしっかり睡眠をとるなど規則正しい生活を心がけましょう。
快適な睡眠のためには、就寝前のスマホ操作を控え、読書や音楽をなどでリラックスするのがおすすめです。
②レクリエーション(Recreation)-運動・娯楽・趣味・気晴らし-
休日には趣味や娯楽など、好きなことに専念する時間をつくりましょう。
好きなことに打ち込むことは、疲労やストレスの解消に役立ちます。
③リラクックス(Relax)-ストレッチ・瞑想・音楽・アロマ-
忙しいときや緊張しているときは、つい体に力が入ってしまいます。
そんなときは、ストレッチや瞑想などで筋肉の緊張をほぐしたり、呼吸を整えたりなどのリラクゼーションを取り入れましょう。
そして
自分の考え方のパターンを知る、他の考え方を探してみる、など「捉え 方を少し変えること」で心身にかかるストレスを減らせることもあります。
本来、思い通りにならないために不満や不安、怒りなどが日々蓄積されることによってストレスが発生すると言われます。
このストレスをなくすには
究極に言えば「思いを持たない」ことです。
[思いを持たない]=一種のマインドコントロール法ですが、
ストレスがある時こそ、自分と向き合い、考え方の癖を変えるきっかけになるこのもあります。
思いを持たないことについては
また今後書きたいと思います。
そして体と心はひとつです。
まずは体の休息、ケアをすることも大切なことです。

ご予約はこちらから💁♀️🔽
https://izumi-kanade.com/free/yoyaku
【冷え症】と【低体温】の違い

いよいよ、本格的に気になってくる「冷え」
多くの方が持つお悩みではないでしょうか。
冷えについて意外と知られていないことがあります。
一般的にいう冷え症とは、手や足など体の末梢への血流が悪くなり、体温が36度以上で正常でも
指先などが冷えていることを指します。
一方「低体温」は体の深部体温が低い状態で、最近36℃未満の低体温の人が増えているそうですが
このふたつはまったく別ものなのです。
低体温はそもそも身体の深部温度が低く、身体の中から冷えるために自覚しにくいのが特徴です。
低体温になると酵素が活性化されないため、基礎代謝や免疫力が弱まり、疲れやすくなり
肌荒れや頭痛、肩こりなどの不調を起こしやすくなります。
なんと体温が1℃下がると免疫力は33%も低下すると言われます。
低体温はもともとの体質というよりも生活習慣から
くることが多いようです。
- 食生活
- 運動不足
- ココロのストレス
- 睡眠不足
低体温はとにかく温める生活をすることで少しずつ改善されます。
●入浴…5分でも10分でも毎日湯船につかるようにする
●スクワット…下半身の脂肪が落ちるとともに、必要な筋肉も付くので、ふくらはぎや太もも、腰などが引き締まった下半身をつくりながら、血行を良くすることができます。
●白湯を飲む…朝は1日の中で最も体温が低い状態なので、朝は冷たい水ではなく、さゆを飲みましょう。夜寝る前も飲むことで体が温まります。
●腹巻き、カイロ、湯たんぽ…お腹、足、首といわれる部分をなるべく冷やさないようにしましょう。
低体温を改善するとこんなに良いことが
◆ 基礎代謝が上がり、太りにくい体に
◆ ストレスに強く病気になりにくい
◆ 新陳代謝が活発になり老化防止に
◆ 内臓脂肪の解消で、メタボ対策に
◆ 腸が活発になり便秘やがんの予防に
◆ 脳の血行が良くなり記憶力の向上に
免疫力を高めて健康を維持するためにも、まずは自分の平熱を知り、低体温の場合は改善策を試してみましょう。
もちろん定期的な運動やマッサージなどで
意識的に血流を良くするということも大切です。
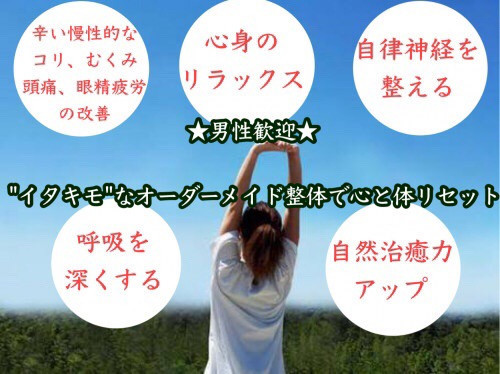
ご予約はこちらから💁♀️🔽
冬に向かう11月の過ごし方

11月が始まり、だんだんと寒くなってきましたがこの時季には「やたらに眠い」「何をするにもおっくう」「集中できない」といったお悩みを感じる方が増加します。
実は、これは日照量の不足と関係があります。
日が短くなることで、なぜそんなに不調が現れるのという理由は
日光に当たることで生成される「セロトニン」と「ビタミンD」の不足です。
「セロトニン」は心のバランスを整えてくれる脳内物質のひとつで、心と身体を安定させ、幸せを感じやすくする働きを持つと言います。
一方で、最近ビタミンDが心や神経のバランスを整える脳内物質セロトニンを調節することがわかったそうです。
これらの不足により
<秋冬のよくある不調>
・食欲が高まり、甘いものや炭水化物が食べたくなる
・朝起きられない、日中も眠い
・気分が落ち込む、気力がない
・集中力ががくんと落ち、いつもできていた家事や仕事ができない
・人づきあいをしたくなくなる、面倒になる
別名、冬季うつ・季節性うつなどと呼び、
春に向かえば自然に回復もしますが
基本的には生活習慣を改善することで、不調を軽減・改善できます。
特に意識的に「陽に当たる」ことが不調の改善につながります。
定期的に外に出たりして目から取り込まれる光量不足を補えば、「セロトニン」と「ビタミンD」の生成を助けることができます。
また陽の光のおかげで体内時計が調整され、自然界の朝・昼・晩のリズムと体のリズムが噛み合いやすくなるので
なかなか眠くなれず、就寝・起床時間にばらつきがある方にもおすすめです。
積み重なったストレスや疲れは体の不調となって現れ、解消には時間がかかってしまいますし
日照時間の不足は、じわじわと私たちの心身に影響を与えます。
おいしいものを食べたり、なるべくリラックスすることで
「疲れ、ストレスはためずに、まめに解消」
を心がけ、早めに回復することこそ、蓄積を防ぐ最良の方法です。
